COVID-19パンデミック中、栄養不良の二重負荷を予防するための取り組み
低栄養と過栄養が個人内で異時性に、または集団内で同時期に存在する現象は「栄養不良の二重負荷(栄養障害の二重負荷)」と呼ばれ、近年、栄養関連で頻繁に取り上げられるテーマの一つだ。栄養不良の二重負荷の問題が提唱された背景の一つに、持続可能(サステナブル)な社会の発展、つまり「SDGs(Sustainable Development Goals)」を目指す機運の高まりがある。

栄養不良の二重負荷(栄養障害の二重負荷)とは
日本人が抱える"栄養障害の二重負荷"を解決に導く 3つの取り組みに「84 selection 2019」を授与(日本栄養士会)ただ、目下の世界の状況、具体的には新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックという状態も、栄養不良の二重負荷の問題と深くかかわっているようだ。栄養失調と肥満は感染症に対する感受性を高め、かつ、感染症罹患時には体タンパクの異化作用が亢進し、栄養失調、筋肉消耗のリスクが高まるという双方向性の関連があるという。
このような視点でCOVID-19と栄養の関連を考察したナラティブレビュー論文が発表された。その要旨を紹介する。
COVID-19パンデミック中に考慮すべき二つの栄養状態
COVID-19パンデミックと栄養状態の関連を指摘する報告は増えているものの、これまで十分には両者の関連が検討されていない。しかし栄養状態の悪化は免疫応答の低下とウイルス感染を含む感染症のリスクの増加に関連しており、COVID-19のリスクも高めると考えられる。
一方、COVID-19罹患時には代謝亢進やエネルギー必要量の増加、消化器症状(吐き気、味覚消失、嘔吐、下痢など)を含むいくつかのメカニズムを通じて、栄養状態に悪影響を与える可能性がある。さらに、都市封鎖は一般生活者の栄養バランスに影響を与えることは、容易に想像可能だ。
高齢者
前記のようにCOVID-19感染は、直接的かつ間接的に複数の経路で栄養状態を悪化させる可能性があるが、高齢者はその直接的な影響を最も強く受ける集団だろう。味覚・嗅覚障害は食欲不振につながり、食欲不振はCOVID-19感染で観察される炎症性サイトカインレベルの上昇にも関連していると考えられる。炎症反応亢進は異化を亢進させ骨格筋を萎縮させる。加えて、COVID-19による長期間の臥床が筋肉の喪失をさらに加速させる。実際、COVID-19患者の少なくとも3分の1が入院時に栄養失調を示し、高齢者ではより高率であることが報告されている。
一方、先進諸国では高齢者でも肥満者が珍しくない。肥満がCOVID-19への感受性および重症化と関連していることはパンデミック初期から報告されている。高齢者の肥満はCOVID-19リスクとして過小評価されている可能性があり、とくに筋肉量低下を伴うサルコペニア肥満はCOVID-19罹患に関しても極めてリスクが高いと考えられる。
また、COVID-19に罹患していない高齢者であっても、都市封鎖などの政策の影響により、栄養状態が低下し得るだろう。高齢者の生活をサポートする体制が必要とされる。
乳幼児
COVID-19は高齢者で重症化しやすく、若年者は重症化しにくい。ただし、低~中所得国の小児、乳幼児は栄養失調状態にある児が多く、先進国の状況とは異なる。さらに、今後の継続的な観察が必要ではあるが、COVID-19のパンデミックは発育阻害(慢性栄養失調)、微量栄養素欠乏症などを引き起こしてくる可能性も想定される。
西側先進諸国では反対に、都市封鎖による身体活動量の減少が、小児の肥満を促すように働くだろう。また、母体の子宮内でパンデミックという特殊な状況に遭遇した児が何らかの影響を受けており、出生後にその影響が現れる可能性にも注視すべきかもしれない。
COVID-19パンデミック中の栄養管理
現在のような特殊な状況ではなく平常時でも、疾患のリスクや栄養失調の可能性をスクリーニングし早期に見い出すことは重要で、COVID-19パンデミック中もすべての入院患者の栄養状態を評価すべき。栄養失調のスクリーニングにはいくつかのツールがあるが、COVID-19パンデミック中には適用が困難なものもある。
例えば、独居の高齢者が入院した時、既に重度の呼吸不全、認知機能低下、意識レベルの低下があれば、最近の食事摂取量や体重の変化に関する情報を患者から得られないことがある。このような場合、通常では介護者や血縁者から情報を入手するが、外出自粛等のために患者との交流が保たれておらず、直近の状況は不明のことがある。このような場合でも、可能な限り栄養状態を評価すべきだが、それには、たとえ精度が十分でなくても、ふくらはぎ周囲長の計測も検討すべきだろう。小児の場合は、臨床に利用できる成長チャートなど、比較的幅広い選択肢があり、疾患等により適宜判断して用いる。
COVID-19罹患時のタンパク質に関して、高齢者では筋肉の喪失を防ぐために、少なくとも1.0g/kg/日が必要とされる。急性または慢性の疾患を有する場合、タンパク質摂取量を1.2~1.5g/kg/日にまで増やす必要もある。さらに重篤なCOVID-19では、高異化に対応するために、2.0g/kg/日まで増やすことも考慮される。小児の場合、体重、年齢、疾患重症度に応じて設定することになる。
タンパク質の同化/異化は、尿中クレアチニンや尿素窒素のモニタリングによって判断することになる。その他、栄養状態を評価するための生化学的マーカーとして、ヘモグロビン、総蛋白、血清コレステロール、リンパ球数などを評価し、重度の栄養失調ではリフィーディング症候群に留意しつつ、摂取エネルギー量の目標を徐々に上げていく。
人工呼吸管理を必要とするCOVID-19患者のように経口摂取不能の場合は、合併症を抑止するためにできるだけ早い段階から経腸栄養を開始する。既に複数の研究で、COVID-19患者のビタミンD欠乏症と免疫系機能障害との関連が示唆されており、微量栄養素の状態を適切に管理することがウイルス感染や疾患の重症化の予防に役立つ可能性があると考えられる。
文献情報
原題のタイトルは、「Joint Effort towards Preventing Nutritional Deficiencies at the Extremes of Life during COVID-19」。〔Nutrients. 2021 May 12;13(5):1616〕
原文はこちら(MDPI)










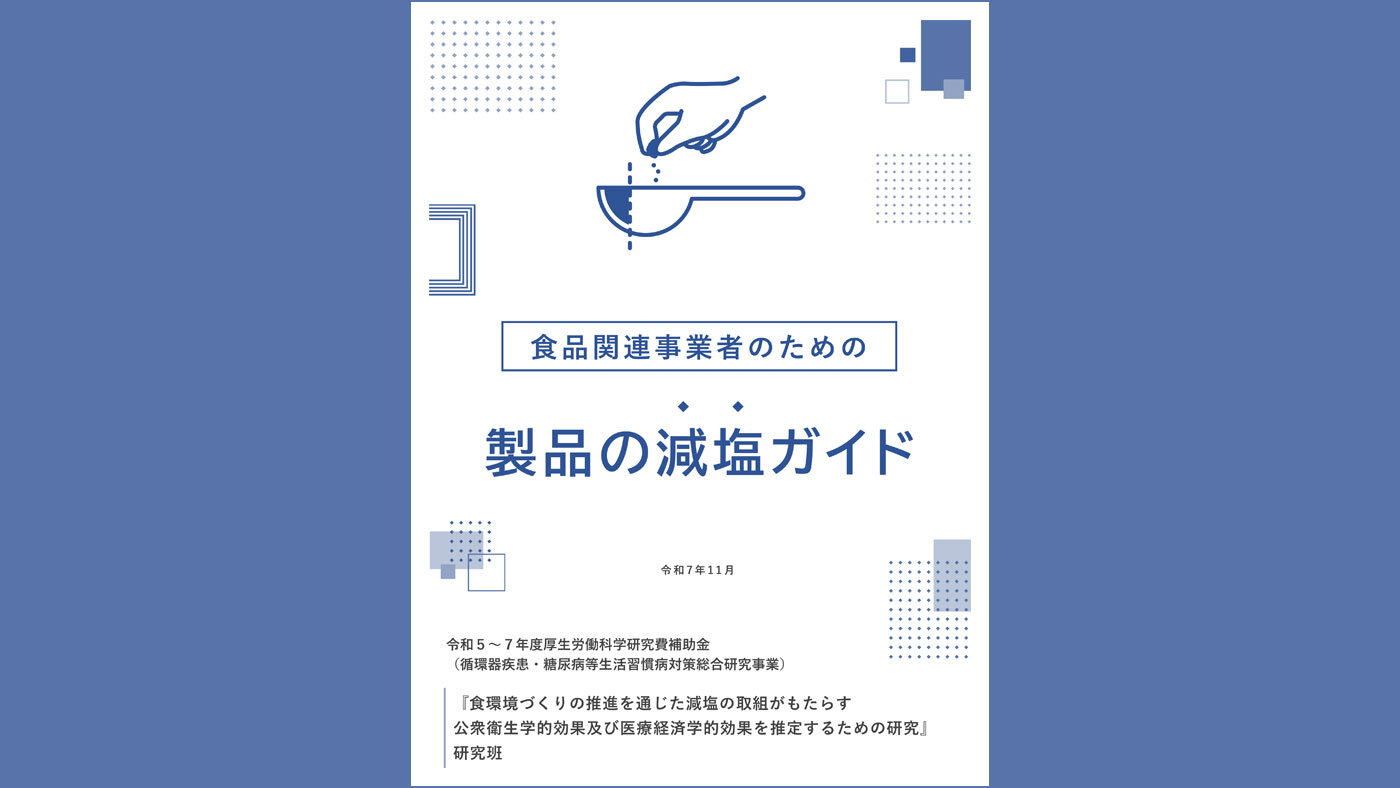












 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










