食事日記と個別化フィードバックの組み合わせで栄養状態が改善し、健康行動が長続きする 東北大学
食事日記を継続的に記録し、そのフィードバックを得ることで栄養摂取が改善し、それによってウェルビーイングが向上する可能性のあることが明らかになった。東北大学などの研究グループの研究によるもので、「Nutrients」に論文が掲載されるとともに、大学のサイトにプレスリリースが掲載された。著者らは、生活習慣病予防のための健康支援プログラムや、企業の健康経営への応用にも期待される成果だとしている。

研究の概要:健康目標に対する行動を、短期でなく、長期に継続する鍵は何か?
生活習慣病の増加は社会的な課題であり、若い頃からの健康的な生活習慣が重要とされる。しかし、その効果が見えづらいため、健康的な食習慣を維持することは難しく、多くの人が途中で挫折してしまう。これを背景として、東北大学と花王(株)の共同研究グループは、将来の健康に向けた良い習慣を継続させる脳の仕組みに注目し、支援する方法を検討した。
これまでの研究により、脳の前頭極(ぜんとうきょく)※1という部位が、近い将来に向けた行動の維持(GRIT〈闘志や気概、行動持続力〉)に関連することは示唆されていたが、遠い将来の健康目標に対する行動継続への関与の詳細は不明だった。そこで前頭極の構造と健康行動の持続力との関連を調べるとともに、各個人に合わせた個別化フィードバックによる食習慣改善の後押しが可能かを検証した。
その結果、個別化フィードバックが長期的な健康行動の維持とウェルビーイング(人生を享受しているという感覚)の向上に有効であることを実証するとともに、前頭極の脳構造が行動維持能力に関与することを明らかにした。
※1 前頭極:大脳の前頭前野の最前部(額の裏あたり)に位置する領域で、ヒトではとくに発達している。意思決定や計画立案、複数の課題の切り替え、将来の見通しを立てるといった高度な認知機能に関与し、目標に向かって行動を持続する働きをもつとされている。
研究の詳細:脳の前頭極の構造的な特徴と、健康行動の継続性の関連を検討
研究の背景:効果をすぐに実感できない行動を、長続きさせるのに必要な要素とは
近年、糖尿病や高血圧などの生活習慣病が増加し、若いうちからの健康的な生活習慣の定着が社会的に求められている。しかし実際には、大学生を中心とした若年層で偏った食事や朝食の欠食が増え、将来の生活習慣病リスクやウェルビーイングの悪化が指摘されている。
健康行動は、始めることは比較的容易だが、すぐに目に見える変化がないため継続が難しく、途中で挫折する人も少なくない。そのような健康行動を長期間維持するためには、「GRIT(行動持続力)」が重要とされる。
一方、本研究グループによる先行研究から、行動を持続する力に脳の前頭極(frontal pole cortex;FPC)が深く関与していることが明らかになっている。FPCは、目標を見据えた行動や自己コントロールに重要な役割を果たしていることが示唆されていたが、健康行動のような予防的行動で、明確な達成目標のない長期的な行動の継続についての関連は明らかでなかった。
本研究では、この前頭極の脳構造的特徴と個別化されたフィードバックが、若年層の健康的な食習慣を維持するうえで、どのような役割を持つのか明らかにすることを目的とした。
今回の取り組み:大学生50人を2群に分け、1群には食事記録を個別化フィードバック
本研究では、平均21歳の健康な大学生約50人を対象に27日間の実験を行い、毎日の食事内容を記録する「食事日記」の継続状況や食生活・心理状態の変化を調べた。
参加者を無作為に二つのグループに分け、一方の個別化フィードバック(PF)群には提出された日記データを分析し、各自の現在の食習慣の特徴や将来起こり得る健康リスクについて具体的なフィードバックを数日ごとに提供した。もう一方の対照(コントロール)群には、個人のデータに基づかない一般的な栄養に関する情報のみ(例えば「野菜をしっかり摂りましょう」等)を提供した。両群とも3日に一度、フィードバックを受け取り、その翌日から再び食事日記を続ける流れを繰り返した。
両群の食事日記の提出状況を比較したところ、PF群は対照群に比べて日記の提出数が一貫して多いことが明らかになった(図1)。とくにフィードバックを受け取った直後の日は、両群とも提出率が上昇する傾向が見られたが、その効果はPF群で顕著だった。また、27日間の介入期間全体を通して食事内容の変化を分析したところ、PF群は対照群よりもカルシウム、ビタミンA・C、食物繊維などの重要な栄養素の摂取量が有意に増加していた(図1)。さらに心理面への影響について、実験前後で不安傾向の変化を比較したところ、PF群では特性不安※2スコアが有意に低下し、対照群との差が確認された(図1)。
図1

※2 特性不安:個人の不安傾向を表す心理学的指標。状態-特性不安検査(STAI)によって測定され、数値が高いほど「緊張しやすい・心配性である」といった持続的な不安傾向が強いことを示す。本研究では介入前後で特性不安スコアを測定し、その変化を評価した。
一方、対照群(一般的アドバイスのみ)ではPF群ほど行動の変化は大きくなかった。また、誰がより食事記録を継続できたかを左右する要因として、脳の前頭極の構造特徴がみられた。
参加者全員のMRI脳画像から前頭極の構造的特徴を測定し(灰白質の厚みや神経繊維の密度指標など)、日記提出数との関係を分析したところ、対照群では前頭極が発達している人ほど食事日記を継続する傾向が強いことがわかった。具体的には、対照群内では前頭極の皮質の厚みが厚い人ほど日記提出日数が多く、他の指標(ミエリン密度やFA※3値が高い人)も同様の傾向が見られた(図2)。これは、個別の支援がない状況では、前頭極が持つやり抜く力(GRIT)に個人差があり、その差が健康行動の継続に影響を与える可能性を示している。
図2

※3 FA(Fractional Anisotropy):拡散MRIにより得られる指標の一つ(拡散テンソル指標)。脳内の神経線維の走行方向の揃い具合(各向きの拡散の偏り)を示し、白質(脳の中の神経線維束)の状態を反映するとされる。値が高いほど神経線維の配向が揃っていることを意味する。
一方でPF群では、前頭極の構造と日記継続との相関関係はみられず、脳構造にかかわらず、全員が高いレベルで行動を継続できていた。言い換えれば、個別化フィードバックの介入によって、前頭極の性質に起因する「続けられる人・続けられない人」の差が解消された可能性がある。
今後の展開:無理なく続けられる健康プログラムでウェルビーイングも向上
研究グループでは今後、脳の前頭極の働きをさらに深く理解し、どのように個人差が健康行動やウェルビーイングに影響を与えているのかを詳細に調べ、とくに個別化フィードバックが脳の可塑性※4にどのような影響を与えるかを縦断的に調査し、その神経メカニズムを明らかにする方針。また、このような脳科学的知見を基盤とした新しい健康支援手法を確立し、個人の脳特性に応じた、より効果的な健康習慣の維持・促進を押し進めていくという。
さらに、企業や自治体での実用化を視野に入れ、職場や地域で誰もが無理なく続けられる健康増進プログラムの開発・実装を推進し、職場や学校、地域社会などさまざまな場面での健康増進やウェルビーイング向上に貢献することを目指すとしている。
※4 脳の可塑性:脳の構造や機能が経験によって変化する性質。
プレスリリース
健康行動を支える脳の仕組みを解明 ─ 脳の前頭極と個別化フィードバックが若者の食生活改善とウェルビーイング向上の鍵に ─(東北大学)
文献情報
原題のタイトルは、「The role of frontal pole cortex and personalized feedback in sustaining future-oriented healthy dietary behaviors」。〔Sci Rep. 2025 May 2;15(1):15416〕
原文はこちら(Springer Nature)











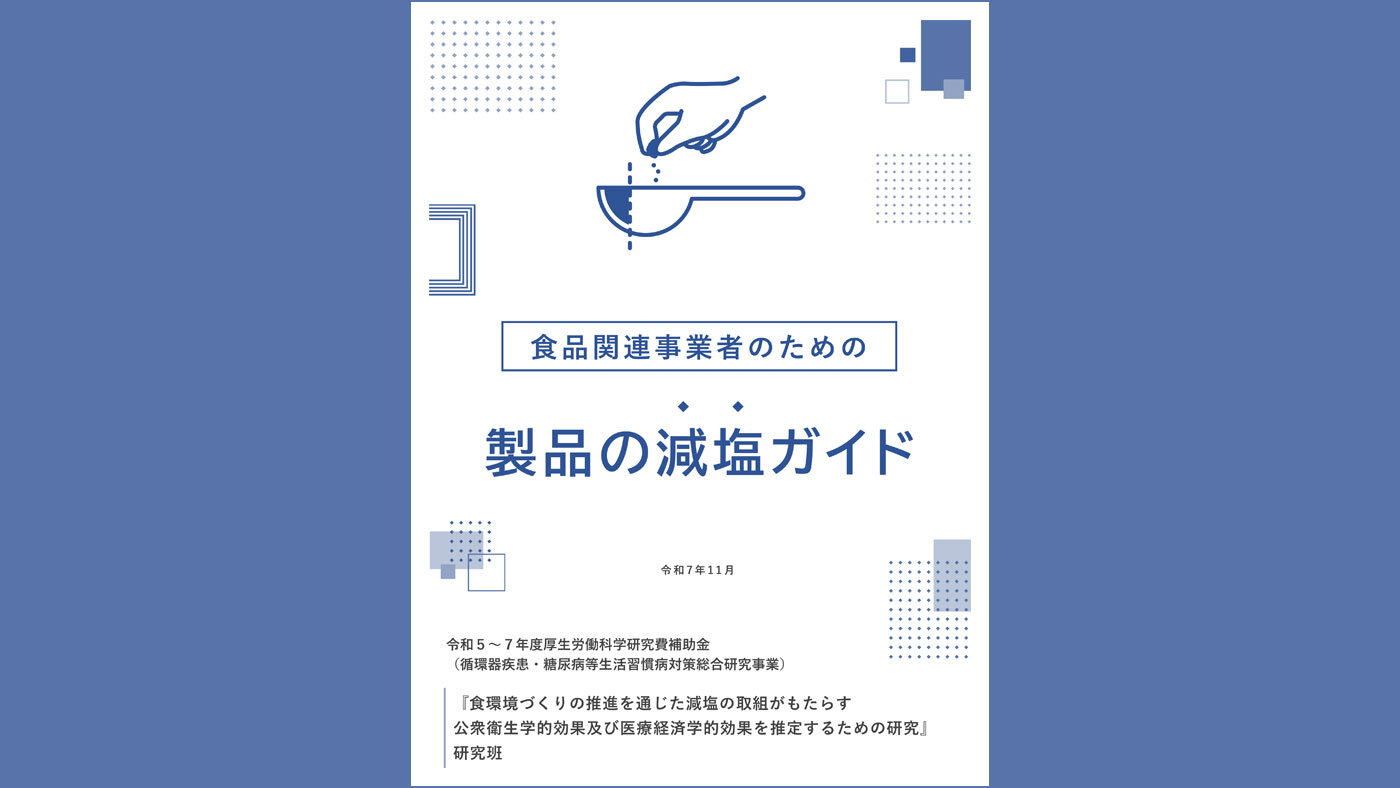











 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!











