筋トレ+中鎖脂肪酸で、脳卒中後のリハビリ効果が拡大する
代謝や筋肉機能に対する潜在的なメリットがあるとされる中鎖脂肪酸(MCT)が、脳卒中後のリハビリテーション効果を押し上げる可能性が報告された。筋力トレーニングにMCT補給を並行して行うことの相加的効果が認められるという。熊本リハビリテーション病院サルコペニア・低栄養研究センターの吉村芳弘氏らの研究の結果であり、国際誌に論文が掲載された。

栄養介入と筋トレが重要な、脳卒中後リハビリテーション
サルコペニアは高齢者に多く、とくに脳卒中後などの機能障害がある場合にはよりリスクが高くなる。また、脳卒中後のサルコペニアの存在は、リハビリテーションの妨げとなり、転帰不良のリスクを高めてしまう。
サルコペニアの改善手段として現在、筋力トレーニングの重要性とともに栄養介入が期待されている。栄養介入では、タンパク質食品の摂取に加えて近年、中鎖脂肪酸(medium-chain triglycerides;MCT)の機能性が注目されている。MCTは摂取後速やかに吸収されケトン体となり、エネルギー基質として利用されるという特徴がある。この特徴が、筋量や筋力の低下を抑止するように働くのではないかと考えられており、フレイルの高齢者を対象とする研究では、MCT摂取により等エネルギー量の長鎖脂肪酸を摂取した場合に比べて筋力が有意に改善したと報告されている。
一方、サルコペニアに対して筋トレや栄養による介入の個別効果のエビデンスが増えてきているが、両者を並行して行った場合に相加的効果がみられるのか否かという点は明らかになっていない。そこで吉村氏らは、脳卒中後のリハビリ中の患者を対象に、筋トレにMCT補給を上乗せすることの意義を検討した。
脳卒中後のリハビリ入院中に、筋トレ、MCT補給、および両者併用でFIMの変化を比較
この研究は、単施設での後ろ向きコホート研究として実施された。2016~23年にリハビリテーション病棟に入院した脳卒中後の患者連続1,080人を解析対象とした。なお、入院時に意識変容を認めた患者や解析に必要なデータが欠落している患者などは除外されている。
主な特徴は、年齢75.6±9.3歳、男性54.1%で、脳卒中の病型は脳梗塞が63.6%と多くを占め、脳卒中前の機能的独立度(modified Rankin Scale;mRS)は中央値0点(生活に全く支障なし)、BMIは同22.3であり、サルコペニアに関連する指標としては、握力が同18.8kg、骨格筋量指数(skeletal muscle mass index;SMI)が同6.3(生体電気インピーダンス法で測定)だった。また栄養状態はMini Nutritional Assessment–Short Form(MNA-SF)で評価され、中央値は7点だった。
BMIが18.5未満、MNA-SFが7点以下などでMCTを補給
入院中には全員に対して多職種による個別化されたリハビリが行われ、そのほか、適応がある場合は、椅子立ち上がり運動による筋トレやMCT補給が行われた。
MCT補給の適応は、BMI18.5未満、MNA-SF7点以下、SMIが男性7.0未満、女性5.7未満、嚥下障害(Food Intake LEVEL Scalet〈FILS〉7点以下)、および通常の栄養管理では体重減少の懸念がある場合などであり、MCT強化米として提供された。MCT強化米は1膳あたり11.8gのMCTを含み、エネルギー量は305kcalだった。一方、MCT補給の対象とされなかった患者には、通常の米飯(1膳あたり168kcal)が提供された。なお、MCTは通常の病院食には含まれていないことから、MCT補給の対象でない患者群は入院中にMCTをほぼ摂取しなかったことになる。
全体として、解析対象1,080人のうち、追加介入としてMCT補給のみを行った「MCT単独群」が126人、椅子立ち上がり運動のみの「筋トレ単独群」が468人、両者を並行した「MCT+筋トレ群」が58人であり、両者いずれの追加介入も行われなかったその他の患者群を「対照群」とした。エネルギー摂取量は全体の中央値が27.3kcal/kg/日、タンパク質摂取量は同1.0g/kg/日であり、追加介入を行った3群間の比較で有意差はなかった。
介入効果は入院期間中の機能的自立度(FIMスコア)の変化で評価
筋トレやMCT補給の効果は、入院時と退院時に行った機能的自立度評価法(functional independence measure:FIM)のスコアの変化で評価した。FIMは身体機能(FIM-motor〈FIM-M〉)と認知機能(FIM-cognition〈FIM-C〉)を18項目で評価し、スコアが高いほうが自立度が高いと評価する。
解析対象者の入院時のFIMスコアは、全体の中央値が66点(FIM-M46点、FIM-C21点)、MCT群は29点(同順に15点、12点)、筋トレ群は82点(58点、25点)、MCT+筋トレ群は36点(21点、17点)だった。
MCT補給は筋トレと並行した場合にのみ相加的に働く
解析対象者の入院期間は中央値86日(四分位範囲53~128日)だった。介入効果の検討に際しては、結果に影響を及ぼし得る因子(年齢、性別、脳卒中の病型、脳卒中前のmRS、チャールソン併存疾患指数、薬剤処方数、タンパク質摂取量、および入院時の握力、MNS-SF、FIMスコアなど)を調整した。
MCT補給と筋トレの並行群で、機能的自立度(FIM)が最も改善
解析の結果、対照群と比較してMCT単独群は、退院時のFIM-Mが有意に低く(β=-4.82〈95%CI;-7.36~-2.29〉)、入院期間中のFIM-M改善幅が有意に少なかった(β=-2.94〈-5.21~-0.67〉)。その一方、筋トレ単独群は対照群より退院時FIM-Mが有意に高く(β=6.31〈3.89〜8.72〉)、入院期間中のFIM-M改善幅が有意に大きかった(β=4.82〈2.45〜7.18〉)。
そしてMCT+筋トレ群は、退院時のFIM-Mがより高く(β=8.79〈5.64~11.95〉)、入院期間中のFIM-M改善幅がより大きかった(β=6.02〈3.42~8.62〉)。なお、分散拡大係数の検討から多重共線性は認められず、筋トレは単独で機能回復を促進し、MCT補給との併用で相加的効果をもたらす可能性が示唆された。
MCT補給と筋トレの並行は、握力や骨格筋量指数(SMI)にもプラスに作用
次に、退院時の握力や骨格筋量指数(SMI)への影響が検討された。
MCT単独群は対照群との比較で、退院時の握力やSMIに有意差がなかった。その一方、筋トレ単独群は対照群に比べ握力(β=1.308〈0.255~2.361〉)、SMI(β=0.146〈0.030~0.323〉)ともに有意に高値だった。
そしてMCT+筋トレ群は、退院時の握力がより高く(β=2.441〈0.483~4.398〉)、SMIもより高値だった(β=0.194〈0.102~0.419〉)。また分散拡大係数の検討から多重共線性は認められなかった。
筋トレ時のエネルギー不足がMCI補給により代償された可能性
以上一連の結果を基に論文の結論には、「MCTサプリメントと椅子立ち上がり運動による筋力トレーニングを組み合わせることで、脳卒中後の患者の機能回復と筋力強化が促進された。リハビリテーションにおけるMCTの有用性が示唆される」と記されている。他方、後ろ向き非ランダム化試験であることから、多くの因子を調整したものの残余交絡が存在する可能性、タンパク質以外の主要栄養素の摂取量が未調整であることなどを研究の限界点として挙げ、前向き研究での検証の必要性を指摘している。
なお、MCT単独では有意な影響が認められないにもかかわらず、筋トレと並行した場合に相加的効果が認められた理由については、MCT由来のケトン体は即時に利用可能なエネルギー源であり、これが筋トレの際に生じる負のエネルギーバランスを補うように働いたためである可能性が高いとの考察が述べられている。
文献情報
原題のタイトルは、「Synergistic Effects of Medium-Chain Triglyceride Supplementation and Resistance Training on Physical Function and Muscle Health in Post-Stroke Patients」。〔Nutrients. 2025 May 7;17(9):1599〕
原文はこちら(MDPI)














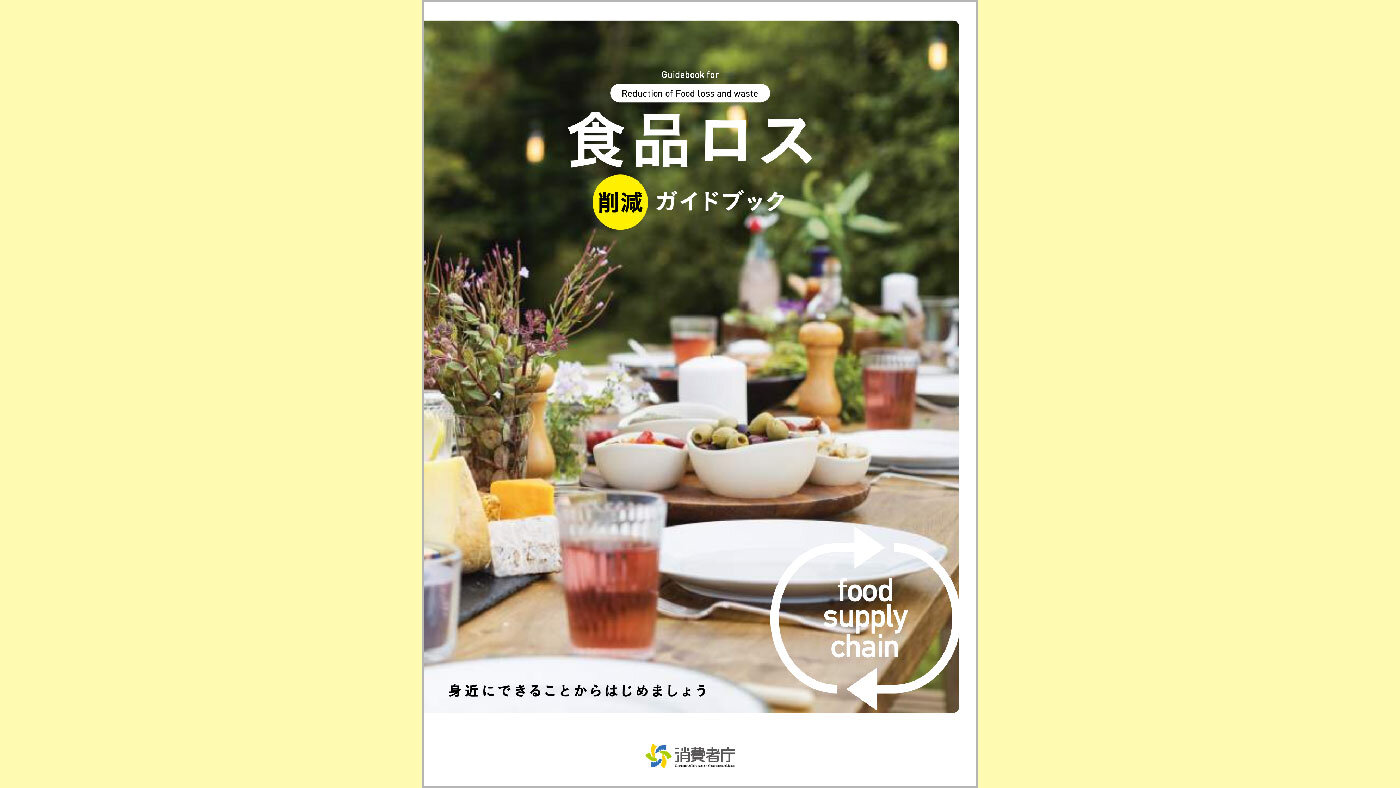








 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










