ラーメン摂取頻度が死亡リスクに影響? 70歳未満や習慣的飲酒者は関連が有意 山形コホート研究
ラーメンの摂取頻度と死亡リスクとの関連を解析した研究結果が報告された。全体として、摂取頻度が週3回以上の場合に死亡リスクが高い傾向が認められ、サブグループ解析では70歳未満、習慣的飲酒者において有意なリスク上昇が認められるという。山形県立米沢栄養大学健康栄養学部の鈴木美穂氏らが、山形県で行われている地域住民対象疫学研究「山形コホート研究」のデータを解析した結果であり、論文が「The Journal of nutrition, health and aging」に掲載された。また山形大学のサイトにプレスリリースが発表されている。

ラーメンの頻繁な摂取で死亡リスクが高まりやすい人の特徴は?
ラーメンの起源は中国だが、現在では世界的にも日本食として認識されるほど、国内で多く食されている。よく知られているように、ラーメンは高塩分であり、食べすぎによる高血圧や脳卒中、胃癌などのリスクの上昇が懸念される。過去にも、人口あたりのラーメン店舗数と脳卒中による死亡率との相関を示したデータが報告されている。
ただし、ラーメン摂取と死亡リスクとの関連に個人差があるのかどうかはわかっていない。仮に、ラーメン摂取によって顕著に死亡リスクが高くなりやすい集団があるなら、その特徴を明らかにすることで、より効果的な公衆衛生対策の立案につなげられる。これらを背景として鈴木氏らは以下の研究を行った。
ラーメン摂取頻度が高い人ほど、スープを残さずに飲んでいる
山形コホート研究の参加者のうちデータ欠落のない6,746人から、追跡開始1年以内に死亡していた人を除外し、6,725人(59.7±6.7歳、男性34.9%)を解析対象とした。
ラーメンの摂取頻度は、月1回未満が18.9%、月1~3回が46.7%、週1~2回が27.0%、週3回以上が7.4%だった。ラーメン摂取頻度が高い群ほど男性が多く、BMIが高く、若年であり、喫煙・飲酒習慣のある割合、高血圧・糖尿病を有する割合が高いという、有意な傾向性が認められた。
また、麺類摂取時にスープを飲む量が半分以上/未満で分けると、ラーメンの摂取頻度が高いほど半分以上飲む人の割合が高かった(傾向性p<0.001)。具体的には、ラーメン摂取頻度が月1回未満の群で半分以上飲む人は33.7%、摂取頻度が月1~3回では42.2%、週1~2回では51.5%、週3回以上では57.7%だった。
全体解析ではラーメン摂取頻度が高いと死亡リスクが高い傾向
中央値4.5年の追跡期間中に145人(2.16%)の死亡(癌死100人、心血管死29人を含む)が記録されていた。
粗死亡率が最も低い、ラーメン摂取頻度が週に1~2回の群を基準として他の群の死亡リスクを比較すると、交絡因子未調整の粗モデルでは、摂取頻度が最も高い群(週3回以上)では非有意ながら死亡リスクが7割近く高い傾向が認められた(ハザード比〈HR〉1.69〈95%CI;0.94~3.03〉)。死亡リスクに影響を及ぼし得る因子(年齢、性別、喫煙・飲酒習慣、麺類摂取時に飲むスープの量、高血圧・糖尿病・脂質異常症の既往)を調整したモデルでも非有意ながら、摂取頻度が週3回以上の群では死亡リスクが約5割高い傾向が認められた(HR1.52〈0.84~2.75〉)。
サブグループ解析では70歳未満、習慣的飲酒者は有意にハイリスクという結果
次に、年齢(70歳未満/以上)、性別、飲酒習慣の有無、麺類摂取時に飲むスープの量(半分以上/未満)で層別化したサブグループ解析を実行。すると、以下のように、有意なリスク差が存在する集団が特定された。
年齢
年齢が70歳未満の場合、ラーメン摂取頻度が週3回以上の群は、前記の交絡因子を調整後、死亡リスクが2倍以上高いことが示された(HR2.20〈1.03~4.73〉)。ただし、ラーメン摂取頻度が最も低い群(月1回未満)においても、有意なリスク上昇が認められた(HR2.17〈1.08~4.34〉)。
70歳以上の場合は、ラーメン摂取頻度と死亡リスクとの間に有意な関連はみられなかった。
性別
男性では、ラーメン摂取頻度が月1回未満の群で、有意な死亡リスク上昇が認められた(HR2.07〈1.09~3.97〉)。女性については死亡リスクとの有意な関連はみられなかった。
麺類摂取時に飲むスープの量
麺類摂取時にスープを半分以上飲む人では、ラーメン摂取頻度が月1回未満の群で、有意な死亡リスク上昇が認められた(HR2.43〈1.09~4.92〉)。スープを半分以上残す人では、死亡リスクとの有意な関連はみられなかった。
飲酒習慣
習慣的飲酒者では、ラーメン摂取頻度が週3回以上の場合に死亡リスクが3倍近く高いことが示された(HR2.71〈1.33~5.56〉)。飲酒習慣のない人では死亡リスクとの有意な関連はみられなかった。
ラーメン摂取に関する食事指導では、個人の特性を考慮する必要がある
著者らは本研究から得られた知見を以下のようにまとめている。
まず、ラーメンの摂取頻度が高い人の特徴が明らかにされ、摂取頻度の高さがBMIや喫煙・飲酒習慣、スープをあまり残さないことなどと関連していた。次に、ラーメンの摂取頻度が高い場合に死亡リスクが高い傾向があり、とくに70歳未満や習慣的飲酒者では有意な関連が認められた。
一方で、ラーメン摂取頻度が最も低い群においても、死亡リスクが高い集団が特定された。この点について著者らは「機序は不明」としながら、心血管リスク因子を有している人がラーメンの摂取を控えていることによる因果の逆転、または食事全体の摂取量が少ないことに伴うフレイルが死亡リスクに影響を及ぼしていた可能性を考察として述べている。
論文では、研究の限界点として、観察研究であり因果関係の考察が制限されること、ラーメン摂取頻度以外の食習慣や運動習慣、社会経済的地位など、死亡リスクに影響を及ぼし得る因子を調整していないこと、摂取されたラーメンの種類や一杯あたりの量を把握していないことなどを挙げた上で、結論を「ラーメン摂取頻度は、男性、70歳未満、習慣的飲酒者、麺類摂取時にスープを半分以上飲む人において、死亡リスクと関連していた。これらの結果は、個人の特性に基づいて、ラーメン摂取に関する食事指導を行う必要があることを示唆している」と総括している。
なお、山形大学のサイト内に掲載されたプレスリリースには、一般向けの解説として「研究のポイントおよびQ&A」がまとめられており、「ラーメンはどのくらいなら安心して食べられますか?」、「健康的に楽しむにはどうすればいいですか?」などの設問とその回答が示されている。
文献情報
原題のタイトルは、「Frequent Ramen consumption and increased mortality risk in specific subgroups: A Yamagata cohort study」。〔J Nutr Health Aging. 2025 Aug 1;29(10):100643〕
原文はこちら(Elsevier)
プレスリリース
ラーメンの過剰摂取が一部の人々の死亡リスクを高める可能性——山形コホート研究より(山形大学)










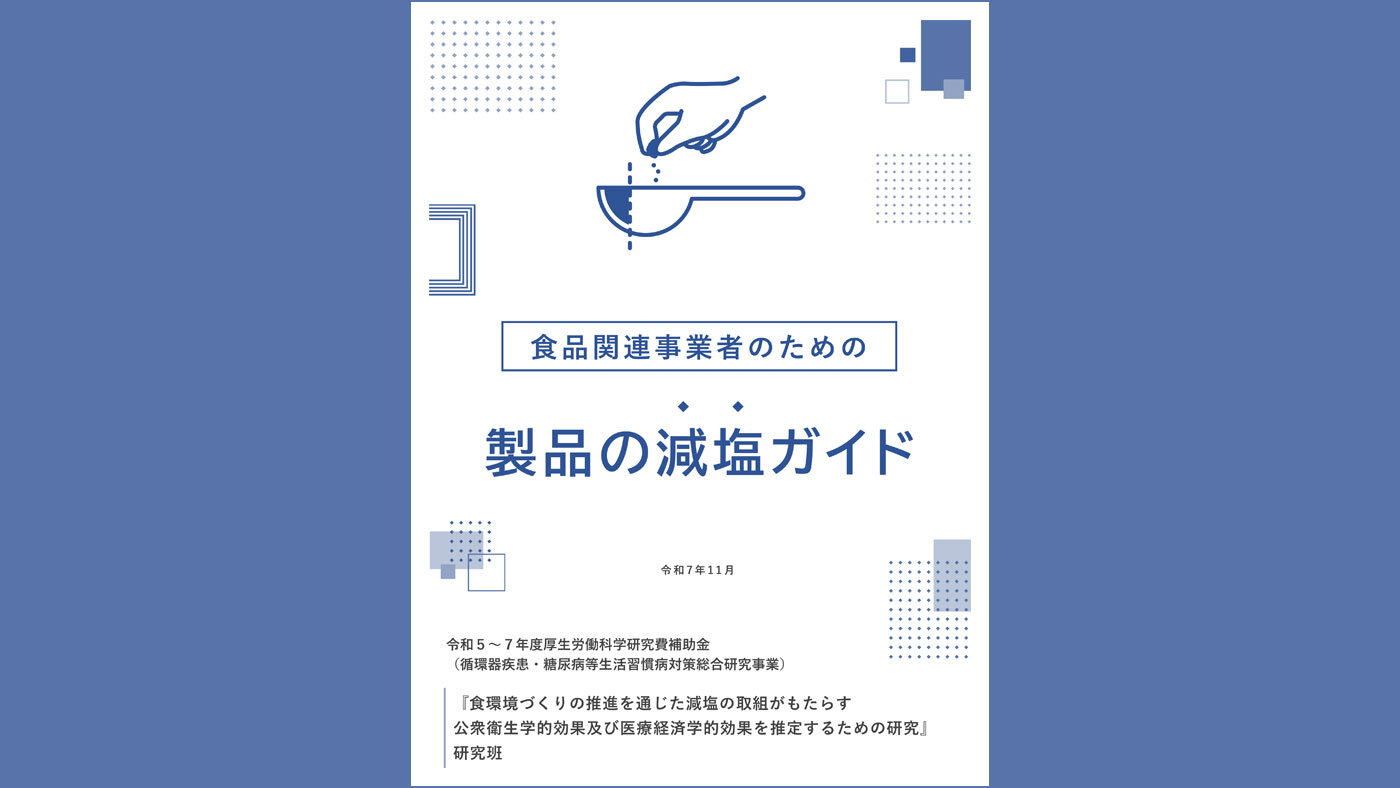












 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










