就寝前のメラトニン摂取で、翌日の高強度運動のパフォーマンスし向上し運動後の回復も早まる可能性
就寝前にメラトニンを摂取すると、翌日の高強度運動のパフォーマンスが向上し、運動後の回復も促進するとする研究結果が報告された。

メラトニンの睡眠改善と酸化ストレス軽減作用は、アスリートに有効か
メラトニンは松果体で合成され、哺乳類の生体リズムを調整しているホルモン。周囲が暗くなると分泌が増えて睡眠を誘い、光、とくに青色光への曝露によって分泌が阻害され覚醒レベルが高まる。また、活性酸素種や活性窒素種によるダメージからミトコンドリアを保護する作用もあり、高強度運動後の筋損傷や炎症を抑制する可能性も示唆されている。
これらのメラトニンの作用のうち、現時点では主に前者についてよく認識されており、スポーツ領域でもメラトニン摂取により睡眠を改善し、それによってパフォーマンス向上を期待するという考え方がある。ただしその効果を実際に示したエビデンスは十分でない。
以上を背景としてこの論文の著者らは、日常的にトレーニングを行っている男性を対象とするプラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験により、メラトニンの効果を検証した。
研究参加者はふだんトレーニングを行っている12人の男性
事前の統計学的検討から、このトピックに関する有意性の検証に必要なサンプルサイズは8人と計算され、20人の研究参加候補者を募集した。参加の適格基準を、週に3時間以上のトレーニングを行っていること、医学的な制限のないこと、非喫煙者であること、サプリメントや抗炎症薬を使用していないこと、過去2カ月以内に睡眠障害を経験していないこと、過去1カ月以内に時差のある旅行を経験していないこととし、これらを満たす12人の男性が研究に参加した。主な特徴は、年齢21.92±2.84歳、BMI22.57±2.57、トレーニング量4±2時間/週、トレーニング歴5.33±6.67年。クロノタイプは中間型が7人、中等度の朝型が5人だった。
無作為に2群に分け、1群はメラトニン摂取条件を先に、他の1群はプラセボ摂取条件を先に試行。1週間のウォッシュアウト期間をおいて割り付けを変えて試行した。各条件のテストは2日間にわたって実施され、72時間前からはアルコール、カフェインの摂取を禁止し、24時間前からは激しい運動を禁止した。
5mシャトルランテストや自覚的運動強度、主観的な回復の程度への影響を検討
テストの1日目は運動をせずに通常の生活とし、就床の30分前(21時30分)にメラトニン6mg、またはプラセボを摂取。これらは同じ外観のカプセルとして支給され、100mLの水とともに摂取された。その後、手首装着型の睡眠モニター(アクチグラフ)をつけて入眠。テスト2日目には7時に起床し、7時30分に標準化された朝食を摂取し、消化のために2時間経過したのち、以下のように5mシャトルランテスト(5 m shuttle run test;5mSRT)を行い、パフォーマンスへの影響を検討した。なお、研究期間中は食事と水分の摂取に関して、一般的なガイドラインに従うことを求めた。
評価項目は、アクチグラフによる睡眠関連パラメーター、5mSRTのほか、採血による筋損傷や炎症マーカーの測定、ボルグスケールによる自覚的運動強度(rate of perceived exertion;RPE)、5mSRTでの心拍数、および、5mSRT直前から最大72時間後までの主観的な回復の程度(perceived recovery status;PRS)、遅発性筋肉痛(delayed onset muscle soreness;DOMS)の程度などだった。なお、5mSRTは30秒を6回として、RPEは0~10の範囲でスコア化し10が最強の強度、PRSも0~10の範囲で10が最も回復している状態、DOMSは下肢の筋肉痛を評価対象として1~10でスコア化し10が最も強い疼痛と評価した。
睡眠には有意な影響がない一方で、5mSRTはメラトニン条件が向上し回復も促進
結果について、まず睡眠関連パラメーターへの影響をみると、睡眠時刻、起床時刻、睡眠時間、入眠潜時(就床から入眠までに要した時間)、睡眠効率(床上時間に占める睡眠時間の割合)など、すべてに有意差が認められなかった。
次に、5mシャトルランテスト(5mSRT)の結果をみると、最大走行距離と自覚的運動強度(RPE)には有意差がなかったが、メラトニン条件では総走行距離(747.5±109.0 vs 625.0±81.0)が有意に長く、疲労指数(4.29±3.04 vs 15.75±9.10%)、減少率(最大走行距離を6回とも記録したと仮定した値と実際の走行距離との乖離率/4.09±3.18 vs 14.12±4.84%)、最大心拍数(182±3 vs 188±7bpm)が有意に低値だった。
続いて主観的な回復の程度(PRS)に着目すると、5mSRTの試行前、試行5分後、24、48、72時間後のすべての時点において、メラトニン条件はプラセボ条件より高値(回復していることを意味する)で推移していた。また、遅発性筋肉痛(DOMS)の程度に関しては、5mSRT試行24、48、72時間後の時点で有意差が認められ、メラトニン条件はプラセボ条件より低値(疼痛が弱いことを意味する)で推移していた。
このほかに評価した、血液検査値での筋損傷のマーカーであるクレアチンキナーゼ(creatine kinase;CK)、乳酸脱水素酵素(lactate dehydrogenase;LDH)や、炎症マーカーのC反応性蛋白(C-reactive protein;CRP)などには、条件間の有意差がみられなかった。
まとめると、就寝前に6mgのメラトニンを摂取することによる睡眠パラメーターの改善は観察されなかったが、翌日の高強度反復運動中の複数の身体能力パラメーターにプラスの影響を与えることが示された。著者は、「これらの結果は、アスリートや身体的に活発な人が、とくに激しい夜間のトレーニングや競技の後など、翌日のパフォーマンスと回復が重要な状況において、就寝前のメラトニン摂取がシンプルかつ合法的なオプションとなり得ることを示している」と総括。またこのトピックに関する今後について、「運動パフォーマンスへの効果を最大化するために、夜間のメラトニン摂取の至適用量と至適タイミングを決定するさらなる研究が必要であり、また、メラトニンによる主観的な回復の促進が数日間続くことの根底にあるメカニズムの解明が求められる」と付け加えている。
文献情報
原題のタイトルは、「Melatonin Supplementation Enhances Next-Day High-Intensity Exercise Performance and Recovery in Trained Males: A Placebo-Controlled Crossover Study」。〔Sports (Basel). 2025 Jun 19;13(6):190〕
原文はこちら(MDPI)










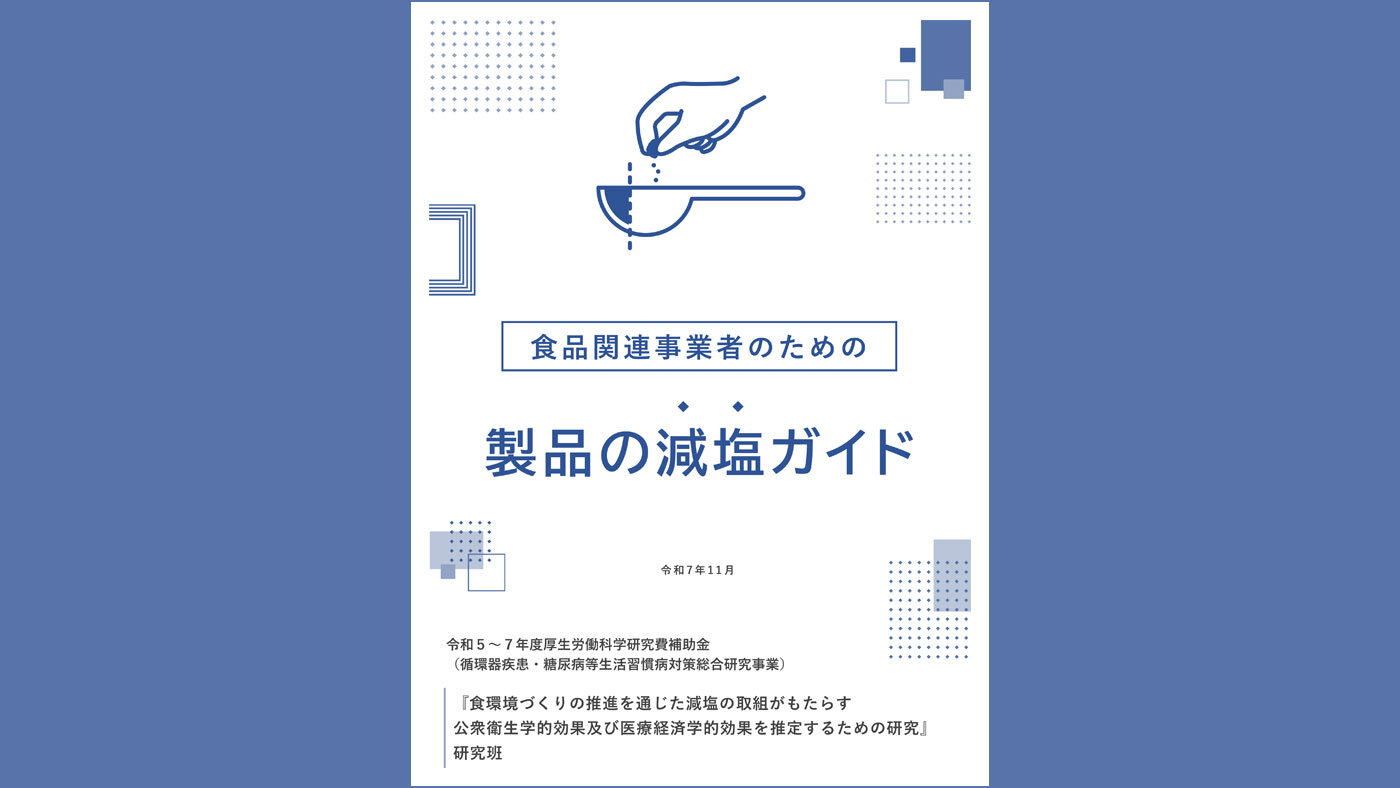












 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










