主観的な情報である「口渇感」は、脱水時の水分補給の指標になり得るのか
脱水症状の簡便な指標として口渇感(喉の渇きの感覚)が利用されているが、口渇感は主観的であり指標としてはかなりアバウトなものだ。しかし、実際には口渇感が脱水を把握するうえで信頼性に足る指標である可能性が報告された。被験者に偽りの情報を伝えても、飲水量は影響されなかったという。

口渇感は偽りの水分喪失情報に左右されるのか?
長時間の運動中、とくに暑熱環境では水分補給がパフォーマンス維持、健康障害防止のために重要だ。運動中の水分補給の必要性を評価する目安として、口渇感を指標とすることが多い。ただし、口渇感が水分補給の指標として十分であるかどうかという点には、いまだ議論の余地がある。
これまでの研究で、水分摂取を禁止した状況においては、口渇感が脱水レベルと強く相関することが示されている。ただし、口渇感のような自覚的な認識は、外部からの情報の働きかけによって変動する可能性がある。例えば、他者からの期待や観察に気付いたときに、他者の意図に沿うような行動の変化が起きるという、ホーソン効果と呼ばれる現象の存在も知られている。
つまり、口渇感やそれを補正するための飲水行動が、与えられた情報によって変化する可能性を否定できない。そこで本論文の著者らは、暑熱環境での運動中に発生する脱水の認識、口渇感が、水分喪失に関する外部から与えられた情報によって変化するか否かを検討した。
真の情報と偽りの情報を伝える2条件の無作為化二重盲検クロスオーバー試験
この研究は、無作為化二重盲検クロスオーバー法で実施された。被験者は11名の健康で活動的な男性(23.0±3.0歳、身長1.75±0.07m、体重76.7±4.9kg)。60分間の運動を課し、体重の変化(水分喪失レベル)を被験者に伝え、運動終了後に自由に水分補給してもらった。被験者への体重変化情報の伝達については、1条件では真実の減少幅を伝え、別の1条件では、実際の減少幅の6割の値を伝えた。この2条件の試行順序は無作為化した。
なお、体重計測に際しては、体重計と被験者の間にカーテンを置き、被験者からは計測値が見えないようにした。また、体重を計測する研究者と被験者は、研究終了まで研究目的を知らされていなかった。研究者が測定した体重の記録は、別の研究者にメモとして渡され、試験条件に従って、真実の値、または偽りの値が被験者に伝えられた。
被験者は前夜から絶食とし、研究室に到着後に標準化された朝食(750kcal、脂質24.6%、タンパク質20.7%、炭水化物54.7%、水分250mL、ナトリウム1,500mg)を摂取。30分間の休息を挟んで、ベースライン体重測定の後に運動を負荷した。運動負荷は、脱水レベルが体重の4%となることを目標として、自転車エルゴメーターとトレッドミルを各30分間、最大心拍数の70~80%の強度とした。運動負荷セッション中は、水分摂取を禁止した。
試行環境は、真の値を伝える条件では、湿球黒球温度(WBGT。暑さ指数)28.8±0.1℃、環境温度32.5±0.7℃、相対湿度73±3%、偽りの値を伝える条件ではWBGT28.9±0.3℃、環境温度32.2±1.1℃、相対湿度70±3%であり、いずれも同等だった。
口渇感は、15分ごとにビジュアルアナログスケールで把握した。そのほかに、温度感覚と膨満感をリッカートスコアで評価。また、尿比重や尿浸透圧の変化も把握した。
運動負荷終了後の30分間、被験者は必要だと思う分の水分を自由に摂取した。
両方の条件で水分摂取量を含む全評価項目に有意差なし
運動負荷前の体重、尿比重、尿浸透圧、口渇感、温度感覚、膨満感は、すべて両条件同等だった。
運動負荷時間は、真情報条件が110.0±24.8分、偽情報条件が115.0±22.3分(p=0.232)で有意差はなく、体重減少幅は同順に2.98±0.37kg、2.93±0.33kgであり、3.88±0.43%、および3.81±0.38%の脱水と評価され(p=0.756)、やはり有意差はなかった。
運動負荷セッション終了後の飲水量は、真情報条件が1,220±249mL、偽情報条件が1,228±422mLであり同等だった(p=0.949)。水分補給後の脱水レベルは、同順に2.50±0.48%、2.48±0.68%だった。
なお、両方の条件で脱水レベルと口渇感との間に、有意な強固の相関が認められた(真情報条件r=0.992、偽情報条件r=0.979.いずれもp<0.05)。その他の評価項目である尿比重、尿浸透圧、温度感覚、膨満感は、運動負荷開始からセッション終了後の水分摂取後にかけて、すべて有意差がなかった。
結論として著者らは、「喉の渇きの知覚(口渇感)は、自由に水分摂取ができない状況での運動中の水分喪失量に関する誤った情報を受け取っても、脱水の補正のための水分摂取量は影響を受けなかった。これは、運動中の水分喪失の認識が、脱水によって誘発される視床下部の口渇にかかわる情報伝達をキャンセルできないことを示唆している可能性がある」と結論づけている。
文献情報
原題のタイトルは、「Awareness of Fluid Losses Does Not Impact Thirst during Exercise in the Heat: A Double-Blind, Cross-Over Study」。〔Nutrients. 2021 Dec 3;13(12):4357〕
原文はこちら(MDPI)
シリーズ「熱中症を防ぐ」
熱中症・水分補給に関する記事
- 気候変動により猛暑日が激増し当たり前の時代に? 文科省・気象庁「日本の気候変動2025」を公表
- 【見逃し配信スタート】夏本番前に必見! アイススラリーの最新活用法を学ぶWebセミナーを公開
- 小中高生の熱中症救急搬送の8割がスポーツ活動中に発生 「8月」「午後〜夕方」「屋外」などは要注意
- 【参加者募集】大塚製薬×SNDJ無料Webセミナー『暑熱環境に負けない! バテない! 熱中症対策2025 アイススラリーによる身体冷却/プレクーリングの基礎と実践』
- 女性持久系アスリートはナトリウム摂取で暑熱下のパフォーマンスが向上 とくに黄体期で顕著な影響
- 子どもの汗腺機能は8歳から男女差が顕在化、夏の発汗量は春の1.5倍 熱中症予防への応用に期待
- 夏の「高温化」により運動部活動が困難に? 国内842都市・時間別の予測データが示す気候変動の深刻な影響
- 「熱中症特別警戒アラート」「熱中症警戒アラート」全国運用スタート 重大な健康被害に警戒を 環境省・気象庁
- 熱中症と居住地域の格差に関連? 社会経済的指標が低いほど緊急入院リスクが高い
- 学校内のAED搬送に影響する因子を検討 患者が女子生徒、スポーツ以外の課外活動の場合などに課題
















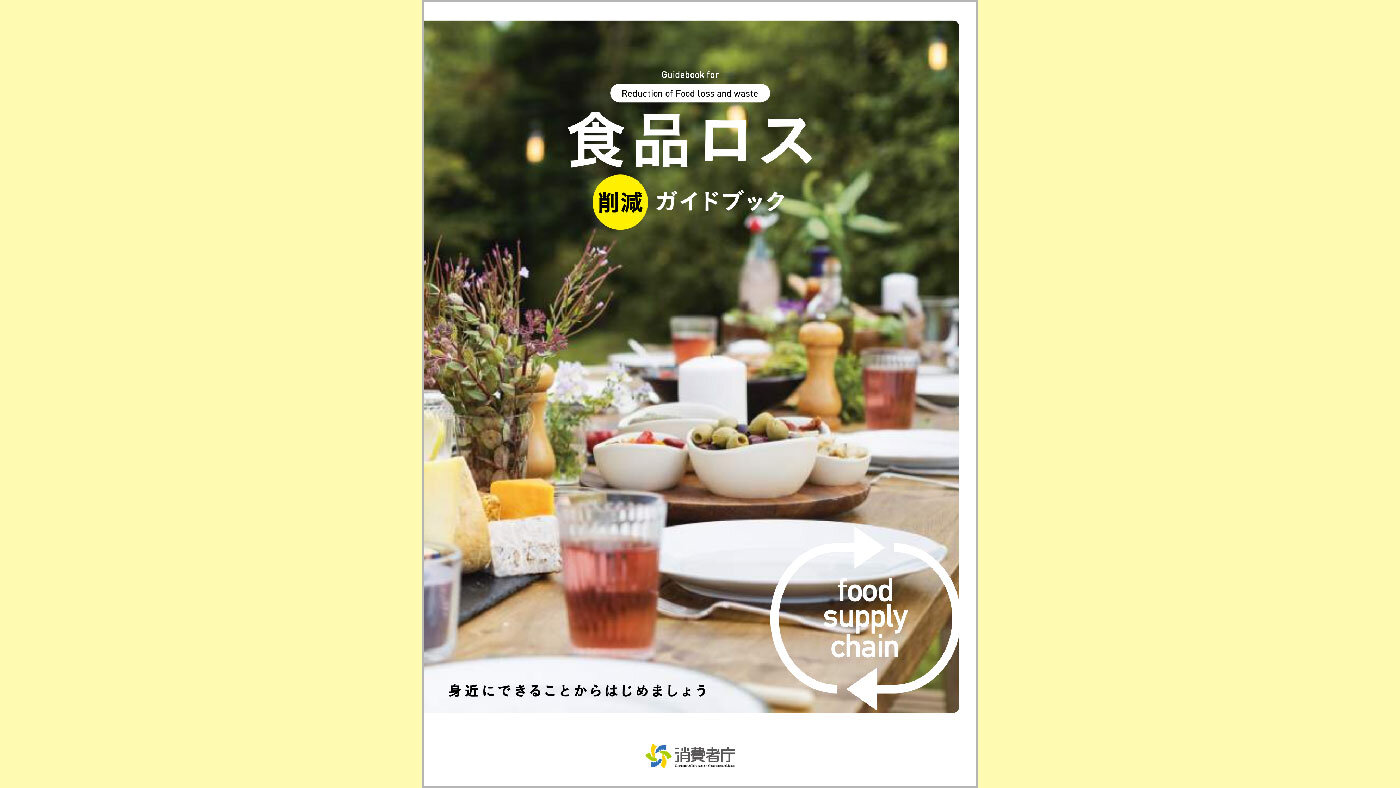







 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










