スポーツにおける緊張とミスの関連を調査 皮肉エラーと過補償エラーの発生率をテニスで検討
競技中のプレッシャーを感じる場面で「〇〇してはいけない!」と考えることが、アスリートのパフォーマンスにどのような影響を及ぼすのかを、テニスのリターンの精度で検討した研究結果が報告された。鹿屋体育大学体育学部の中本浩揮氏らの研究であり、「Journal of sport & exercise psychology」に論文が掲載された。

プレッシャーの影響を、アスリートの回避思考と苦手意識をからめて検討
アスリートがパフォーマンスを最大化して発揮するうえで、競技中の強いプレッシャーをどのように処理するかも大きな課題の一つ。高度なトレーニングを行い実績のあるアスリートでも、ときにプレッシャーによって初心者のようなミスを犯すことがある。このようなミスが発生するメカニズムについては、多くの研究がされてきている。
これまでに提唱された仮説として例えば、ハイレベルアスリートであればプレー中に要求される一連の動作は、通常は意識せずとも自然に行えるのに、プレッシャーがかかるとトレーニング初期のようにその動作を丁寧に再現しようと意識しすぎるあまり、あたかも初心者のような状態に退行してしまうという説がある。また球技などでは、打ってはいけないエリアを意識しすぎて、逆にそのエリアにボールが行ってしまう「皮肉エラー(ironic error)」が生じたり、過剰に避けようとして本来の目標外(ゴールの枠外やコート外)にボールが行ってしまう「過補償エラー(overcompensation errors)」が生じたりすることが知られている。
さらに、これらのエラーの発生に、アスリート個人の苦手意識(例えばテニスにおいて、バックハンドやフォアハンドの得意/不得意)が関与している可能性も指摘されている。これらを背景として中本氏らは、特定の位置への打球が禁止された状況でのテニスのリターンショットの精度がプレッシャーの強弱や苦手意識によって、どのように変化するかという検討を行った。
熟達したテニス選手12人を対象にプレッシャーの影響を検討
研究参加者は、大学のテニスチームに所属している学生12人(男子7人、女子5人)。年齢は19.5±1.5歳で競技歴は10.5±3.5年であり、全国大会出場者も含まれていて、全員がハイレベルで競技を行っているアスリート。
相手コートの中央に自動球出し機を置き、射出されるボールを定められた目標位置に正確に打ち返すという課題が実行された。目標ゾーン(target zone)は相手コートのベースラインとシングルスラインに隣接した範囲(面積は相手コートの16分の1)とし、その手前(または後方)のエリア(面積は同じく16分の1)を「皮肉ゾーン(ironic zone)」として、そこへのボールの返球を禁止した。一方、目標エリアの後方(または手前)のエリア(やはり16分の1)は「過補償ゾーン」(overcompensation zone)として、そこへの返球は禁止ではなかったが、リターンショットとしては過補償エラーとして判定した。
なお、目標ゾーンと皮肉ゾーンの前後関係が結果に影響を及ぼすことを避けるため、研究参加者の半数は皮肉ゾーンを手前に、残りの半数は皮肉ゾーンを後ろに設定した。また、この研究ではショットの正確さの検証を最も重視し、球の威力(スピード)は求めなかった。
この課題における苦手意識、およびプレッシャーの強弱の影響を同時に評価するため、以下のような手法がとられた。
苦手意識(得意/不得意)を評価し、それに基づき4群に分けて競争
まず、12人の参加者に対してビジュアルアナログスケールを用い、バックハンドとフォアハンドのどちらが得意かを評価。その回答を基に、バックハンドが極めて得意な群、バックハンドがやや得意な群、フォアハンドが極めて得意な群、フォアハンドがやや得意な群という4グループに3人ずつ分類。それぞれ得意な条件と不得意な条件での試行を行った。
またこの研究では、個人レベルではなく、この四つのチームレベルで成績を競い合うこととして、各アスリートに責任感のプレッシャーを負荷した。
プレッシャーの強弱の設定方法
弱いプレッシャーを負荷する条件では、単にできるだけ多く目標ゾーンへの返球を成功させることを課し、3人の合計スコアをそのグループの成績として評価した。
一方、強いプレッシャーを負荷する条件ではスコア争いではなく、賞金の獲得を目指してもらった。具体的には、目標ゾーンへの返球が成功した場合はそのチームに1球ごとに100円を支給。皮肉ゾーンへ返球された場合は、それまでに貯まっていた金額をリセットした。過補償ゾーンを含むその他のエリアへの返球は、賞金の加算や減算もなかった。なお、賞金額がトップのチームにのみ賞金を支給することを、参加者へ事前に伝えた。
プレッシャーと苦手意識の強弱でエラーの発生パターンが異なる
参加者は、上記の4条件(苦手意識〈得意/不得意〉、プレッシャーの強弱が異なる条件)をそれぞれ30回、計120ショットを試行した。各条件での返球成功率、皮肉エラーや過補償エラーの発生率は、以下のようになった。
苦手意識が薄くプレッシャーが弱い条件では、成功(目標ゾーンへの返球)率49.7±12.1%、皮肉エラー発生率17.5±7.2%、過補償エラー発生率13.3±8.2%。苦手意識が薄くプレッシャーが強い条件では、成功率49.2±15.6%、皮肉エラー発生率8.6±7.5%、過補償エラー発生率28.9±14.6%。苦手意識が強くプレッシャーが弱い条件では、成功率44.7±10.3%、皮肉エラー発生率13.3±5.9%、過補償エラー発生率14.4±4.6%。苦手意識が強くプレッシャーが強い条件では、成功率45.3±14.4%、皮肉エラー発生率9.2±6.7%、過補償エラー発生率27.5±8.4%。
プレッシャーや苦手意識の強弱と各ゾーンへの返球率との関連
統計解析の結果、チームごとの成功した返球数は条件間に有意差がなかったが、皮肉ゾーンや過補償ゾーンへの返球数には条件間の有意差が認められた。そこで、プレッシャーの強さや苦手意識の強さと、各ゾーンへの返球数との関連を検討した。
すると、参加者は標的ゾーンを狙っているにも関わらず、プレッシャーが強くなると、過補償ゾーンへの返球確率が有意に増加し、苦手意識が薄い場合には75%増加(リスク比〈risk ratio;RR〉1.75〈95%CI;1.31~2.35〉)、苦手意識が強い場合は55%増加(RR1.55〈1.17~2.05〉)していた。
反対に、皮肉ゾーンへの返球は、プレッシャーが強くなることで有意に減少する傾向を示し、苦手意識が薄い場合には40%(RR0.60〈0.41~0.88〉)、苦手意識が強い場合には30%減少していた(RR0.70〈0.46~1.05〉)。
一方、苦手意識の強さは、その他ゾーンへの返球確率を増加させる傾向が認められた(低プレッシャー35%増(RR1.35〈1.05~1.74〉)、高プレッシャー34%増(RR1.34〈0.97~1.85〉))。
プレッシャーや苦手意識はさまざまなミスのリスク要因だが、成功率には影響しない?
以上の結果をまとめると、プレッシャーや苦手意識の強弱によって、エラーの発生パターンが変化すると考えられる。具体的には、プレッシャーは禁止されたプレーを過剰に回避する結果(過補償エラー)を増加させ、苦手意識はランダムなミスを増加させる。ただし、成功率はどの条件でも変わらない可能性が示唆された。
なお、先行研究からは、プレッシャーによって皮肉エラーが増えるという結果が報告されているが、本研究ではむしろ、皮肉エラーは減り過補償エラーが増加していた。著者らはこの点を「新たな発見」としたうえで、先行研究と相反する結果となった理由として、失敗した場合のリスクの大きさの違いと、ショットの速度を求めなかったことが関係している可能性を挙げている。
前者については、先行研究は成功した場合に1点加点し、皮肉エラーの場合には1点減点するという設定であったのに対して、本研究では皮肉エラーが発生すると獲得した賞金をすべて失うという、よりハイリスクの設定だった。そのため、皮肉エラーを過剰に避けた可能性がある。後者については、力強くショットする場合、開始した動作を途中で調整することは困難であり、精度はショットの開始時点でほぼ決定しているが、ショット速度を要求しない場合には動作の途中で調整が可能であり、その調整の際に過剰な補正が発生しやすいのではないかとのことだ。
いずれにしても、試合中の緊張場面で「〇〇だけはしてはいけない」といった、一見プレーに好影響を与えそうな指導者の言葉かけや選手の意識は、実際には特定のエラーを増大させるという現象は興味深い。
文献情報
原題のタイトルは、「Inhibition of Ironic Errors and Facilitation of Overcompensation Errors Under Pressure: An Investigation Including Perceived Weakness」。〔J Sport Exerc Psychol. 2024 Apr 30;46(3):151-163〕
原文はこちら(Human Kinetics)










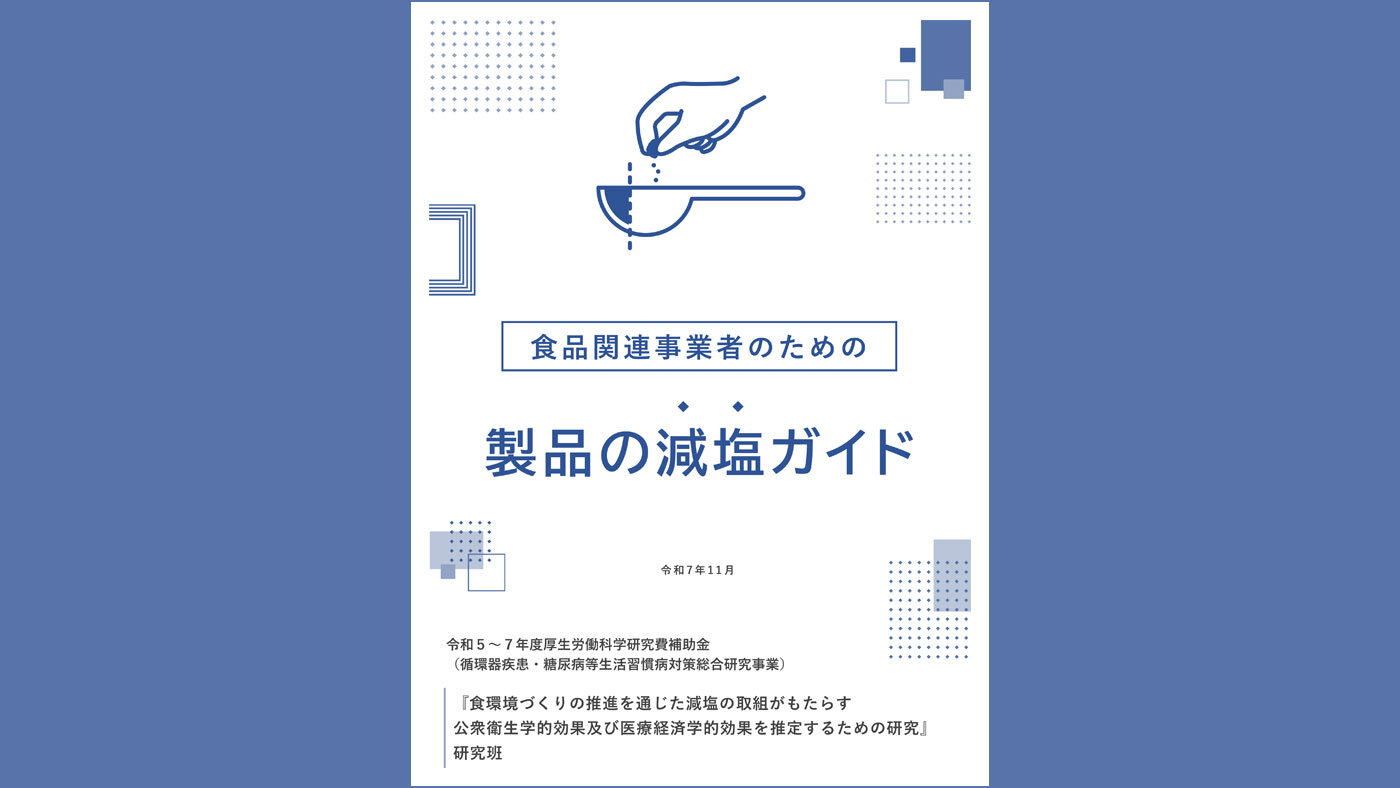












 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










