アスリートへのドーピング防止教育は短期的には効果はあるが、長期介入や受動的参加の場合は逆効果の可能性
ドーピング防止プログラムの有効性に関する報告を対象としたシステマティックレビューとメタ分析の結果が報告された。防止プログラムは、短期的には有効性が認められるが、長期的な有効性のエビデンスは乏しく、また、参加者が能動的でない場合には負の影響が生じる可能性を示唆する結果も示されている。

これまでのドーピング防止介入の効果をシステマティックレビューで検討
スポーツにおけるドーピングは依然として世界的な課題として残されており、アスリートのドーピング抑止のため、さまざまな防止プログラムが提案・実施されてきている。2019年には世界アンチ・ドーピング機構(World Anti-Doping Agency;WADA)がドーピング防止活動における国際的教育基準(International Standard for Education;ISE)を提案。最近では、より実効性の高いプログラムの因子として、アスリートの社会的規範や道徳的関心を高めるアプローチがより重要とされるようになってきた。
今回紹介する論文の研究は、このWADAのISE提案以降に報告された、ドーピング防止プログラムの効果に関する研究をシステマティックレビューとメタ分析により総括して、有効性の高い手法を探ることを目的に実施された。
文献検索の手法
システマティックレビューとメタ解析のガイドライン(PRISMA)に基づき、PubMed、ScienceDirect、SciELO、Redalycという四つの文献データベースを用いた文献検索を実施。包括基準は、2019年以降に報告され2024年10月4日までに収載された論文で、アスリートを対象にドーピング防止介入を行い、その効果を一つ以上の指標で定量的に評価している研究であり、対象者の競技、レベル、性別、年齢、国籍は限定しなかった。除外基準は、対象が非アスリート(コーチなど)の研究、2019年以前に発表された研究、全文の取得が不能な論文など。
一次検索で180報がヒットし重複削除後の179報を2名の研究者が論文タイトルに基づき独立してスクリーニング。採否の意見の不一致は3人目の研究者が解決し、11報の要約をレビューし9報を抽出。それらの論文の参考文献のハンドサーチにより1報を追加し、最終的に10件の研究論文を特定した。
受動的なアスリートや介入期間が長い場合には、プログラムに工夫が必要
特定された10件の研究の参加者は合計3,670人(女性1,094人、男性2,487人〈一部の論文は性別について触れられていないため合計数と一致しない〉)。介入には、講義、オンラインプラットフォームへのアクセス、ビデオゲームなどの手法が用いられていた。
ドーピング意図に関しては有意な効果、道徳的要因への効果は非有意
介入効果は、ドーピングの意図、アンチ・ドーピング行動、アンチ・ドーピングの道徳的要因という3点について評価され、介入前と介入後の変化、および、介入前と追跡調査での変化という、合計6通りの効果量(ES)が計算された。
ドーピング意図に関する介入の効果は、介入前と介入後の比較で有効性が認められ(ES=0.32〈95%CI;0.25~0.39〉、I2=45.79%)、かつ、介入前と追跡調査の比較でも有効性が認められた(ES=0.34〈0.26~0.42〉、I2=31.63%)。アンチ・ドーピング行動に関する介入の効果は、介入前と介入後の比較で有効性が認められたが(ES=-0.29〈-0.51~-0.08〉、I2=94.37%)、介入前と追跡調査の比較では有意でなかった(ES=-0.13〈-0.29~0.03〉、I2=73.29%)。アンチ・ドーピングの道徳的要因に関する介入の効果は、介入前と介入後の比較(ES=0.01〈-0.10~0.12〉、I2=77.26%)、および、介入前と追跡調査の比較(ES=-0.01〈-0.14~0.14〉、I2=0.00%)の双方ともに、有意でなかった。
この結果を基に著者らは、ドーピングリスクにつながるような、より深い価値観を変えるには、これまでのプログラムで使われていない「メンターシップなどの代替アプローチが必要であることが示唆される」と述べている。
アスリートの介入プログラムへの参加が受動的な場合は逆効果の可能性も
続いて、プログラム参加者の特徴や介入期間などにより効果が異なるのかが検討された。
その結果、ドーピング意図に関しては、アスリートのプログラムへの参加が受動的であった場合には、上述の全体解析の結果とは反対に、介入前と介入後の比較(ES=-0.83〈-1.128~-0.534〉)、および、介入前と追跡調査の比較(ES=-0.86〈-1.228~-0.487〉)の双方で、負の影響が観察された。また、介入期間が長い(プログラムのセッション数が多い)ことも、介入前と介入後の比較(ES=-0.55〈-0.773~-0.320〉)、および、介入前と追跡調査の比較(ES=-0.48〈-0.762~-0.204〉)の双方で、負の影響が観察された。
一方、参加アスリートの年齢が高いことは、介入前と介入後の比較(ES=0.12〈0.061~0.183〉)、および、介入前と追跡調査の比較(ES=0.13〈0.058~0.210〉)の双方で、ドーピング意図に関する介入効果の高さと関連していた。
これらに基づき著者らは、「アンチ・ドーピング教育プログラムは、短期的な態度や意図に関してはプラスの影響を与えるが、行動変容を持続させるには継続的な強化と積極的な関与が必要である。また、介入期間が長期になることにより効果が低下するという結果は、アスリートに永続的なアンチ・ドーピング行動を植え付けるうえで、単独の介入のみでは不十分であることを示唆している」と総括している。
文献情報
原題のタイトルは、「Effective Intervention Features of a Doping Prevention Program for Athletes: A Systematic Review with Meta-Analysis」。〔Sports (Basel). 2025 Apr 7;13(4):108〕
原文はこちら(MDPI)









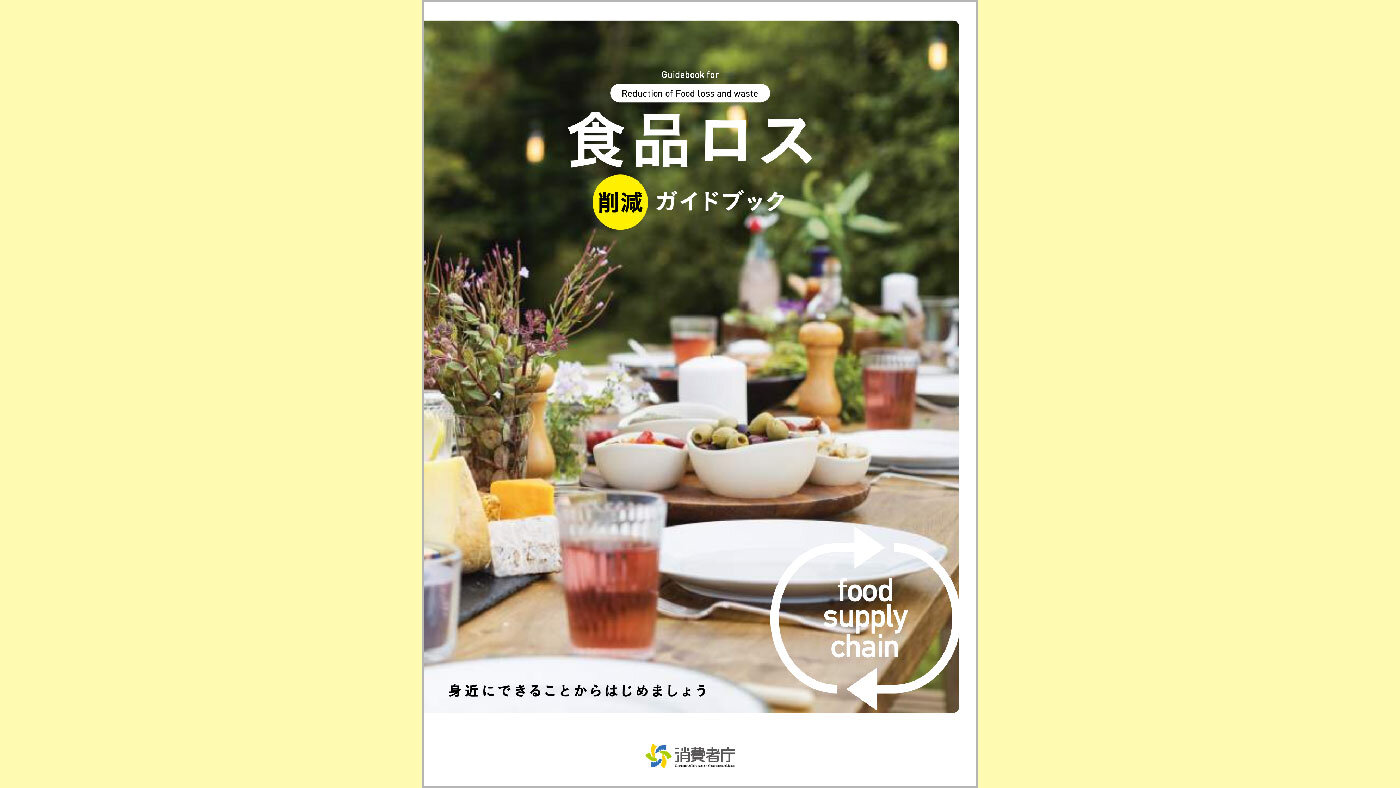













 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!








