【あじこらぼ】減塩の次なる一手は「食環境整備」 武見ゆかり先生が語る実践と連携の重要性
去る2024年10月に開催された第83回 日本公衆衛生学会総会にて、女子栄養大学 副学長・教授の武見ゆかり先生が、「産業保健と地域保健の連携による職域の減塩の推進」をテーマに講演されました。講演では、現場で活動する栄養士・管理栄養士にとって実践的かつ今後の活動に直結する知見が多数示されました。この講演のレビュー記事が、栄養士・管理栄養士向け情報サイト「あじこらぼ」(味の素株式会社)で公開されましたのでご紹介します。
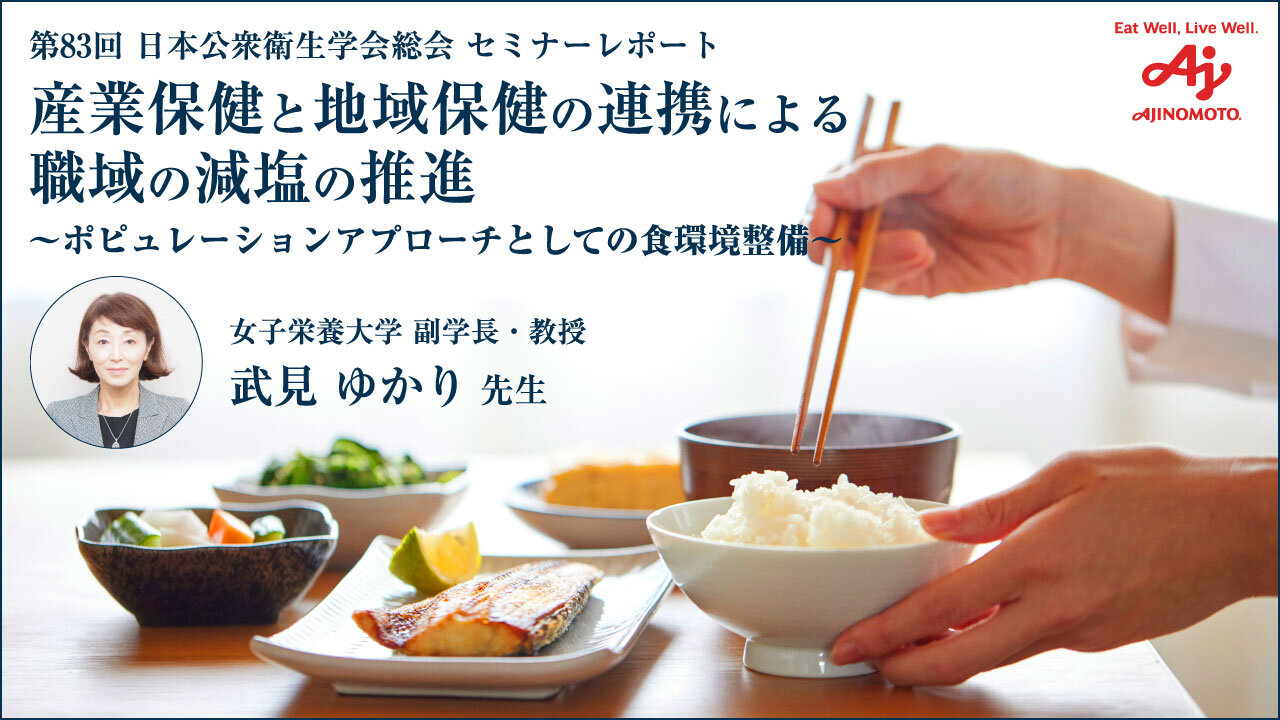
減塩の目標達成には環境整備がカギ
日本人の平均食塩摂取量は現在も10g前後で推移しており、2024年度から始まった「健康日本21(第三次)」で掲げられた国民平均7gという目標を達成するには、新たな視点からのアプローチが不可欠です。武見先生は、個人の努力だけに頼るのではなく、“自然に健康になれる環境づくり”の一環としての「食環境整備」の必要性を強調しました。
講演では、職域での食環境改善による具体的な減塩の成功事例が2件紹介されました。1つは、社員食堂を持たない企業でスマートミール対応弁当の導入と減塩講話の実施により、食塩摂取量と尿Na/K比が有意に改善した事例。もう1つは、社員食堂を持つ企業において、メニューの減塩化と情報提供を行った結果、従業員の血圧が有意に低下した事例です。いずれも、「食品へのアクセス」と「情報へのアクセス」の両輪が有効に機能した好例として紹介されました。
また、武見先生は、情報提供だけのポピュレーションアプローチで生活習慣を変えるには限界があることを指摘。人々が無意識のうちに減塩を実現できるような、食品そのものの質の改善が、健康格差の是正にもつながる重要な施策であると述べました。
今後、栄養士・管理栄養士には、従来の教育活動に加えて、職域や地域と連携した食環境づくりの視点がますます求められます。減塩を社会全体で推進するための中核的存在として、多職種との連携を活かした取り組みが期待されています。
このセミナーレポートの全文と印刷用のPDFは、Webサイト「あじこらぼ」で絶賛公開中です。栄養に携わる方にとって必見の内容ですので、ぜひご一読ください。
レビュー記事の全文&PDFダウンロードはこちら!
第83回 日本公衆衛生学会総会「産業保健と地域保健の連携による職域の減塩の推進~ポピュレーションアプローチとしての食環境整備~」
武見 ゆかり 先生(女子栄養大学 副学長・教授)







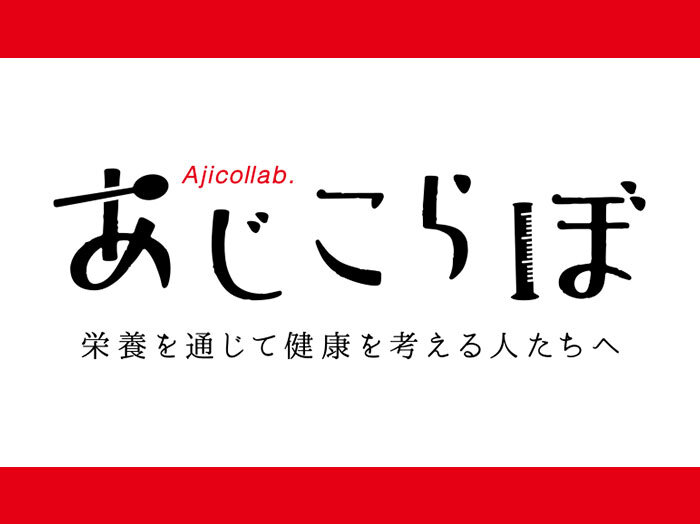
















 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!











