中年期以降に食事の多様性が増すことは寿命に影響するのか? JACC Studyの2万人超を調査
食習慣が健康状態に強く関与していて、心血管死や癌死、および全死亡のリスクと関連のあることは広く知られている。しかし、人々の食習慣は人生の途中で変化することも少なくない。では、そのような変化が生じた場合に、死亡リスクも変化するのだろうか? この疑問に対する一つの答となる日本人対象研究の結果が、「Journal of Epidemiology」に掲載された。国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 ヘルス・メディカル微生物研究センターの渡邉大輝氏、愛媛大学大学院農学研究科の丸山広達氏らが報告した。

日本人における食事の多様性の変化と死亡リスクとの関連を解析
食習慣と健康アウトカムとの関連については、横断研究にとどまらず縦断研究のエビデンスも存在する。しかし、それらの研究の大半は食習慣を一時点でのみ評価していて、観察期間中に生じた可能性のある食習慣の変化が考慮されていない。それでも海外からは、地中海食スコアや代替健康食事指数(Alternate Healthy Eating Index;AHEI)で把握した食習慣の改善が、死亡リスクと負に関連することが報告されている。ただ、日本人でのエビデンスはみられない。渡邉氏らは、国内多施設共同大規模コホート(the Japan Collaborative Cohort)研究(JACC Study)のデータを用いてこの点を検討した。
JACC Studyは、1988~90年に国内45地域に居住する40~79歳の成人11万585人を登録し、2009年まで健康アウトカムを前向きに追跡した研究。このJACC Study参加者のうち、ベースライン時および追跡5年目に実施した食物摂取頻度調査票(Food Frequency Questionnaire;FFQ)を用いた調査に回答していて、それまでにがん・心血管疾患に罹患しておらず、その他のデータ欠落のない2万863人(ベースライン時の年齢55.7±9.3歳、女性63.0%)を解析対象とした。
食事の多様性の変化パターンに基づき、4群に分けて死亡リスクを比較
食習慣の評価には、食品摂取の多様性スコア(Dietary diversity Score;DDS)を用いた。33種類の食品について、FFQで把握した摂取頻度に基づき0~1点の間にスコア化し、合計33点満点のDDSを算出。すると、ベースライン調査におけるDDSの平均は10.5点、5年後の調査の平均は10.3点だった。
各調査の平均点の上か下かで、多様性が‘高い/低い’と判定。2回の調査での判定結果に基づき、全体を4群に群分けして、死亡リスクを比較した。各群の該当者割合は以下のとおり。
ベースライン調査と追跡調査ともに‘低い’で一貫していた「低/低」群(37.7%)、ベースライン調査では‘低い’だったものが追跡調査では‘高い’に改善していた「低/高」群(14.1%)、ベースライン調査では‘高い’だったものが追跡調査では‘低い’に悪化していた「高/低」群(14.4%)、ベースライン調査と追跡調査ともに‘高い’で一貫していた「高/高」群(33.8%)。
食事の多様性が一貫して高かった群のみ、死亡リスクが有意に低いという結果
中央値14.8年(四分位範囲6.9~16.1)、25万6,277人年の追跡で、2,995人(14.4%)が死亡していた。解析に際しては、交絡因子(年齢、性別、地域、BMI、喫煙・飲酒・運動・睡眠習慣、エネルギー摂取量、テレビ視聴時間、就業状況、婚姻状況、高血圧・糖尿病の既往など)の影響を統計学的に調整したうえで、「低/低」群を基準として死亡リスクを比較した。
その結果、「高/高」群でのみ、全死亡(ハザード比〈HR〉0.82〈95%CI;0.74~0.91〉)と心血管死(HR0.81〈0.67~0.98〉)のリスクの有意な低下が観察された。「低/高」群や「高/低」群は「低/低」群と有意差がなかった。つまり、5年の間に食事の多様性が変化したことによる死亡リスクへの影響は認められなかった。
なお、癌死や呼吸器疾患死については、「高/高」群も「低/低」群との差は有意ではなった(それぞれ、HR0.93〈0.80~1.09〉、0.93〈0.69~1.25〉)。
性別の解析では、男性の死亡リスクはDDSと関連なし
続いて性別ごとに解析すると、女性では全体解析と同様に、「高/高」群では、全死亡(HR0.73〈0.63~0.85〉)と心血管死(HR0.54〈0.31~0.94〉)のリスクの有意な低下が観察された。「低/高」群や「高/低」群の死亡リスクは、やはり「低/低」群と有意差がなかった。
一方、男性では「高/高」群においても、死因にかかわらず「低/低」群と有意差がなかった。
中年期以降に食事の多様性を改善しても死亡リスクは変わらない可能性
著者らは本研究を「日本人を対象にDDSの変化と全死亡リスク、死因別死亡リスクとの関連を検討した初の研究」と位置づけている。
結果的に、DDSの変化と死亡リスクとの有意な関連は認められなかった。先述のように、海外の先行研究では、地中海食スコアやAHEIで把握した食習慣の改善が死亡リスクと負に関連するという、本研究とは異なる結果が示されている。この違いの理由として著者らは、「食事の多様性を表すDDSは他の指標より解釈が容易ではあるが、ナトリウムや飽和脂肪酸などの控えるべき栄養素の摂取が多い場合にも高く評価される傾向があることなどの影響が考えられる」として、「より精度の高い指標を用いた再検討が必要な可能性がある」としている。
また、DDSと死亡リスクとの関連が女性で有意、男性では有意ではないという結果の理由として、男性は野菜や果物、乳製品の摂取量が全体的に少なく、DDSの高低で分けても群間差があまりないこと、サンプル数が少なかったために統計的に有意になりにくいこと、調理の習慣や食品に関する知識が女性ほど高くない可能性があることなどの影響を挙げている。
結論として、「40歳以上の国内一般住民を対象とした我々の研究により、DDSで評価した食事の多様性の高さが全死因および心血管疾患による死亡のリスクと負に関連していることが示された。ただし、性別ごとの解析では女性においてのみ、それらの関連が有意だった。さらに、ベースラインから5年後までのDDSの変化は死亡リスクと有意な関連がなかった。よって、中年期以降に食事の多様性が向上しても、死亡リスクが抑制されない可能性が示唆された。このことは、食事の多様性が低い人に対して、より早期から改善を働きかけることの必要性を示しているとも考えられる。ただし、本研究結果の検証のため、より大規模なサンプル、かつ食事の質のより精緻な評価手法を用いた今後の研究が必要かもしれない」とまとめられている。
文献情報
原題のタイトルは、「Changes in dietary diversity and subsequent all-cause and cause-specific mortality among Japanese adults: The Japan Collaborative Cohort Study」。〔J Epidemiol. 2025 Mar 8〕
原文はこちら(J-STAGE)









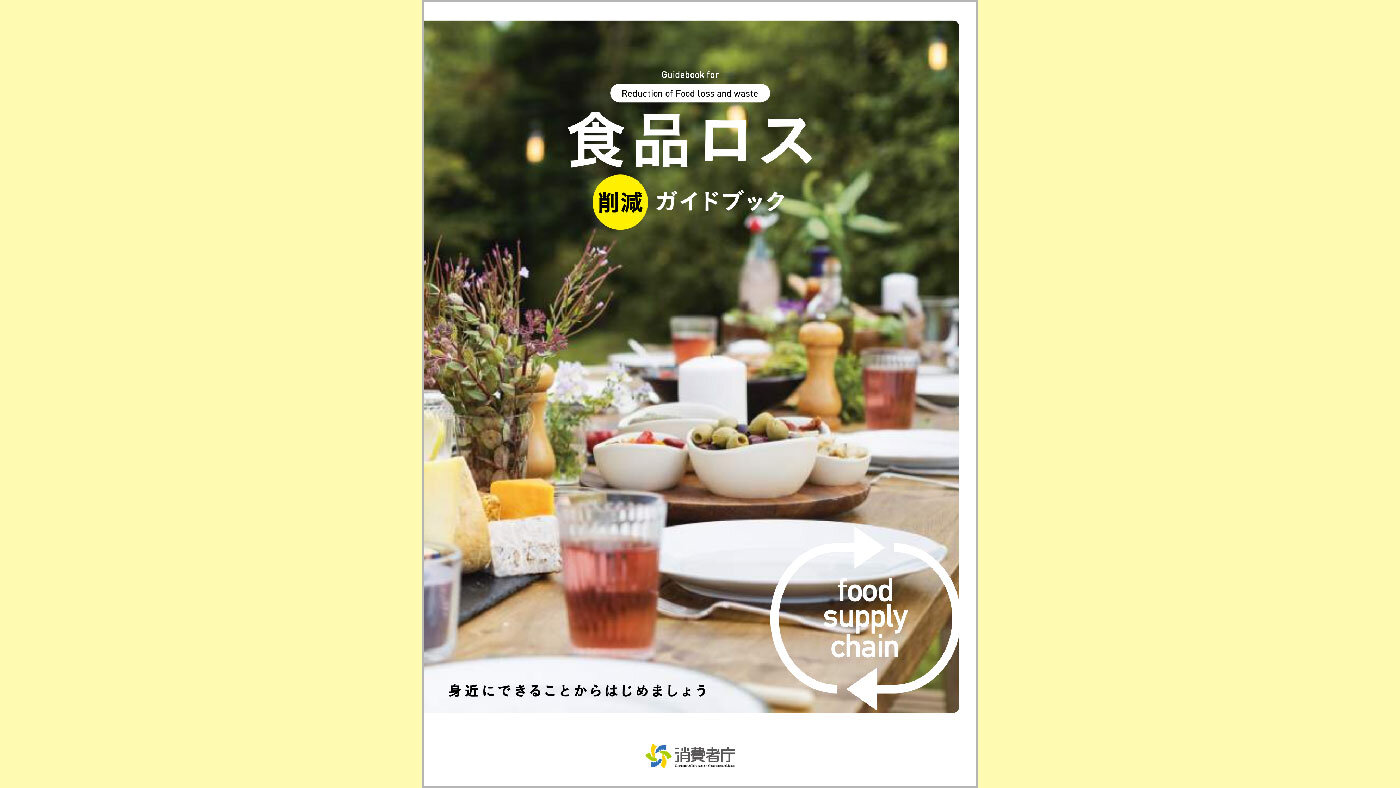













 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!








