学校給食が経済的に困難な世帯の子どもの肥満を抑制 効果は卒業後少なくとも数年間持続 上智大学
学校給食が、経済的に困難な世帯の中学生の体重や肥満率を抑制するように働いていることが報告された。上智大学と曁南大学(中国)の研究者による研究の結果であり、「Health Economics」に論文が掲載されるとともに、大学のサイトにプレスリリースが掲載された。この効果は、中学校を卒業して給食を食べなくなった後も、少なくとも数年間は持続するという。著者らは、「学校給食には、子どもの食習慣を望ましい方向に変化させる食育効果があることが示唆される」としている。

研究の背景:給食に長期的な食育効果はあるのか?
世界中で肥満が急増するなか、肥満対策としての学校給食の役割が国際的に注目されている。しかし、その効果について十分なエビデンスがなく、また学校給食には多大なコストがかかることが問題視されることもある。
日本でも、このトピックについて、個人レベルのデータを用いた精緻な検証は本研究が初めて。また、給食が体重に与える効果は、給食がなかった場合に持参したであろう弁当の内容に依存するため、世帯や地域の特性によって効果が違うと考えられるが、子どものバックグラウンドによる効果の違いは世界的にも十分検討されていなかった。
さらに、日本の学校給食に関しては、食事摂取を通じて生徒の健康を直接的に改善するだけでなく、「食育」と呼ばれる教育効果を通じて長期的な食習慣改善効果を持つことが期待されているが、給食の中長期的な効果についてはよくわかっていなかった。
研究の方法:給食のある学校とない学校の生徒の体型指標の差を検討
この研究では、厚生労働省の「国民栄養調査(現:国民健康・栄養調査)」の1975~94年の個人レベルのデータを用いた分析が行われた。同調査は、日本全国を代表するサンプルでさまざまな個人特性とともに身長・体重の計測値がわかる、世界的にも貴重なデータ。
日本では公立小中学校の生徒は、通っている学校で給食が提供されていれば原則として給食は強制参加であり、また、ほぼすべての公立小学校で給食がある一方で、公立中学校では市区町村により給食の有無が分かれている。この差を利用して、中学校給食のある地区とない地区で小学4~6年生と中学生の体型指標の差を比較するという、差の差(difference-in-differences;DID)分析を行った。
分析の結果:給食のある学校では、社会経済的地位の低い世帯の子どもの肥満が少ない
分析結果は、全体では中学校給食による体重や肥満への有意な効果はみられなかった。しかしその一方で分析対象を、非ホワイトカラーの父親の子や、一人あたり世帯支出が低い世帯の子ども、すなわち社会経済的地位の低い世帯の子どもに限定すると、中学校給食によりボディマス指数(BMI)や肥満度、肥満が有意に減少することが示された。
中学校給食による肥満減少効果は母親のBMIが高い子どもやエネルギー摂取の多い地域の子どもなど、エネルギー過剰摂取のリスクが高い子どもにもみられたことから、給食がエネルギーの過剰摂取を抑制することで肥満を減少させたことが示唆される。
さらに、社会経済的地位の低い世帯の子どもへの給食の肥満減少効果は、中学卒業後の15~17歳にも認められた。このことから、給食を食べることで直接的に肥満が減少するだけでなく、「食育」の理念のとおり、学校給食が食生活の改善を通じた長期的な肥満抑制効果を持つことが示唆された。
一方、学校給食による瘦せすぎへの影響は全く見られなかった。
今後の展望:給食の費用対効果の検討には肥満抑制を介したコスト低減も考慮が必要
本研究は、学校給食が社会経済的地位の低い世帯の子どもに対して肥満抑制効果をもつことを示唆しており、生徒全員を対象に厳しい栄養基準に基づいて栄養バランスのとれた昼食を提供する日本の学校給食、および、給食を教育の一部として位置づける「食育」の高い価値を示すものと言える。
また、学校給食実施には多大な費用がかかるという経済的ハードルがあるが、費用対効果の評価にあたっては、小中学生の栄養状態改善による直接的かつ短期的な効果だけでなく、食習慣改善による長期的効果を考慮する必要があることを示唆している。
プレスリリース
学校給食は経済的に困難な世帯の子供の肥満を減らすことが明らかに 卒業後少なくとも数年間は肥満減少効果が持続(上智大学)
文献情報
原題のタイトルは、「Wholesome Lunch to the Whole Classroom: Short- and Longer-Term Effects on Early Teenagers' Weight」。〔Health Econ. 2025 Mar 18〕
原文はこちら(John Wiley & Sons)
















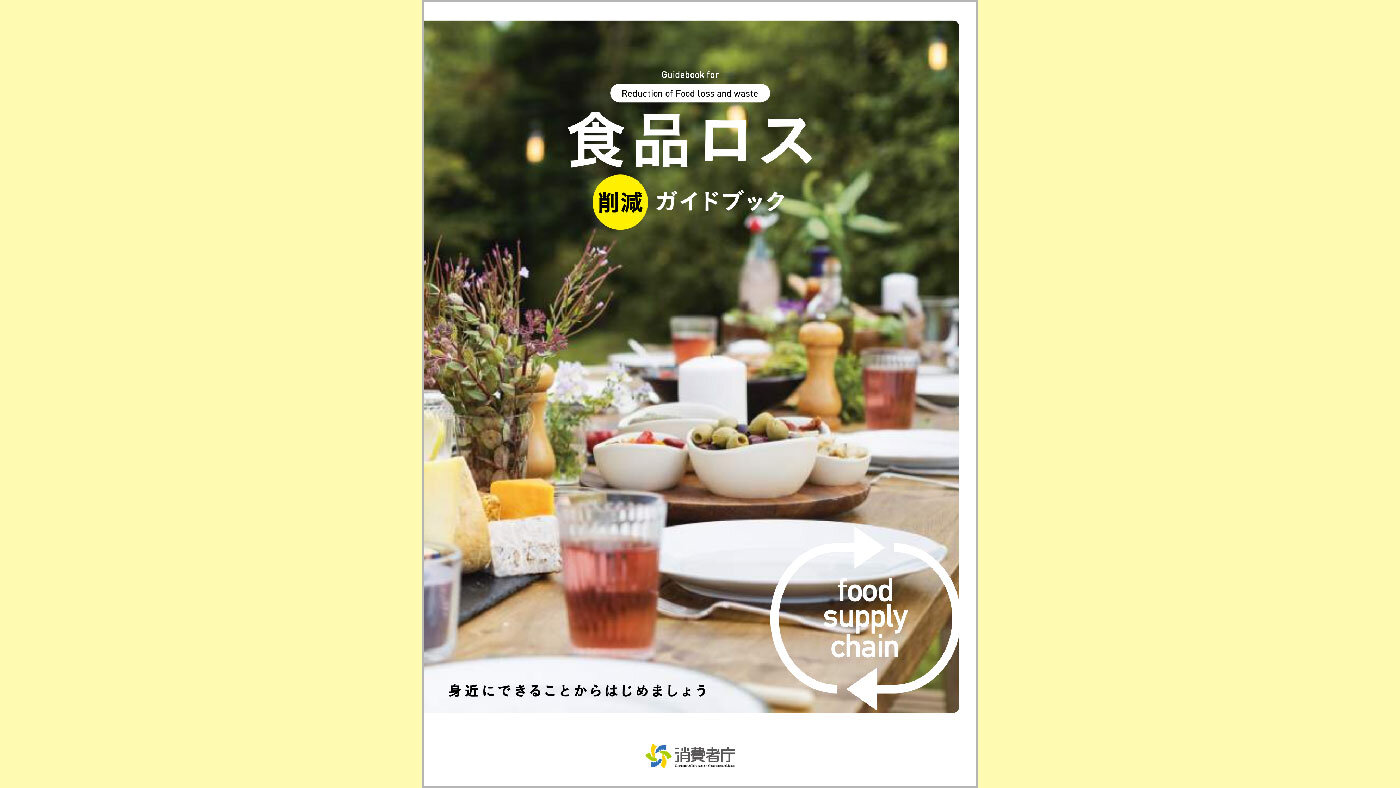






 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!











