クレアチンが血管内皮機能を改善か 二重盲検試験でFMD、空腹時血糖、中性脂肪が改善
アスリートのパフォーマンス上のメリットに関するエビデンスが豊富なクレアチンが、血管機能に対して保護的に働く可能性のあることを示唆する研究結果を紹介する。二重盲検クロスオーバー試験の結果、プラセボでは変化のみられなかった血管内皮機能などに、有意な改善が認められたという。米国の研究者によるパイロット研究の報告。
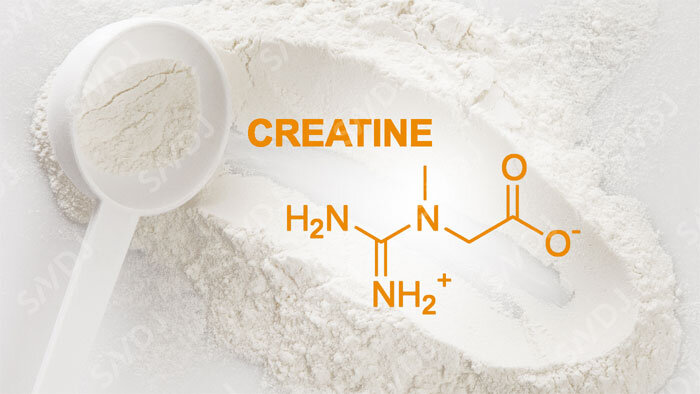
クレアチンの医学領域での可能性を探る研究
クレアチンは、スポーツ栄養の領域ではさまざまなエビデンスが蓄積されてきており、パフォーマンス向上のために利用しているアスリートが少なくない。クレアチンのスポーツパフォーマンス上のメリットは、アデノシン三リン酸(adenosine triphosphate;ATP)再合成促進作用などによるものと考えられるが、基礎研究では、クレアチンが抗酸化作用、抗炎症作用、代謝機能改善・脂質低下作用なども有することが示されている。
一方、酸化ストレスや慢性炎症、糖・脂質代謝低下等を基盤として発症・進展する血管性疾患が昨今、世界的に増加しており、膨大な患者が薬剤による医学的治療を受けている。薬物介入により心血管疾患(cardiovascular disease;CVD)等のリスクを抑制可能であるが、医学的治療には副作用のリスクがあり、また医療費の増大、服薬アドヒアランス不良による効果減少、医療アクセス状況次第で生じる受けられる恩恵の格差などの問題もつきまとう。サプリメントとして流通しているクレアチンに、仮に血管機能を保護する作用があるとすれば、これらの問題を部分的に緩和し得る。
以上を背景として本論文の著者らは、クレアチンの血管保護作用を探るパイロット研究を実施した。
研究の対象と方法について
この研究の対象は、ふだんの運動量が少ない(中強度運動の時間がガイドライン推奨の週150分以下)、50~64歳の成人12人。心血管疾患(CVD)や代謝性疾患の既往、管理不良の高血圧、クレアチン摂取者、喫煙者などは除外した。また、血清クレアチニンが0.6~1.2mg/dLの範囲で、腎機能(eGFR)が60mL/分/1.73m2以上、尿素窒素(BUN)6~24mg/dLを参加の適格条件とした。なお、運動量が十分でない成人を対象としたのは、そのほうが血管機能が低下していることが多いと想定され、介入効果の検討に適していると考えられたことによる。
試験デザインは、プラセボ対照二重盲検クロスオーバー法で、無作為に6人ずつの2群に分け、1群にはクレアチン、他の1群にプラセボを支給し4週間摂取してもらい、4週間のウォッシュアウト期間をおいて割り付けを変更して4週間摂取してもらった。プラセボはマルトデキストリンを用いた。
摂取量は両者ともに、最初の5日のローディング期間(体内のクレアチン量を高めるための期間)は1日20g(5gを4回)、その後の23日間(クレアチンのターンオーバーを満たし体内量を維持する期間)は1日5gとした。支給したサプリがクレアチンかプラセボかは、研究参加者および研究者にもマスクし、割り付けを知らされていない別の研究者が結果を解析した。
評価項目は、動脈の血管内皮機能の指標である血流依存性血管拡張反応(flow mediated dilation;FMD)、動脈の柔軟性の指標である脈波伝播速度(pulse wave velocity;PWV)、および近赤外分光法を用いた細小血管機能、酸化ストレスマーカー、採血検査に基づく糖・脂質関連指標などであり、これらを12時間以上の絶食、カフェイン・アルコール摂取と運動の禁止後に評価した。
4週間のクレアチン摂取で血管機能、血糖値、中性脂肪に好ましい変化
研究参加者の年齢は58.3±3.4歳、男性・女性が各6人、BMI25.6±5.6だった。前記の評価項目のうち、脈波伝播速度(PWV)、酸化ストレスマーカーに関しては、有意な影響は観察されなかったが、FMDや細小血管機能、糖・脂質関連指標には、以下のような有意な影響が認められた。
FMDはクレアチン条件でのみ介入後に有意に上昇
血流依存性血管拡張反応(FMD)は、血管内皮から放出される一酸化窒素(NO)依存性の血管拡張反応を測定するもので、値が高いほど内皮機能が良好と判断する。
本研究において、プラセボ条件では介入前が8.13±2.76%、介入後は8.08±2.07%であり、有意な変化はみられなかった。一方、クレアチン条件では同順に7.68±2.25%、8.90±1.99%であり、介入によって有意に上昇し、かつ介入後の値はプラセボ条件より有意に高かった。より高精度な指標とされるシェアストレス(せん断応力)で補正した値で検討した場合も、同様の結果が得られた。
細小血管機能もクレアチン条件でのみ有意な変化
近赤外分光法を用いた細小血管機能の評価(虚血-再灌流後の酸素飽和度の回復速度)に関しては、プラセボ条件では介入前が2.47±1.4%/秒、介入後は2.11±1.01%/秒であり、有意な変化はみられなかった。一方、クレアチン条件では同順に2.29±1.42%/秒、3.71±1.44%/秒だった。前記のFMDと同様に、クレアチン条件では介入によって有意に上昇し、かつ介入後の値がプラセボ条件より有意に高かった。
クレアチン条件では空腹時血糖と中性脂肪が低下
空腹時血糖は、プラセボ条件では介入前が101.91±7.53mg/dL、介入後は102.82±9.23mg/dLであり、有意な変化はみられなかった。一方、クレアチン条件では同順に103.64±6.28mg/dL、99±4.9mg/dLと有意に低下していた。
同様に、トリグリセライド(triglyceride;TG〈中性脂肪〉)も、プラセボ条件では91±46.34mg/dL、99.45±45.1 mg/dLと有意な変化がないのに対して、クレアチン条件では99.82±35.35mg/dL、83.82±37.65mg/dLと有意に低下していた。
著者らは、「これらの結果はクレアチンの血管系に対する潜在的なメリットの裏付けと言える。この発見の検証と、作用メカニズムの理解のために、より大規模な研究が期待される」と述べている。
文献情報
原題のタイトルは、「Effect of Creatine Monohydrate Supplementation on Macro- and Microvascular Endothelial Function in Older Adults: A Pilot Study」。〔Nutrients. 2024 Dec 27;17(1):58〕
原文はこちら(MDPI)























 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!











