ケルセチンが高齢者の筋トレをサポート 閾値の高い運動単位が動員され筋力アップ 日本人対象RCT
フラボノイドの一種のケルセチンが、高齢者の筋力トレーニングの効果を押し上げることを示唆するデータが報告された。日本人対象RCTの結果であり、閾値の高い(強い力を出す)運動単位が動員されて、プラセボよりも高い筋力向上が認められたという。中京大学大学院スポーツ科学研究科の渡邊航平氏らの研究によるもので、「European Journal of Nutrition」に論文が掲載された。

高齢者の筋トレの安全性と有効性を両立させる戦略を探る研究
加齢に伴うサルコペニアやフレイルの抑止のために、筋力トレーニング(筋トレ)が推奨される。より効果的に筋力を高めるためには高強度の筋トレが適しているが、高齢者では関節機能の低下や安全性の懸念などがあり、十分な負荷をかけられないことが少なくない。
一方、加齢に伴う筋力低下は、筋線維萎縮や筋神経支配の喪失などによって運動単位(motor unit;MU)が減少することの影響が大きいと考えられており、これに対して、高出力を発揮するための運動単位(動員閾値の高い運動単位)を増加させる介入方法が提案されている。例えば、全身の振動を併用した筋トレや、血流制限下での筋トレだ。ただし、それらはいずれも専用機器と専門家の監視が必要であり、実用性が乏しい。
他方、ケルセチンはアセチルコリンやドーパミンなどの神経伝達物質の放出を刺激したり、運動単位の発火頻度を変化させたりすることが知られている。ケルセチン摂取により、筋線維の伝道速度が上昇するといった、先行研究の報告もある。よって、ケルセチン摂取という簡便な手法が、高齢者の筋トレ効果を高める可能性がある。渡邊氏らはそのような仮説の下、以下の研究を行った。
日本人高齢者を対象に、筋トレを併用して6週間介入
研究参加者は65~82歳の健康な高齢者30人。BMI18.5~35、運動制限がないことが適格条件で、人工関節置換術の既往者やケルセチンを含むサプリメント摂取者などは除外されている。
試験デザインはプラセボ対照二重盲検並行群間比較試験であり、年齢、性別の分布、およびベースライン時点の筋力のバランスを考慮したうえで、ケルセチン摂取群とプラセボ摂取群に割り付け、6週間の筋トレ介入中にそれらを摂取してもらった。
ケルセチン群は200mgのケルセチンとデキストリン1.8g、プラセボ群は2gのデキストリンを毎朝水とともに摂取。これらは、外観などから区別できないカプセルとして支給した。筋トレは膝伸展筋の強化を意図して、最大随意筋力(maximal voluntary force;MVF)の60%の強度で10回を3セット、週3回とした。
評価項目は、体組成、MVF・筋肉厚・運動単位(いずれもトレーニングを行った脚で測定)、体力テスト(椅子立ち上がりテスト、timed up&go test〈TUG〉)などであり、介入前、介入開始3週時点、介入終了1週間後という3時点で評価した。
運動単位(MU)については、動員閾値の変化を把握するために、すべての運動単位(MUall)に加えて、MVFの0~20%(MU0-20)、20~40%(MU20-40)、40~60%(MU40-60)と、負荷強度を細分化した評価も行った。なお、運動単位の動員閾値とは、筋肉が収縮する時、ある運動単位が活動を開始するのに必要な最小限の力のことで、小さい力で働く運動単位は動員閾値が低く、大きな力を出す運動単位は動員閾値が高い。
このほか、簡易型自記式食事歴質問票(brief-type self-administered diet history questionnaire;BDHQ)と国際標準化身体活動質問票(International Physical Activity Questionnaire;IPAQ)により、栄養素摂取量と身体活動量を評価した。
主要評価項目は最大随意筋力(MVF)であり、上記のその他の指標は副次評価項目として設定されていた。
ケルセチンは動員閾値の高い運動単位への働きかけを介して、筋力を向上する可能性
介入中に4人が脱落し、解析対象は26人となった。ケルセチン群が13人(73±4歳、男性6人)、プラセボ群が13人(71±5歳、男性5人)であり、ベースライン時点で、体組成、筋力、筋肉厚、運動単位(MU)、栄養素摂取量、身体活動量など、すべての評価項目に有意差がなかった。
ケルセチン群で筋力が有意に大きく上昇
主要評価項目である最大随意筋力(MVF)は、プラセボ群が介入前111.2±47.4Nm、介入後117.1±49.9Nm、ケルセチン群が同順に93.9±25.4Nm、105.9±25.5Nmであり、両群ともに有意に上昇していたが(p<0.001)、介入後の値に有意差はなかった(p=0.240)。ただし、介入前後での変化率は、プラセボ群5.3±4.8%、ケルセチン群15.1±11.0%であり、後者のほうが有意に大きく上昇していた(p<0.001)。
筋肉厚、筋肉量、体力テストについては、本研究の6週間の介入では時間効果が有意でなく、群間差も非有意だった。
ケルセチン群では動員閾値の高い運動単位の発火頻度が低下
運動単位の動員閾値は、介入前は群間に有意差がなかった。それに対して介入後には、ケルセチン群において発火頻度が低下しており、とくに閾値の高い運動単位で群間差が有意だった(MUallおよびMU20-40、MU40-60は群間差が有意であり、MU0-20は非有意)。
また、ケルセチン群において、介入前後のMU40-60の変化率はMVFの変化率と有意に正相関していた(r=0.642、p=0.018)。MUallやMU20-40、MU40-60の変化率とMVFの変化率との関連は非有意であったことから、ケルセチンは動員閾値の高い運動単位への働きかけを介して筋力向上作用を高める可能性が示唆された。なお、プラセボ群では負荷強度の強弱にかかわらず、動員閾値とMVFの変化率との有意な関連は認められなかった。
著者らは、「われわれの研究結果は、ケルセチンの摂取がより高い動員閾値の運動単位の適応を向上し、筋力トレーニングと組み合わせることでその効果が拡大し、高齢者の筋力改善における有効な戦略となり得ることを示している」と総括している。
文献情報
原題のタイトルは、「Quercetin ingestion alters motor unit behavior and enhances improvement in muscle strength following resistance training in older adults: a randomized, double-blind, controlled trial」。〔Eur J Nutr. 2025 Mar 10;64(3):117〕
原文はこちら(Springer Nature)









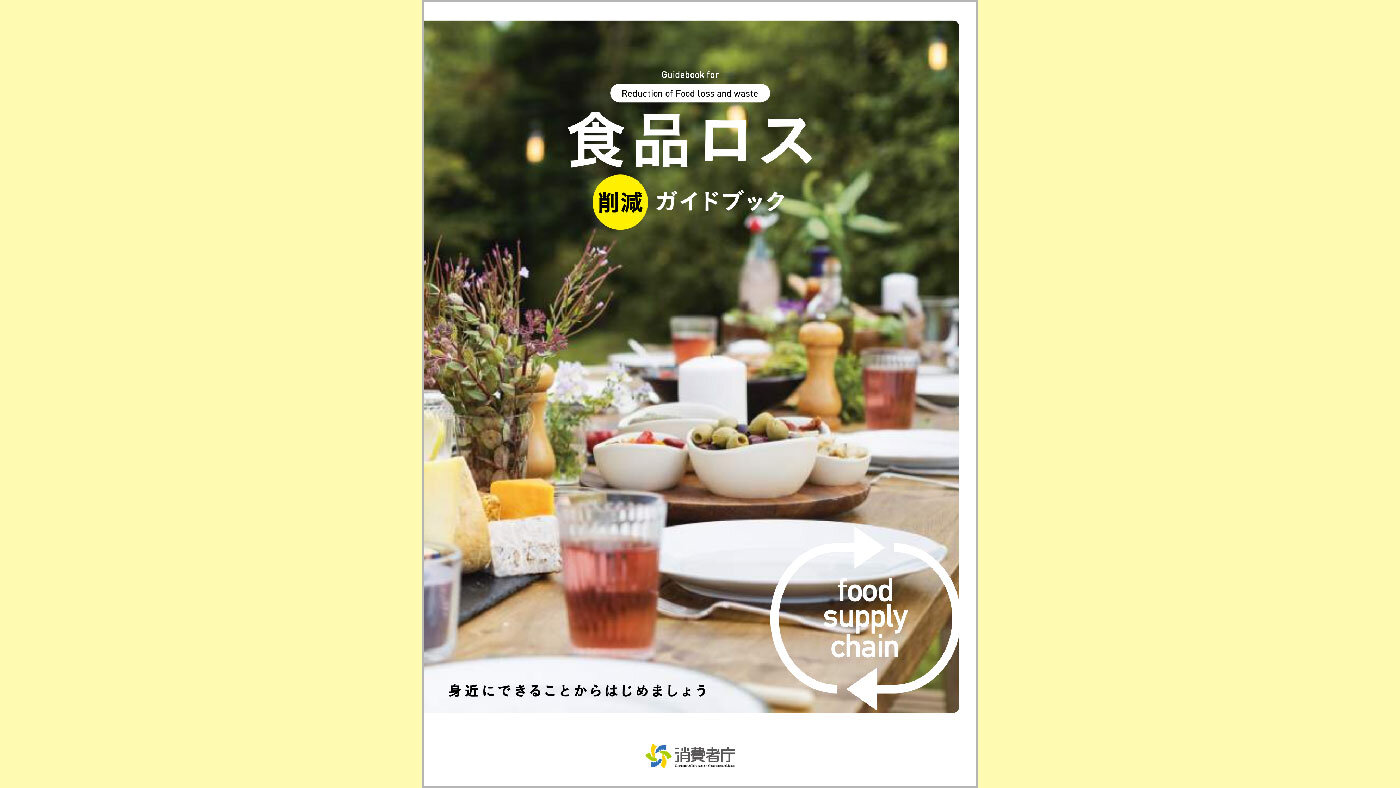













 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!








