カルシウムの摂取量が転倒リスクと関連 国内地域住民対象コホート研究のエビデンス
国内の40歳以上の地域住民を対象とする研究から、カルシウム摂取量が少ない場合に転倒リスクが高いことが報告された。横断的解析と縦断的解析のいずれでも、有意な関連が認められるという。新潟大学大学院医歯学総合研究科健康増進医学講座の蒲澤佳子氏らの研究の結果であり、「The Journal of nutrition、health and aging」に論文が掲載された。
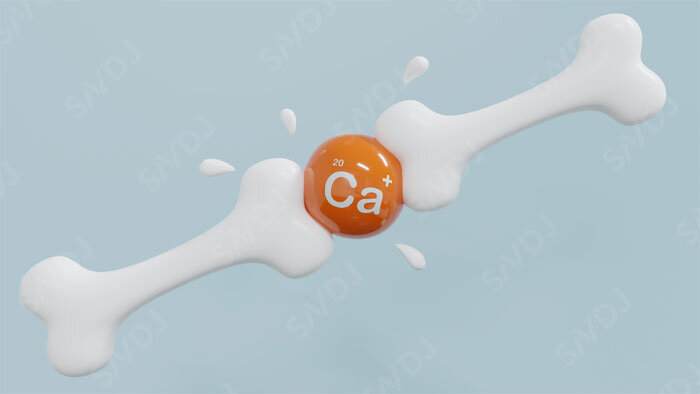
カルシウム摂取量と転倒リスクとの関連は?
転倒は高齢者の外傷の主要な原因であり、転倒に伴う骨折を機に、長期臥床、身体障害、認知機能低下、要介護、死亡へとつながることも少なくない。一方、高齢者の骨折のリスク因子として骨量減少を主徴とする骨粗鬆症が挙げられ、骨量減少に対してはカルシウム摂取量を増やすことが有効とするエビデンスがある。ただし、カルシウム摂取量と転倒リスクとの関連の知見は少ない。
これを背景として蒲澤氏らは、新潟県で行われている地域住民コホート研究(魚沼コホート、湯沢コホート)のデータを用いて検討を行った。
40歳以上の地域住民を対象とした前向きコホート研究5年追跡データを分析
この研究は、解析に必要なデータの欠損、および体格指数(BMI)と摂取エネルギー量の外れ値を除外し、横断的解析は男性1万8,439人、女性2万127人、縦断的解析は同順に1万3,872人、1万5,361人を解析対象とした。
カルシウム摂取量は食物摂取頻度調査票から把握し、残差法により摂取エネルギー量で調整した値を用いた。転倒については、過去1年以内の転倒の有無を質問票で調査した。ベースラインの分析対象者の特徴として、男性は平均年齢が62.7歳、カルシウム摂取量のエネルギー調整中央値は463mg/日、過去1年間で転倒を経験していた割合は19.5%であった。女性は同順で、63.5歳、577mg/日、18.8%であった。
本研究では、性別ごとのカルシウム摂取量の四分位数に基づき、それぞれ4群に分け、第4四分位群(カルシウム摂取量が多い上位25%)を基準として、過去1年以内に転倒の経験を有することのオッズ比を算出した。横断的解析では、結果に影響を及ぼし得る因子(年齢、BMI、喫煙・飲酒習慣、身体活動量、摂取エネルギー量、地域、慢性疾患の有無、骨折の既往、独居/同居)を調整した。縦断的解析ではさらに、ベースラインの転倒経験の有無を調整した。
男性・女性ともにカルシウム摂取量が少ない群に転倒経験者が多い
横断的解析では、男性、女性ともに、カルシウム摂取量が多い群に比べて、少ない群ほど転倒経験者が多いという有意な関連が認められた。この結果は縦断的解析でも同様であり、カルシウム摂取量の四分位群の最も少ない群は、最も多い群に比べた転倒の調整オッズ比が男性では1.20 (95%信頼区間1.04、1.40)、女性では1.23 (95%信頼区間 1.09、1.39)であった(男女とも傾向性p<0.05)。
年齢層(65歳未満/以上)、BMI(22未満/以上)、および身体活動量(性別ごとの中央値〈男性39.9、女性38.5MET・時/週〉未満/以上)で層別化した解析を実施したところ、男性では若年、BMI低値、身体活動量が多い群で、より明らかな関連が認められた。女性ではそれらの特徴による差異は認められなかった。
以上一連の結果に基づき著者らは、「40歳以上の一般成人の転倒予防において、適切なカルシウム摂取が重要であるというエビデンスを得られた。食習慣が異なる他の集団での、さらなる研究が求められる」と結論づけている。
文献情報
原題のタイトルは、「Association of dietary calcium intake with risk of falls in community-dwelling middle-aged and older adults」。〔J Nutr Health Aging. 2024 Dec 31;29(3):100465〕
原文はこちら(ELSEVIER)























 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!











