糖尿病予備群の血糖変動と栄養素摂取量、活動量、交感神経活性、心拍数の関連を詳細解析
心電図データや連続血糖測定データなどの測定結果が蓄積されたオープンアクセスのデータベース(PhysioNet)を用いて、HbA1cが正常高値で糖尿病ハイリスク状態にある人の血糖変動と関連のある因子を、詳細に検討した結果が報告された。栄養素摂取量と血糖上昇・低下速度との関連なども報告されている。北海道大学病院医療・ヘルスサイエンス研究開発機構の宮腰崇氏、伊藤陽一氏による研究であり、「JMIR diabetes」に論文が掲載された。

糖尿病予備群の血糖変動にはどんな生体パラメーターや食事バターンが関連するのか?
2型糖尿病の患者数が世界的に増加し、医療コストの増大を招いている。糖尿病発症後には基本的に生涯にわたる治療が必要とされるため、可塑性のある前糖尿病(予備群)に対する介入の重要性が高まっており、糖尿病への移行を防ぐ効率的な戦略が模索されている。
これまでにも多くの疫学研究や介入研究の報告があり、それらの知見に基づき、おもに食事・栄養、運動・身体活動をターゲットとした介入が行われてきている。しかし近年、ウェアラブルデバイス技術の進歩により、従来の研究手法では把握できなかったパラメーターをリアルワールドで評価できるようになってきた。例えば、心拍数や交感神経活性などであり、さらに血糖変動を連続的に把握したり、身体活動強度も知ることができるようになっている。そして、それらのデータの一部は、「PhysioNet」と呼ばれるデータベースに公開され、研究目的でのオープンアクセスが可能とされている。
宮腰氏らは、PhysioNetのデータを活用し、糖尿病予備群の人の生体パラメーターや摂取栄養素と血糖変動との関連の詳細な検討を行い、糖尿病発症抑制戦略への応用可能性を探った。
食後血糖上昇速度は炭水化物摂取量と正、食物繊維摂取量と負の独立した関連
PhysioNetのデータベースから、血糖変動に焦点を当てた研究を検索した結果、35~65歳の男性または閉経後女性でHbA1cが5.3~6.4%の範囲(平均5.73±0.28%)の16人を対象に、手首装着型のウェアラブルデバイスと連続血糖測定(continuous glucose monitoring;CGM)を用いて8~10日間にわたりモニタリングしたデータが見つかった。
この研究では、3軸加速度センサーにより把握された身体活動量や、心拍数、心拍の間隔、皮膚温、および交感神経活性の指標である皮膚電気活動などが測定されていたほか、栄養素摂取量が評価されていた。本論文は、それらのパラメーターと血糖値や血糖変動との関連を詳細に解析した結果が示されているが、本稿ではその中から栄養素摂取量との関連を中心に紹介していく。
食後の血糖上昇速度と関連のある因子
食事開始直後の血糖値が最も低い時点から、食後の血糖値が最も高い時点の血糖変動の幅を、その間の経過時間で除して、血糖上昇の傾き(血糖上昇速度を表す)を算出したうえで、重回帰分析で関連因子を検討した。
その結果、正の独立した関連のある因子として、皮膚温(t=2.52、p=0.01)と炭水化物摂取量(t=6.53、p<0.001)、タンパク質摂取量(t=3.82、p<0.001)が特定された。反対に、負の独立した関連のある因子として、摂取エネルギー量(t=-3.98、p<0.001)と食物繊維摂取量(t=-2.51、p=0.01)が特定された。
続いて、評価した各パラメーターの標準偏差を独立変数とする重回帰分析を行うと、身体活動量の標準偏差が大きい(日ごとの活動量の差が大きい)ことが、負の独立した関連のある因子として特定された(t=-2.06、p=0.04)。また、食前30分間の心拍数の標準偏差も、負の独立した関連のある因子だった(t=-2.12、p=0.03)。反対に、独立した正の関連因子としては、食前90~60分の皮膚電気活動(交感神経活性)の標準偏差が特定された(t=1.97、p=0.049)。
食後の血糖降下速度と関連のある因子
次に、食後の血糖値が最も高い時点から、血糖値低下が終了した時点の血糖変動の幅を、その間の経過時間で除して、血糖降下の傾き(血糖低下速度を表す)を算出したうえで、重回帰分析で関連因子を検討した。
その結果、正の独立した関連のある因子として、身体活動量(t=2.67、p=0.008)、血糖低下中の心拍数(t=3.86、p<0.001)、食前90~60分の心拍数(t=2.27、p=0.02)が特定された。反対に、負の独立した関連のある因子として、添加糖の摂取量(t=-3.72、p<0.001)が特定された。
評価した各パラメーターの標準偏差を独立変数とする重回帰分析では、有意な関連因子は抽出されなかった。
食後血糖上昇速度が速い食事パターンはピークからの低下速度も速い
これらのほかに、炭水化物、タンパク質、食物繊維、添加糖、摂取エネルギー量のそれぞれの中央値で二分したうえで、どのような組み合わせが食後血糖上昇・低下速度と強い関連があるかという検討も行われた。
その結果、食後血糖上昇速度が最も緩やかなのは、タンパク質と食物繊維の摂取量は中央値を上回り、その他は中央値を下回るグループであって、上昇勾配の平均値は0.506 mg/dL/分だった。一方、食後血糖上昇速度が最も速いのは、炭水化物と添加糖の摂取量は中央値を上回り、その他は中央値を下回るグループであって、上昇勾配の平均値は1.675 mg/dL/分だった。
食後血糖ピークからの低下速度が最も緩やかなのは、タンパク質と摂取エネルギー量は中央値を上回り、その他は中央値を下回る食事であって、低下勾配の平均値は-0.408 mg/dL/分だった。一方、低下速度が最も速いのは、炭水化物と添加糖の摂取量は中央値を上回り、その他は中央値を下回る食事(食後血糖上昇速度が最も速いパターンと同じ)であって、低下勾配の平均値は-1.028 mg/dL/分だった。
著者らは、「ウェアラブルデバイスデータを用いることで、血糖値と生理・栄養指標の関係性を検討し得た。今後、ウェアラブルデバイスデータのオープンデータセットを容易に利用できるようになるに従い、さまざまな角度からの統計解析が可能となることで、この領域の知見の蓄積が進むと期待される」と述べている。
文献情報
原題のタイトルは、「Association of Blood Glucose Data With Physiological and Nutritional Data From Dietary Surveys and Wearable Devices: Database Analysis」。〔JMIR Diabetes. 2024 Dec 3:9:e62831〕
原文はこちら(JMIR Publications)









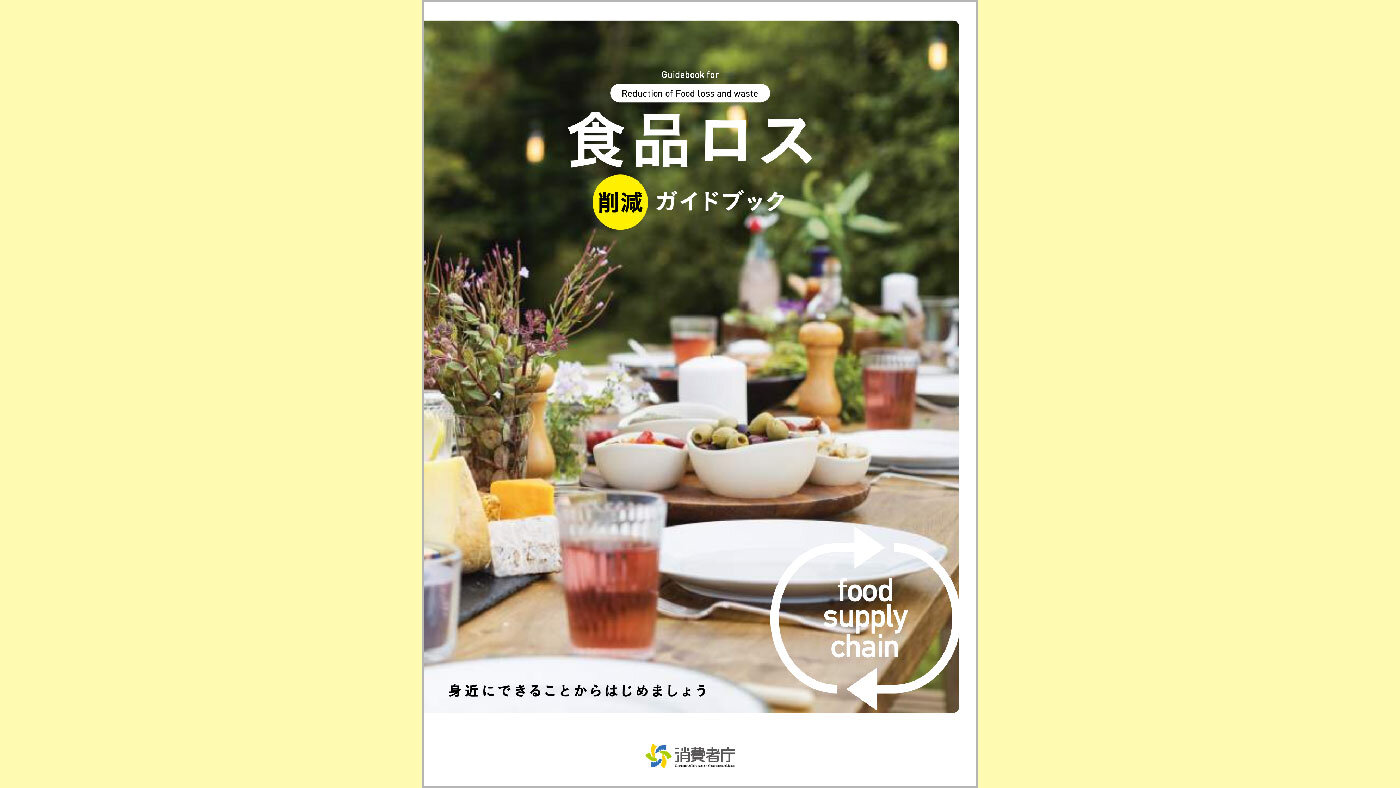













 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!








