日本人の身体活動量はどのように変化したか 2003~19年の国民健康・栄養調査のデータ解析
厚生労働省が毎年実施・公表している「国民健康・栄養調査」のデータ(政府統計の窓口「e-Stat」)を用いて、近年の日本人の身体活動量の変化を詳細に解析した結果が報告された。2003年以降に男女ともに1日あたりの平均歩数が減少してきていること、都道府県によって歩数の差(幅)が存在することなどが明らかにされている。医薬基盤・健康・栄養研究所 身体活動研究部の中潟崇氏、小野玲氏の研究によるもので、「Data in Brief」に論文が掲載された。

国民健康・栄養調査のデータを駆使して日本人の身体活動習慣を詳細に解析
国民健康・栄養調査は終戦の年の1945年に、海外からの食糧援助を受けるための基礎資料を得ることを主目的として開始され、以来、震災や新型コロナウイルス感染症パンデミックのために中止または実施自治体が縮小されたことはあるが、原則、毎年1回11月に継続的に行われてきている。国民健康・栄養調査は横断調査であるため、同一対象の食事・身体活動習慣の変化を縦断的に把握することはできないものの、定期的に繰り返される調査であることから、日本人の食事・身体活動習慣の全体的な経年変化を捉えることが可能。また、都道府県ごとに集計されているため、地域差を検討することもできる。
このように多面的な解析が可能な国民健康・栄養調査だが、これまでのところ、運動習慣、歩数計による歩数、座位行動などの身体活動関連データの経年的な推移や、それらが都道府県によって異なるのかといった点は十分検討されていなかった。中潟氏らは、2003年から2019年の国民健康・栄養調査のデータを用いて、性別、年代別の実態を明らかにした。同氏らは、「この解析結果は、2024年度に始まる『健康日本21(第三次)』推進のための基礎資料となり得る」としている。
性別、年齢層別の身体活動習慣が明らかに
解析した項目は、運動習慣の有無、歩数、座位行動という3項目。このうち運動習慣については、「1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している」場合に、「運動習慣あり」と定義されている。
女性は運動習慣のある割合が減少、男性は横ばい
2019年(令和元年)時点で20歳以上であり、運動習慣がある人の割合の年齢調整値は、男性が29.5%、女性は20.9%だった。2003年から2019年までの年齢調整値の変化は、男性は有意な変化がないものの女性は25~26%だった2010年前後から顕著に減少していた。
年齢層別にみると、20〜59歳は性別にかかわらず、運動習慣のある人の割合が低く、60歳以上では比較的その割合が高かった。70歳以上は男女ともに2003年以降、増加傾向にあり、2019年では男性は42.7%、女性は35.9%と全世代で最も高かった。
なお、健康日本21(第三次)では、運動習慣のある人の割合を20~64歳で30%、65歳以上では50%とする目標を掲げている。
歩数計で調査した歩数は男女ともに減少し、女性はより大きく減少
2019年の平均歩数は男性が7,162歩、女性は6,105歩(どちらも年齢調整値)だった。2003年以降、男性の歩数は7,465歩から徐々に減少してきており、女性は6,757歩から約650歩減少した。なお、健康日本21(第三次)では、20~64歳は8,000歩、65歳以上は6,000歩を目標としている。
都道府県の比較を行うため、2012年と2016年の国民健康・栄養調査は調査地区を拡大して実施され、歩数を都道府県別にみると、男女ともに首都圏、愛知県、大阪府などの大都市圏は他の地域よりも歩数が総じて多いという傾向が認められた。
座位行動は男性のほうが長い傾向
座位行動時間については、解析対象期間では2006年、2013年、2017年の3回調査されている(2006年と2013年は同じ質問票で平日と休日をそれぞれを連続変数で回答し、2017年は2006年・2013年と異なる質問票で、平日と休日の区別をせず、「3時間未満」、「3-8時間」、「8時間以上」の選択肢から1つ選択)。全体的に、女性よりも男性のほうが座位行動時間が長い傾向にあった。
例えば2006年の調査で平日の座位行動時間が8時間を超える人の割合は、全体で35.2%、性別では男性が37.3%、女性は33.4%だった。また週末は同順に、37.1%、40.9%、33.8%だった。2013年の調査では全体で35.2%、性別では男性が38.1%、女性は32.8%であり、やはり男性のほうが多かった。さらに、週末については同順に、39.0%、42.8%、35.7%であり、性別での比較でより大きな差が認められた。
2017年の調査では、8時間以上の選択肢を回答した割合は全体で11.9%、男性13.8%、女性10.3%だった。年齢層を加味した解析では、男性については20~59歳では8時間を超える人の割合が15.0%であるのに対して60代(10.3%)および70歳以上(12.3%)はその割合が低かった。女性では60代が5.5%と最も低く、その他の年齢層は10~12%だった。
著者らは、「2003年以降、男女ともに1日あたりの平均歩数は全体的に減少してきており、都道府県での比較では、歩数が少ない都道府県から歩数が多い都道府県まで歩数の幅が存在している。国民健康・栄養調査は横断研究であり、協力率やサンプルサイズといった限界はあるものの、研究者、臨床医、政策立案者はこれらの点を認識する必要があるだろう」と述べている。また「この結果は、身体活動・運動分野における健康政策の立案、推進を目指す上で、性別、年代、地域差に関する理解を深め、公衆衛生対策の基礎的な資料となり得る。さらに、健康日本21の目標達成のための重要な視座を提供するものでもある」としている。
なお、医薬基盤・健康・栄養研究所は、医薬基盤研究所(大阪府茨木市)と国立健康・栄養研究所(東京都新宿区)が平成27年に統合されて国立研究開発法人としてスタートを切り、2023年3月に著者らの所属する国立健康・栄養研究所が大阪府吹田市と摂津市にまたがる「北大阪健康医療都市」(健都)に移転した。小野氏らは大阪府摂津市が進める「健康・医療のまちづくり」の一環として、18歳以上の摂津市民を対象とした「大阪府摂津市民の健康・栄養とウェルビーイングに関する縦断調査(摂津スタディ)」を展開しており「北大阪健康医療都市(健都)から、生活習慣と健康課題をライフコース別に明らかにしたい」と述べている。
文献情報
原題のタイトルは、「Data resource profile: Exercise habits, step counts, and sedentary behavior from the National Health and Nutrition Survey in Japan」。〔Data Brief. 2024 Jan 24:53:110103〕
原文はこちら(Elsevier)










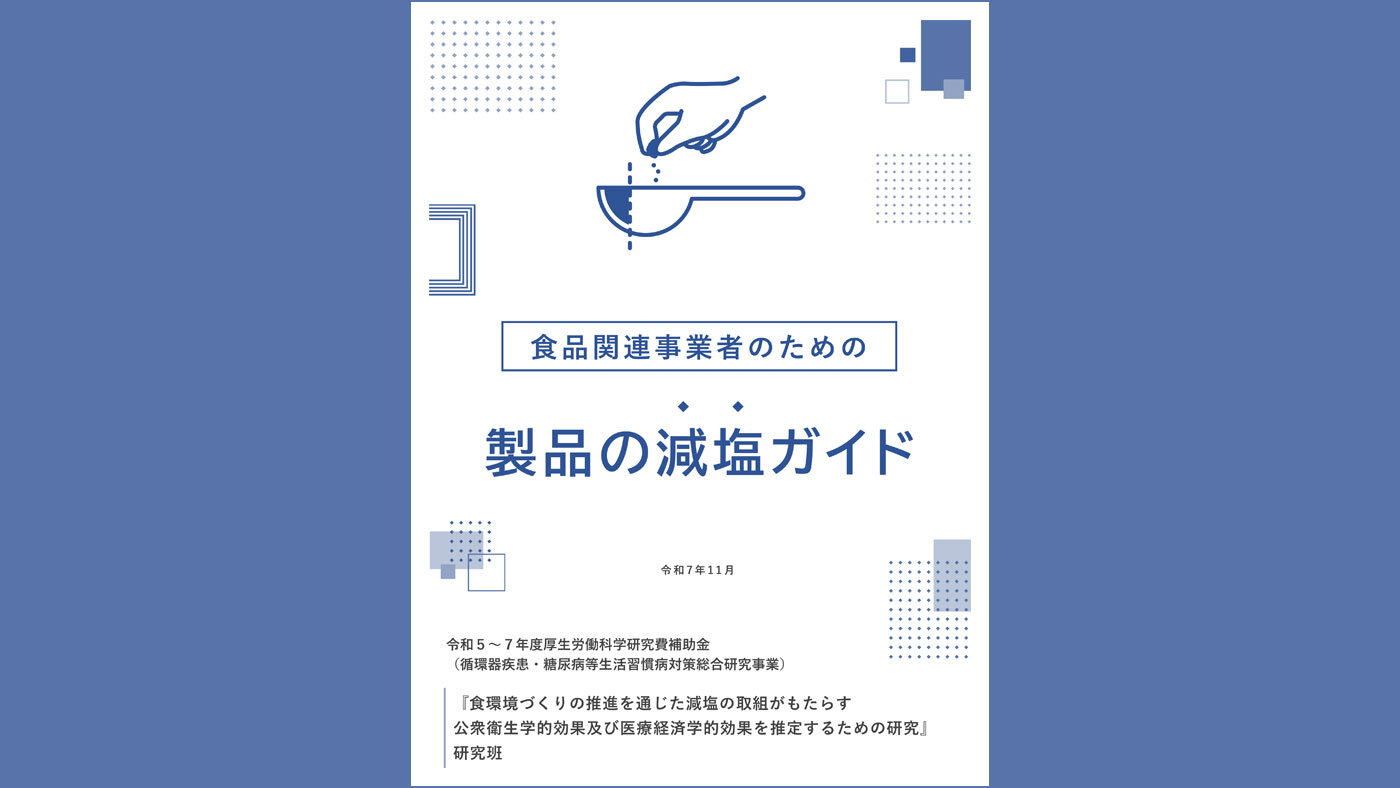












 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










