タンパク質摂取と咀嚼能力は、互いに独立してフレイルに関連
日本人高齢者を対象とする調査の結果、タンパク質摂取(タンパク質エネルギー比)が少ないことと、客観的に評価した咀嚼能力が低いことが、それぞれ独立してフレイルに関与していることが示された。東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野の濵洋平氏、岡田光純氏らの研究であり、「Nutrients」に論文が掲載された。消化管での栄養素吸収力低下も、フレイルリスク因子ではないかとの考察も加えられている。

フレイル関連因子としての咀嚼能力の低下と栄養素摂取量の不足を同時に評価した研究
高齢者人口の増大と若年者人口の減少が急速に進行中の日本では、実効性の高い介護予防対策の確立が喫緊の課題となっており、フレイル予防がその主眼と目されている。これまでの研究で、フレイルのリスク因子として、筋力の低下のほかに、栄養状態の悪化と咀嚼機能の低下の重要性が明らかにされてきている。栄養関連ではエネルギー量やタンパク質の不足に加えて、ビタミンD不足も筋力や骨代謝の低下、骨折リスク増大を介してフレイルリスクに関与することが指摘されている。
ただしこれまでのところ、それらの因子の関連を包括的に検討した研究は行われていないため、相互の関連性が不明である。これらの相互の関連性が明らかになれば、より効果的なフレイル予防対策の立案に結びつく可能性がある。
以上を背景として濵氏らは、東京医科歯科大学病院の歯科外来受診者を対象とする横断研究により、摂取エネルギー量、タンパク質摂取およびビタミンD摂取量、客観的・主観的咀嚼能力と、フレイルとの関連を検討した。
歯科外来の高齢患者約200人を対象に横断的な解析
研究対象は、2022年1月からの1年間に同院歯科外来へ歯のメンテナンスのために受診した患者から募集された、65歳以上の患者200人。要支援・要介護者、歯科治療継続中の患者、認知症またはその疑いのある患者、食事制限を必要とする疾患罹患者、脳梗塞や整形外科的疾患などのフレイルリスクに影響を及ぼし得る疾患既往者を除外し182人を解析対象とした。
各評価指標について
フレイルの判定
フレイルは日本語版フレイル基準(Japanese version of the Cardiovascular Health Study criteria〈J-CHS基準〉)を用いて判定した。体重減少、主観的疲労感、日常生活活動量の減少、身体能力(歩行速度)の減弱、筋力(握力)の低下という5項目のうち1項目のみが該当する場合をプレフレイル、2項目以上が該当する場合をフレイルと判定。本研究ではそれら両者を「フレイル群」と定義したうえで、後述の統計解析を行った。
咀嚼能力
咀嚼能力の客観的評価には、グミゼリー2gを20秒間咀嚼後に10mLの水で含嗽し、濾過紙に排出してもらい、グミからのグルコース溶出濃度を測定するという手法を用いた。この手法では吐き出した水のグルコース濃度が高いほど、咀嚼能力が高いと判定する。
主観的な評価には、フレイル健診に用いられている「基本チェックリスト」の中の「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」を利用。この質問に「はい」と回答した場合に咀嚼能力の低下ありと判定した。
栄養状態
栄養状態の評価には簡易型自記式食事歴質問票(brief-type self-administered diet history questionnaire;BDHQ)を用い、摂取エネルギー量、タンパク質摂取のエネルギー比、ビタミンD摂取量を把握した。
解析対象者のおもな特徴
解析対象者は、年齢が中央値74.0歳、女性が57.1%、独居者81.9%であり、骨格筋量指数(skeletal muscle mass index;SMI)は6.3kg/m2だった。
栄養関連の指標は、摂取エネルギー量が中央値1,818.0kcal/日、タンパク質エネルギー比は平均17.3%、ビタミンDは中央値17.0μg/日。客観的な咀嚼能力(グミ咀嚼・含嗽後の吐き出し液中のグルコース濃度)は160.5mg/dL、主観的な咀嚼能力は良好が85.7%だった。
J-CHS基準に基づき、89人(48.9%)がフレイル群と定義された。その内訳は、プレフレイルが83人、フレイルが6人だった。
咀嚼能力の低下が栄養状態の良否にかかわりなく、フレイルに関与
フレイル群と非フレイル群を比較すると、年齢や性別の分布、SMI、および摂取エネルギー量には有意差が観察されなかった。
その一方で、タンパク質エネルギー比(18.0 vs 16.6%エネルギー、p=0.003)、ビタミンD摂取量(19.1 vs 13.6μg/日、p=0.006)はいずれもフレイル群のほうが少なかった。また、咀嚼能力にも以下のような有意差が認められ、フレイル群のほうが低下していた。客観的指標は171.0 vs 150.0mg/dL(p=0.005)、主観的指標は良好の割合が91.4 vs 79.8%(p=0.02)。
タンパク質摂取と客観的咀嚼能力が、フレイルの独立した関連因子
次に、年齢、性別、独居/同居、SMI、摂取エネルギー量、タンパク質エネルギー比、ビタミンD摂取量、客観的咀嚼能力、主観的咀嚼能力を独立変数、フレイル群であることを従属変数とするロジスティック回帰分析を施行。その結果、筋肉量の多寡の指標であるSMI(OR2.50〈95%CI;1.07~5.88〉)のほかに、タンパク質エネルギー比(OR2.47〈1.10~5.55〉)、客観的咀嚼能力(OR2.06〈1.07~3.97〉)が、フレイルに独立した関連のある因子として抽出され、これらの因子がそれぞれ異なる経路でフレイルリスクに関与していると考えられた。
摂取した栄養素の吸収力の低下もフレイルリスクの一因?
以上に基づき論文の結論は、「簡易型自記式食事歴質問票(BDHQ)を使用して評価したエネルギー、タンパク質、ビタミンDなどの栄養素の摂取とは独立して、咀嚼能力がフレイルと関連していることが明らかになった」と総括されている。なお、著者らは本研究に先立ち、「咀嚼能力の低下が栄養素摂取量の減少を介してフレイルに関連する」との仮説を立てていたという。しかし結果は上記のように、それら両者は互いに独立してフレイルに関与していた。この点について、論文中には以下のような考察が述べられている。
本研究ではBDHQにより栄養素摂取量を評価したが、摂取された栄養素がどの程度吸収され生体内で利用されたかは評価していない。既報研究によると、摂取栄養素の吸収に関連する因子の一つとして、咀嚼能力が挙げられている。よって、咀嚼能力が低下している場合、摂取した時点の栄養素量は充足していたとしても、それが十分に吸収されず、フレイルリスクを高める可能性が考えられるとのことだ。
ただし本研究は生体内での栄養素の分布を評価し得る、例えば血液検査などを実施していないため、この点についてはさらなる研究が必要としている。また、この点以外に本研究は横断研究であり因果関係の解釈が制限されること、フレイルの社会的側面に焦点を当てていないこと、対象が大学の附属病院に通院中の患者であり、健康意識が比較的高いと考えられる集団という選択バイアスが存在する可能性などの限界点を挙げている。
文献情報
原題のタイトルは、「Association between Masticatory Performance, Nutritional Intake, and Frailty in Japanese Older Adults」。〔Nutrients. 2023 Dec 12;15(24):5075〕
原文はこちら(MDPI)

















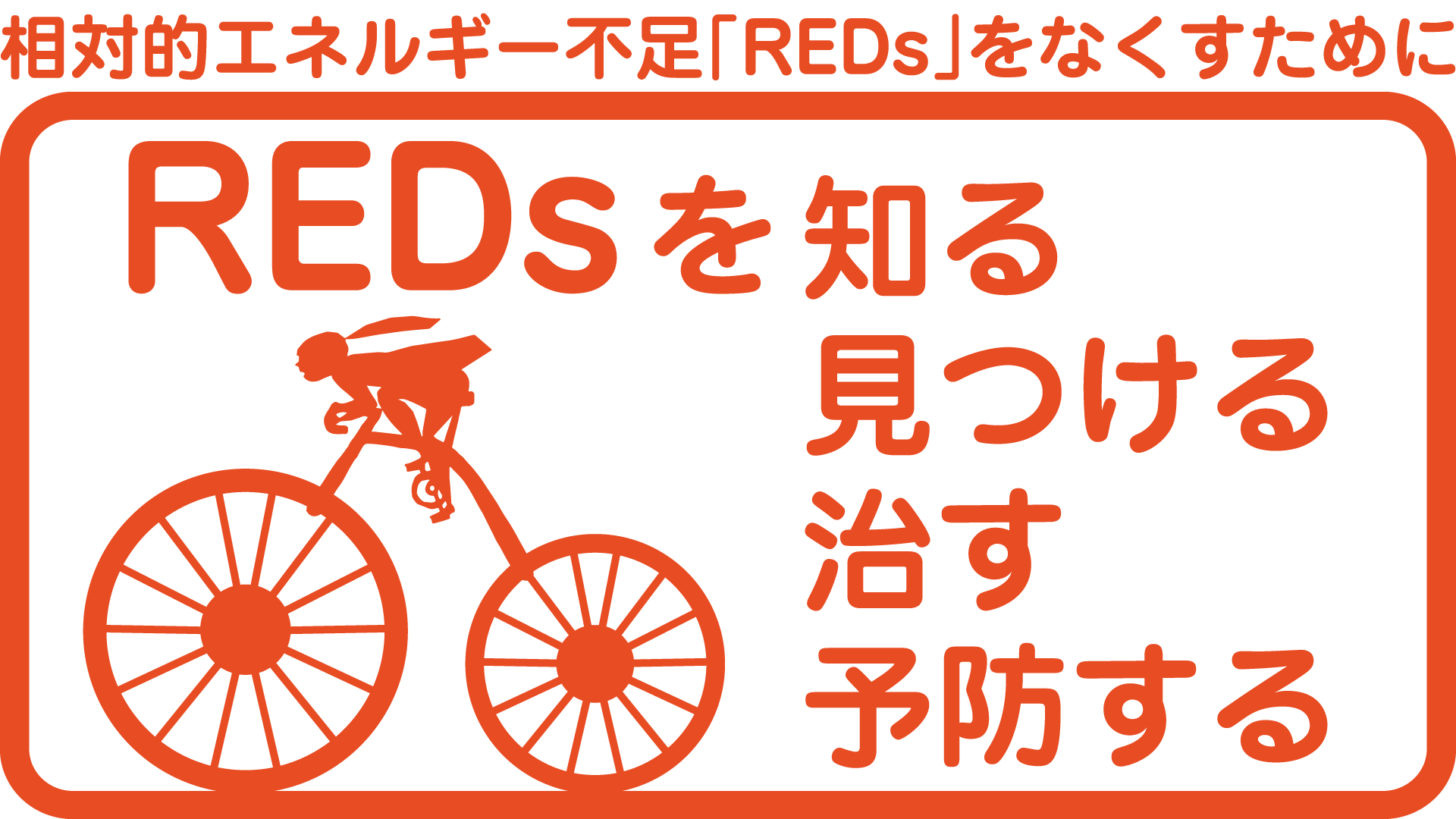





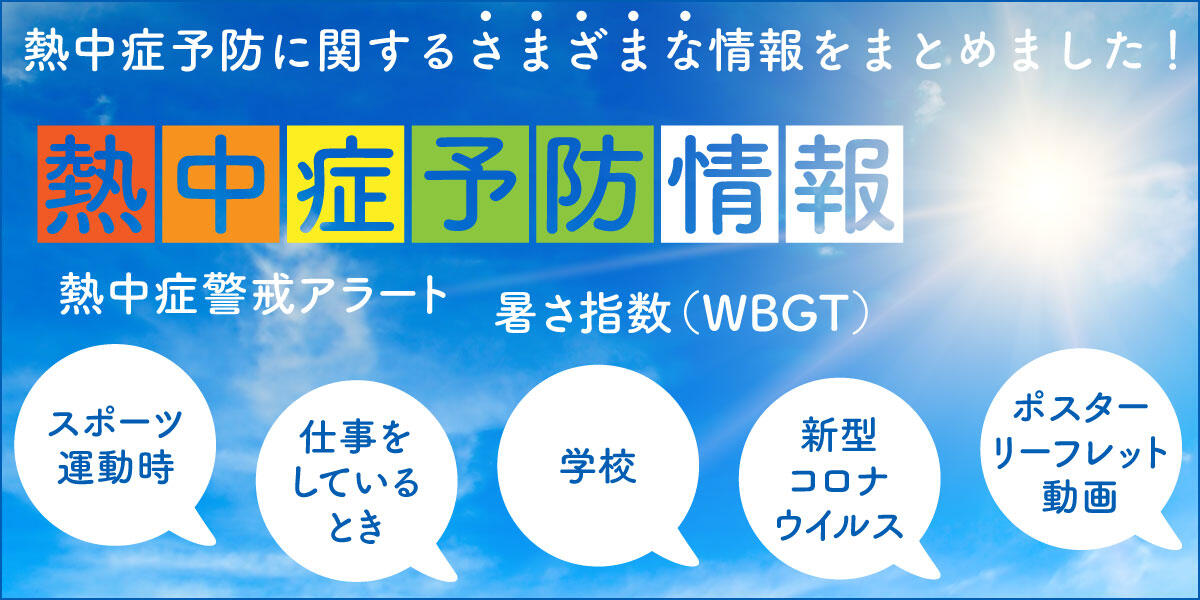 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!











