子どもと親に対する2年間の食事・運動介入で、子どもの認知機能にどのような影響が現れる?
6~9歳の子どもとその親に対して、食事や運動に関する介入を2年間断続的に行い、子どもの認知機能にどのような影響が現れるかを、非ランダム化比較試験で検討した結果が、フィンランドから報告された。子どもたちの食事や運動の習慣は、介入の有無にかかわらず変化する可能性もあることから、実際の食事・運動習慣と認知機能との関連も検討され、興味深い結果が示されている。

観察研究ではなく、介入研究で子どもの認知機能への影響を証明できるか?
多くの子どもは、飽和脂肪酸やスクロースの摂取量が多くて野菜の摂取量が少ない。また近年は屋外で遊ぶ頻度が減り、屋内でゲームなどをして時間を過ごす子どもたちが増えている。このような傾向は日本に限らず世界中でみられるようで、この研究が行われたフィンランドでも同じようだ。
過去の観察研究では、野菜や果物、魚、未精製穀物などの摂取量が多く、食事の質が高い子どもは学業成績や認知機能が高いという正相関が示されている。また、今回紹介する論文の著者らは以前、子どもたちの身体活動や食事の質が認知機能に影響を与える潜在的な可能性を報告している。ただし、子どもたちに対する食事・運動に「介入」を行うことが、認知機能に影響を及ぼし得るかを、長期間追跡して検討した研究結果は存在しない。
これを背景として著者らは、フィンランドのクオピオ市で行われている小児の身体活動と栄養に関する研究(Physical Activity and Nutrition in Children;PANIC)のデータを用いた解析を行った。
6~9歳の小学生とその親に2年間介入し、認知機能を非介入群と比較
PANIC研究はクオピオ市内の小学校に通う6~9歳の子ども736人に参加協力を依頼し、512人が参加。参加者の小学校入学時点の健康状態は、同国の全小学校生徒の入学時健診のデータと同等だった。
障害のある子どもと研究参加同意を撤回した子どもを除外した504人を、介入群306人と非介入群(対照群)198人に分類。介入群には後述の方法により身体活動の増加と食事の質向上を指導。介入前のベースライン時点と介入2年後の認知機能の変化を比較検討した。2年後の解析対象は追跡期間中の脱落により、435人(介入群259人、対照群176人)となった。
介入方法
介入群に対しては、2年の間に子どもとその親に対して、臨床栄養士による食事カウンセリングを6回、運動医学の専門家による身体活動指導が6回行われた。各セッションは30~45分だった。身体活動介入については、座位行動を減らす工夫についての口頭や書面での指導に加えて、クオピオ市内で運動に参加できる機会の情報提供、スポーツ器具の支給、スポーツ施設への入場料の支援、および学校の放課後の運動クラブ活動への参加奨励なども行った。
認知機能の評価方法
認知機能の評価は、知識や言語スキルに依存しないRCPM(Raven's Colored Progressive Matrices)という指標を用いた。RCPMは12項目からなる3セットの課題が示され、被検者は正しいアイテムを選択する。スコアは0~36点の間で表され、スコアが高いほど認知機能が高いと評価する。
栄養素摂取量と食事の質の評価方法
4日間の食事記録を用いて、栄養素摂取量を把握するとともに、バルト海食事スコア(Baltic Sea Diet Score;BSDS)という指標を用いて食事の質を評価した。BSDSは、果物、野菜・ベーリー、高繊維穀物、低脂肪乳、魚の摂取量などはプラス評価、赤身肉や加工肉、脂質エネルギー比や飽和脂肪酸摂取量などはマイナスに評価する仕組みで、合計スコアは0~18点の間で表され、スコアが高いほど食事の質が高いと評価する。
身体活動・座位行動の評価方法
ウェアラブルモニターを支給し、被検者個々の心拍数に基づき校正。ベースライン時と2年間の追跡終了時の各4日間連続で、座位行動、軽強度・中等度・高強度運動の運動量を計測した。また、保護者対象のアンケートにより、子どもの身体活動時間と座位行動時間を把握した。
介入の割付で比較すると非有意ながら、実際の食事の質との関連は有意という結果
介入群と対照群の比較
ベースライン時点の比較
では結果だが、まずベースライン時点の両群の子どもたちの特徴を比較すると、年齢、性別(男児の割合)、BMI、思春期発来後の子どもの割合、親の教育歴、摂取エネルギー量、食事の質(BSDSスコア)、総身体活動時間、座位行動時間、および認知機能(RCPMスコア)に有意差はなかった。ただし、世帯収入は介入群のほうが有意に高かった。
2年追跡後の比較
続いて2年間追跡した後の子どもたちを比較すると、年齢、性別(男児の割合)などに有意差がないことは当然ながら、BMI、思春期発来後の子どもの割合、摂取エネルギー量も有意差が生じていなかった。世帯収入の有意差はベースライン同様に認められた。
一方、食事の質を表すBSDSスコアは介入群のほうが有意に高くなっていた(13.8±3.7 vs 11.5±4.1、p=0.002)。また、総身体活動時間も介入群のほうが有意に長くなっていた(122.4±41.6 vs 103.5±41.6分/日、p<0.001)。
肝心の認知機能を表すRCPMスコアは、ベースライン時には介入群23.9±5.3、対照群23.8±4.9点(p=0.998)であったものが、2年後には同順に29.1±3.7、28.9±3.8点で(p=0.675)、両群ともに上昇して有意な群間差は生じていなかった。
介入割付を無視した、食事の質や身体活動と認知機能の全体での関連
次に、介入群と対照群を分けずに被検者全体を対象として、食事の質や身体活動と認知機能との関連が検討された。
食事の質は認知機能と有意に関連
解析の結果、食事の質を表すBSDSスコアは、認知機能を表すRCPMスコアと有意な正の関連が認められた(β=0.097、p=0.026)。詳細に検討すると、赤身肉とソーセージの摂取量は認知機能と負の関連があり(β=-0.009、p=0.004)、低脂肪乳の摂取量は正の関連が認められた(β=0.001、p=0.019)。
一部の身体活動が認知機能と有意に関連
身体活動については、総身体活動時間は認知機能と有意な関連がなかった。ただし、詳細な検討からは、組織化されたスポーツへの参加は認知機能と有意な正の相関があり(β=0.032、p=0.010)、反対に、親が把握していない身体活動は認知機能と有意な負の関連が認められた(β=-0.010、p=0.010)。
これら一連の結果に基づき著者らは、「結論として、強力な構造化された食事・運動介入でない限り、子どもの認知機能を有意に向上させることはできないようだ。ただし、食事の質の改善、低脂肪乳の摂取量の増加、組織的なスポーツへの参加などは、子どもの認知機能向上と関連があった」とまとめている。
文献情報
原題のタイトルは、「Effects of 2-year dietary and physical activity intervention on cognition in children—a nonrandomized controlled trial」。〔Scand J Med Sci Sports. 2023 Aug 9〕
原文はこちら(John Wiley & Sons)
















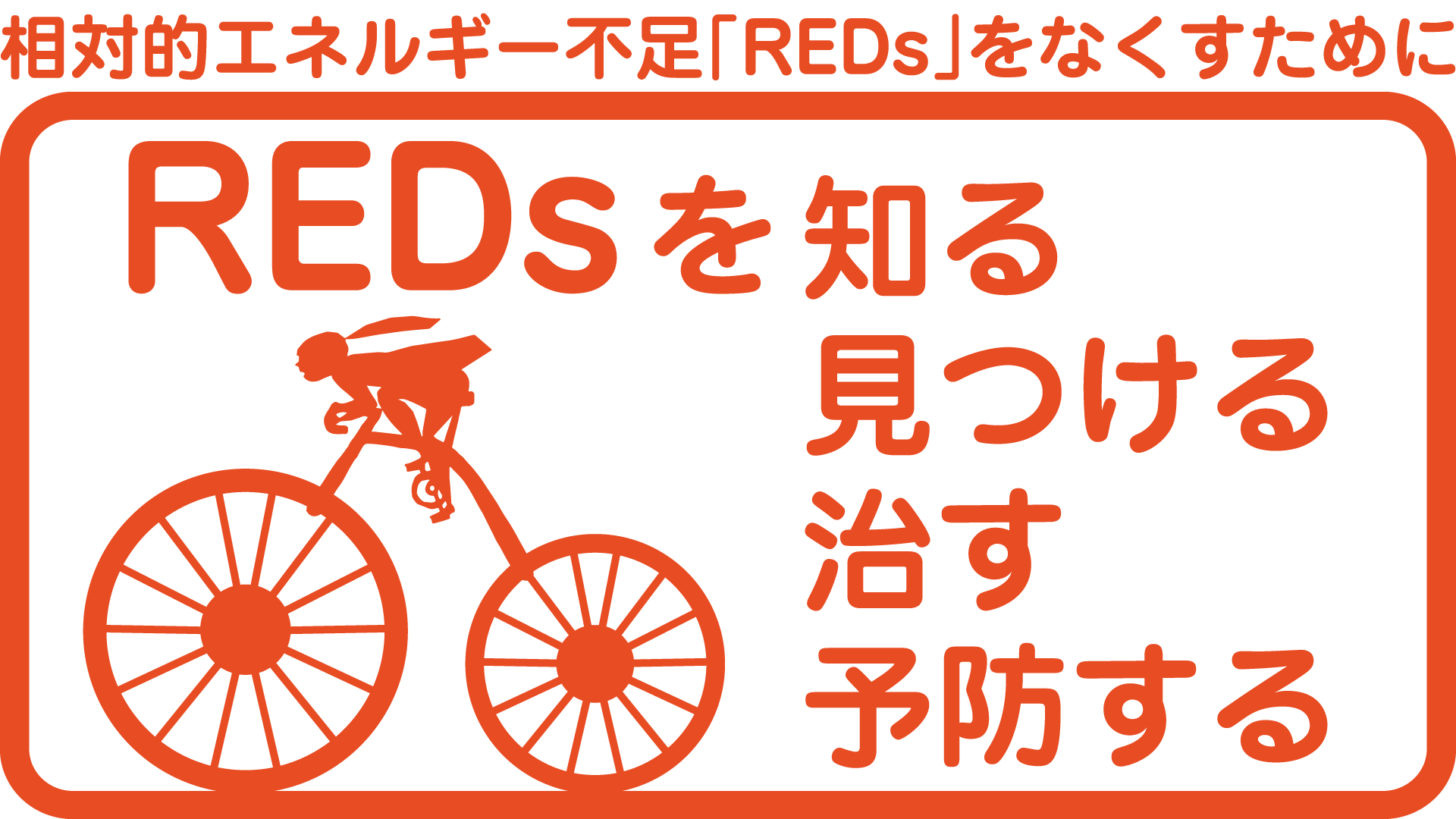





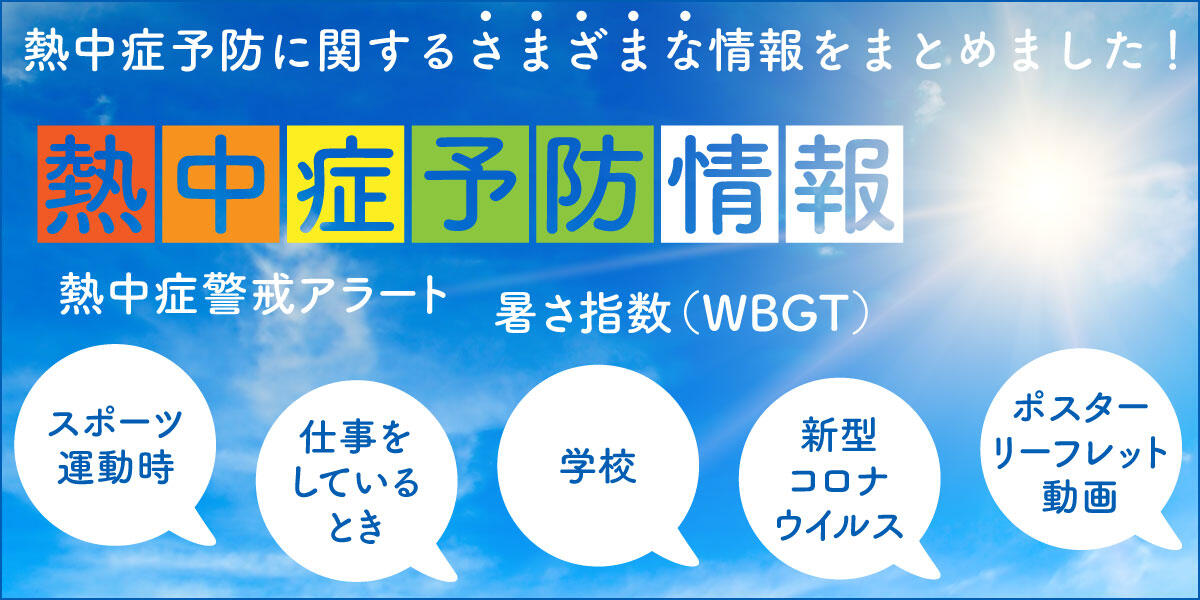 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!











