ジロイシンがロイシン以上に筋トレ効果を高める可能性 男性対象10週のRCTで一部の指標に有意差
筋タンパク質合成刺激作用のある必須アミノ酸のロイシンが2個つながったジペプチドである「ジロイシン」が、ロイシン以上に筋トレ効果を高める可能性を示唆する研究結果を紹介する。米国の研究者によって行われた、日常的に筋トレを行っている男性対象の二重盲検比較試験の結果であり、昨年末に「PLOS One」に報告された。

ジロイシンはロイシンの効果を上回る?
必須アミノ酸の一つであるロイシン(leucine)は、筋タンパク質合成(muscle protein synthesis;MPS)刺激作用を持つことから、筋量や筋力を高めるためのサプリメントとして広く利用されている。一方、近年、食品中のペプチド(ジペブチドやトリペブチド)の研究が進み、ロイシンが2個つながったジペプチドである「ジロイシン(dileucine)」に関する理解も深化して、体内への吸収率がロイシンを上回り、筋肉へより速く到達する可能性が示唆されてきている。とはいえ未だ基礎研究が多くを占めており、実際にヒトがジロイシンを摂取した場合にロイシン以上の効果が発揮されるのかどうかは明らかでなかった。
ふだん筋トレを行っている男性を3群に分け10週間介入して比較
今回紹介する論文の研究は、日常的に筋力トレーニングを行っている男性を3群に分け、ロイシン、ジロイシン、およびプラセボのいずれかを摂取してもらい、10週間での筋力関連指標の変化を比較するという、二重盲検並行群間比較試験として実施された。事前の統計学的検討により、このトピックの有意差を検証するたに必要とされるサンプルサイズは24~33人と計算された。
研究参加者の募集に対して587人の男性が応募。適格条件は、自己申告に基づくBMI25未満、体脂肪率25%以下、過去1年以上の筋トレ継続、ベンチプレスでの最大挙上重量が体重の1.0倍以上、レッグプレスでは同1.5倍以上、過去1年以内にアナボリックステロイドを摂取していないこと――を満たし、かつ研究手法の説明後にも参加に同意したのが113人で、このうち57人が研究に参加した。
この57人を、除脂肪体重に群間差が生じないように考慮のうえ無作為に3群に分類。ロイシン、ジロイシン、プラセボのいずれかを毎日2g、10週間にわたり摂取してもらった。摂取タイミングは、筋トレ実施日は筋トレ後60分以内、休息日は朝食時とした。また、研究参加の30日前からは、マルチビタミン/ミネラル以外のサプリメント(例えばクレアチン、β-アラニン)の摂取を禁止した。
介入期間中は標準化されたプロトコルで筋トレ(週に上半身と下半身を各2回で計40回)を継続。また、食事に関してはエネルギー量を30kcal/kg以上、タンパク質1.5g/kg以上として、食事記録に基づき遵守状況を確認。遵守率が90%未満だった参加者は、解析から除外された。
評価項目は、体組成、レッグプレスおよびベンチプレスの1回最大挙上重量(one repetition maximum;1RM)、1RMの80%の負荷で挙上不能になるまでの回数(repetitions to failure;RTF.筋持久力)、下肢筋力指標としてのカウンタームーブメントジャンプ(countermovement jump test;CMJ)などで、8時間の絶食、および、24時間前からのカフェイン・アルコール・ニコチン摂取、運動を禁止した状態で評価した。
ジロイシンは下半身の筋力や筋持久力をロイシン以上に向上させるという結果
10週間の介入を終了した参加者は34人だった。年齢は28.3±5.9歳、BMI25.5±3.7、体脂肪率19.1%で、サプリ(ジロイシン、ロイシンまたはプラセボ)の摂取と筋トレの遵守率は97.6%だった。介入前(ベースライン時点)において3群間に、年齢、BMI、体脂肪率、レッグプレスおよびベンチプレス1RMはいずれも有意差がなかった。また、介入期間中の摂取エネルギー量、主要栄養素バランスにも有意差はなかった。
レッグプレスの1RMとRTFの変化に有意な群間差
体重や除脂肪体重、および大腿中央部の筋厚は、3群ともに介入期間中に増加するという、有意な時間効果が認められた。ただし、変化量の群間差は非有意だった。一方、筋力や筋持久力の指標の一部に、以下のような有意な群間差が観察された。
レッグプレスの1RM
レッグプレスの1回最大挙上重量(1RM)は各群で以下のように変化していた。ロイシン群は介入前が290±67kgで介入後は335±62kg、ジロイシン群は同順に263±75kg、324±78kg、プラセボ群は286±74kg、307±86kg。
介入前後の変化量を群間で比較すると、ロイシン群とプラセボ群(p=0.23)、および、ロイシン群とジロイシン群(p=0.48)は有意差がなかったが、ジロイシン群とプラセボ群の比較では前者の変化量のほうが有意に大きかった(95%CI;5.8~73.2kg、p=0.02)。
レッグプレスのRTF
レッグプレスの筋持久力(RTF)は各群で以下のように変化していた。ロイシン群は13±5回から18±5回、ジロイシン群は13±4回から28±8回、プラセボ群は14±8回から24±11回。
介入前後の変化量を群間で比較すると、ロイシン群とプラセボ群(p=0.47)、および、ジロイシン群とプラセボ群(p=0.32)は有意差がなかったが、ジロイシン群とロイシン群の比較では前者の変化量のほうが有意に大きかった(95%CI;0.58~20.3回、p=0.04)。
以上を基に著者は、「1日2gのジロイシンサプリメントは、レジスタンストレーニングを行っている男性において、ロイシンやプラセボよりも下半身の筋力と筋持久力の向上という点で効果的だった。この結果は、ジロイシンがレジスタンストレーニングへの適応を改善する効果的なサプリメントとなる可能性を示唆している」と述べている。
なお、一部の著者が、ジロイシンに関する特許を出願中であることや、本研究の研究資金提供企業との利益相反(COI)に関する情報を開示している。
文献情報
原題のタイトルは、「Dileucine ingestion, but not leucine, increases lower body strength and performance following resistance training: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial」。〔PLoS One. 2024 Dec 31;19(12):e0312997.〕
原文はこちら(PLOS)













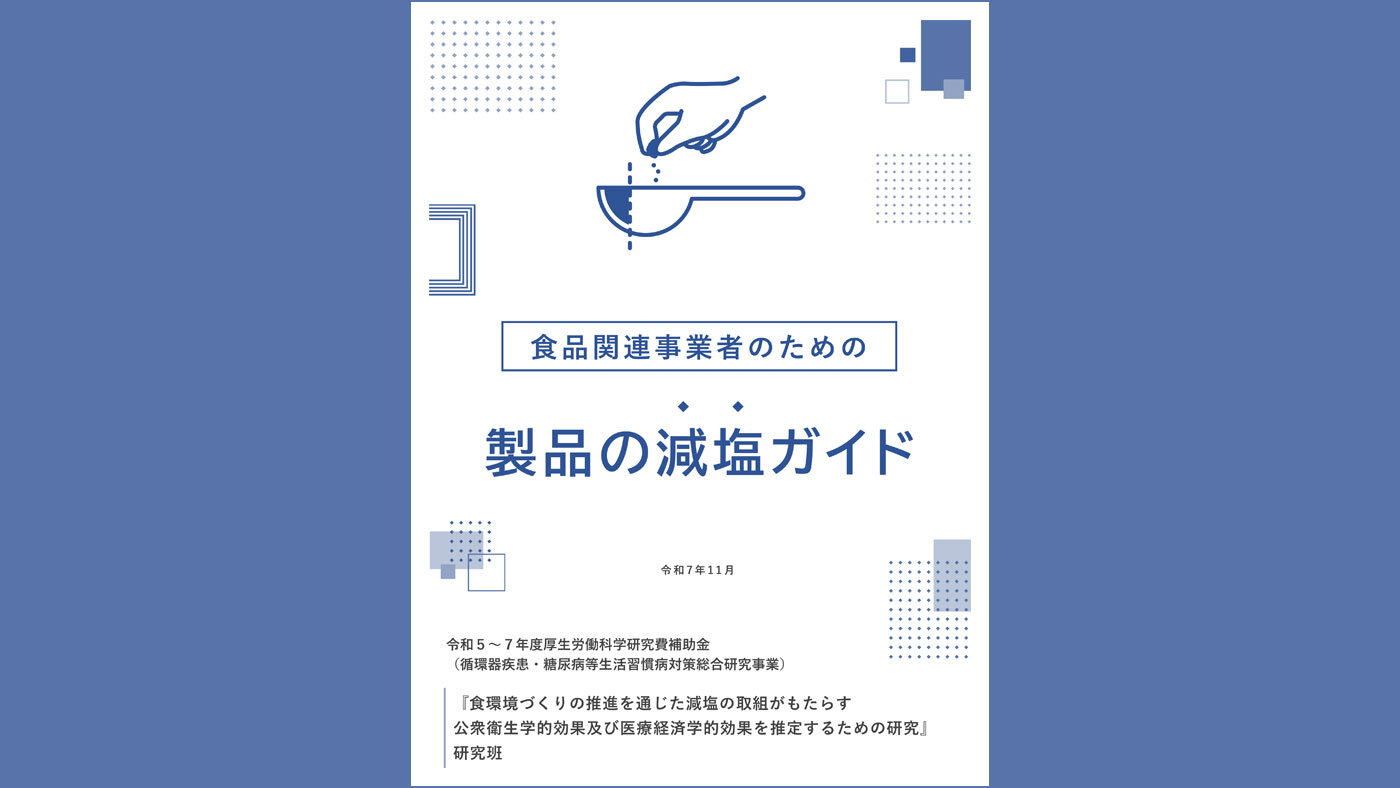









 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










