低炭水化物ダイエットで痛風リスク上昇、ただしタンパク質・脂質を植物性食品から摂ればリスク抑制
低炭水化物ダイエットによって、痛風ハイリスク状態である「高尿酸血症」になりやすくなること、ただし、減らした炭水化物のエネルギーを植物性食品で代替すれば、リスクは上がらない可能性があることが報告された。また、このような関係は、BMIが23.5以上の場合に有意であって、23.5未満の集団では有意でないという。日本と同様に米を主食とし、食習慣が類似している韓国の国民健康栄養調査のデータを解析した研究。

低炭水化物ダイエットで減量すると、尿酸値は下がるのか、上がるのか?
近年、炭水化物の摂取を減らし、その分のエネルギー量をタンパク質または脂質で補うという、低炭水化物ダイエットが流行している。現時点で長期的アウトカムへの影響は不明確だが、短期的には減量や糖代謝改善というメリットを期待し得るとする一定のエビデンスもある。体重管理のために低炭水化物ダイエットを試みる人は少なくない。
一方、体重管理が必要な過体重・肥満者に多い疾患の一つとして、高尿酸血症やそれに基づく痛風が挙げられる。尿酸値を下げ痛風リスクを抑制するという点で、減量が重要であることは間違いないが、減量のために低炭水化物ダイエットを行った場合、タンパク質や脂質の摂取を増やすことになり、食事に注意しなければ動物性食品の摂取が増えやすい。動物性食品は一般的にプリン体を多く含んでいるため、尿酸値を高めるように働く。このため、低炭水化物ダイエットによって、かえって尿酸値が上がり痛風を惹起してしまう可能性も考えられる。
ただし、これまでのところ、一般生活者においてこれらの関係がどのようになっているのかは明らかにされていない。そこで今回紹介する論文の著者らは、韓国の国民健康栄養調査(Korea National Health and Nutrition Examination Survey;KNHANES)のデータを用いた解析を行った。
韓国国民健康栄養調査3万4千人のデータを解析
2016~22年のKNHANESの参加者4万3,900人から、19歳未満、妊娠中・授乳中、解析に必要なデータの欠落、摂取エネルギー量が極端(500kcal/日未満または5,000kcal/日超)などの該当者を除外した3万3,960人を解析対象とした。
24時間思い出し法により栄養素摂取量を推定し、低炭水化物食スコア(low-carbohydrate diet score;LCDS)を算出。LCDSは、0~30点でスコア化され、スコアが高いほど低炭水化物ダイエットらしい食生活であることを意味する。本研究では、食事全体で評価した総LCDSのほかに、動物性食品由来または植物性食品由来のタンパク質と脂質の摂取量に基づき、動物性LCDS、植物性LCDSというスコアも算出した。
なお、高尿酸血症は、男性は血清尿酸値7.0mg/dL超、女性は6.0mg/dL超と定義した。
低炭水化物食スコアが高い人ほど高尿酸血症が多いが、植物性食品の多さは反対に作用
総LCDSの五分位数を基に全体を5群に分類すると、上位五分位群(より低炭水化物ダイエットらしい食生活の人)は、若年者、男性、喫煙者、習慣的飲酒者が多く、所得が高く教育歴が長い傾向があった。尿酸値は第1五分位群(最も低炭水化物ダイエットらしくない食生活である下位20%の集団)は平均5.0mg/dLで、第2五分位群は5.2mg/dL、第3および第4五分位群は5.3mg/dL、第5五分位群(最も低炭水化物ダイエットらしい食生活である上位20%の集団)は5.4mg/dLだった。
交絡因子(年齢、性別、喫煙・飲酒・運動習慣、摂取エネルギー量、野菜・果物の摂取量、eGFR、高血圧・糖尿病・脂質異常症、収入、教育歴)を調整し、総LCDSの第1五分位群を基準として高尿酸血症の該当者数を比較すると、第2~第5五分位群はすべてオッズ比が有意に高く(例えば第5五分位群はOR1.41〈95%CI;1.22~1.63〉)、総LCDSが高いほど高尿酸血症の該当者が多いという有意な関連が認められた(傾向性p<0.001)。
植物性食品由来のタンパク質と脂質の摂取量で比較した場合は関連が非有意
動物性食品由来のタンパク質と脂質の摂取量に基づく指標である、動物性LCDSの五分位数で分けた解析では、第3~第5五分位群はオッズ比が有意に高く(第5五分位群はOR1.28〈1.12~1.47〉)、動物性LCDSが高いほど高尿酸血症の該当者が多いという有意な関連が認められた(傾向性p<0.001)。
それに対して、植物性食品由来のタンパク質と脂質の摂取量に基づく指標である、植物性LCDSの五分位数で分けた解析では、第2~第5五分位群がすべて第1五分位群と有意差がなく(第5五分位群でもOR1.00〈0.87~1.16〉)、植物性LCDSと高尿酸血症との関連は非有意だった(傾向性p=0.75)。
植物性食品由来のタンパク質が多いと高尿酸血症リスクが低い傾向
次に、摂取エネルギー量に占める脂質およびタンパク質の割合(パーセントエネルギー〈%E〉)の五分位数で5群に分けた解析を実施。その結果、総脂質(傾向性p=0.12)、植物性脂質(同0.93)、総タンパク質(0.22)、動物性タンパク質(0.50)については、高尿酸血症リスクとの関連が見られなかった。
一方、動物性脂質についてはその摂取割合が高いほど高尿酸血症の該当者が多いという有意な関連が認められた(傾向性p=0.03)。その反対に、植物性タンパク質については、有意水準未満ながら、その摂取割合が高いほど高尿酸血症の該当者が「少ない」という傾向が認められた(同0.07)。
BMI23.5未満/以上に層別化すると、23.5以上の集団で全体解析と同じ結果
続いて、BMI23.5未満/以上に層別化した解析を施行した。
BMI23.5未満の集団では6.4%が高尿酸血症であり、総LCDS、動物性LCDS、植物性LCDSのいずれについても、高尿酸血症リスクとの関連が非有意だった。一方、BMI23.5以上の集団では19.0%が高尿酸血症であり、全体解析と同様に、総LCDSと動物性LCDSに関してはスコアが高い群ほど高尿酸血症の該当者が多いという有意な関連があり、植物性LCDSについては関連が非有意だった。
著者らは、「低炭水化物ダイエットは肥満および心血管代謝疾患の管理において広く普及しているものの、尿酸値低下におけるその役割については依然として議論が続いている。低炭水化物ダイエットを行う際の食品源の構成が、高尿酸血症のリスクに影響を与えるかどうかを明らかにするために、さらなる大規模コホート研究が必要とされる」と述べている。
文献情報
原題のタイトルは、「Associations of low-carbohydrate diets patterns with the risk of hyperuricemia: a national representative cross-sectional study in Korea」。〔Nutr J
. 2025 Apr 12;24(1):59〕
原文はこちら(Springer Nature)









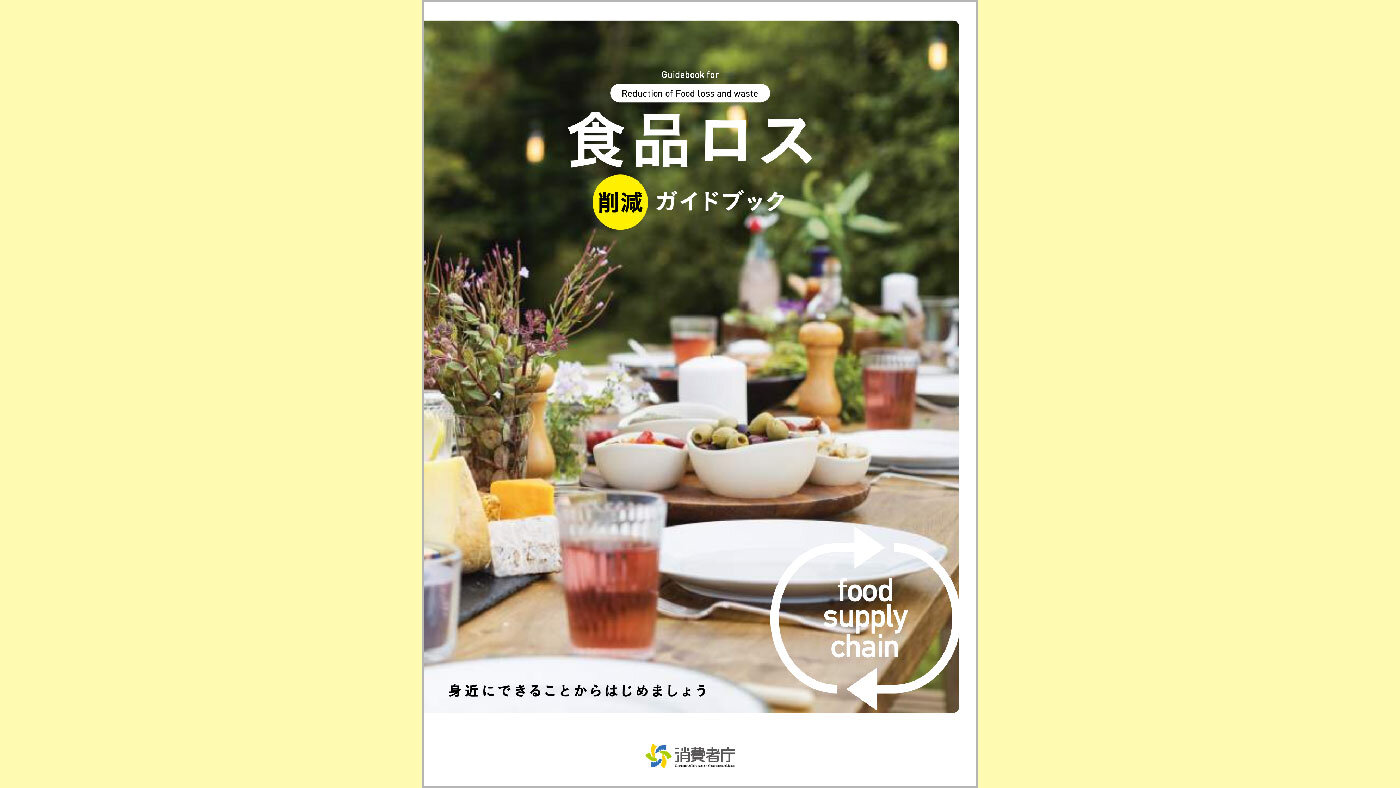













 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!








