大学医学部と中学校が連携した子どもたちの生活習慣改善への取り組み 実態調査と学校保健活動の事例の報告
大学と中学校が連携した学校保健活動の報告が、「日本公衆衛生雑誌」に掲載された。鳥取大学医学部環境予防医学分野の桑原祐樹氏らによる論文であり、中学生のデジタル機器の利用状況の実態や、抑うつレベルと食生活・運動習慣との有意な関連を示した調査結果も示されている。

医学生が主体的に参画して続けられている、松江市内の中学生に対する保健活動
成人後、とくに中高年以降に罹患率が上昇する生活習慣病のリスクとなる生活習慣は、実際には成人前、さらには小児期に形成され始め、成人後の介入ではその変更が困難なことが多いとされている。そのため、生活習慣病対策として成人対象の取り組みばかりでなく、小児・未成年者へのアプローチの重要性も指摘されている。母子健康や学校保健においても、例えば「健やか親子21」の取り組みなどによって、小児期からの健康づくりが推進されている。
一方、子どもたちの健康に影響を及ぼし得る生活習慣として近年、スマートフォンやゲームなどのデジタル機器の使用時間の長さへの懸念がしばしば指摘されるようになった。このほかにも我が国特有の課題として、OECD加盟国で最下位とされる子どもたちの精神的幸福度の低さが挙げられる。
このような状況に対応して、鳥取大学医学部環境予防医学分野では、デジタル社会における思春期世代の心身の健康を目指し、デジタル機器の節度ある使用と好ましい生活習慣の獲得について啓発することを目標とした公衆衛生活動を実施してきている。桑原氏らの今回の報告は、同講座が2022年度に行った学校保健活動の取り組みの概要と、島根県松江市内の中学校でのアンケート調査や健康教育活動を通して得た知見を総括したもの。
なお、同講座のこの活動は、歴史的には1991年まで遡り、当時、島根医科大学(現・島根大学医学部)が地域の教育委員会や学校と協力し「小児成人病対策事業」を実施したことに始まる。その後は研究者の異動に伴い、鳥取大学の同講座が活動を継続。現在は、医学部4年生の社会医学実習のフィールドとして、松江市内の小・中学校を10人程度のグループ単位で1年につき半年程度の間、週に半日程度訪問。児童・生徒との交流や聞き取り調査、アンケート調査などを通して学校保健上の課題を取りまとめ、それに対応した保健教材を作成し、医学生自身がそれを使って授業を行うなど、ピア・エデュケーション(同世代の仲間による教育技法)による啓発を実践している。
論文では、それらの活動の詳細な報告がされているが、本稿では中学生を対象に実施したアンケート調査の結果を中心に紹介する。
松江市内のある中学校全生徒のアンケート調査の結果
このアンケート調査は、松江市内のある中学校の生徒全員に対し、自記式質問紙を用いて実施された。調査項目は、先述の社会的背景を反映し、デジタル機器の使用状況を含む生活習慣全般を把握する内容。また、患者健康質問票(Patient Health Questionnaire-9;PHQ-9)を用いて抑うつ傾向を評価し、生活習慣との関連を検討した。
中学生4人に1人が軽度うつ傾向、9人に1人が中等度うつ傾向
この中学校の全生徒467人のうち434人から回答を得て、回答内容に不備のない357人(男子46.5%)を解析対象とした。
PHQ-9のスコア4点以下を「うつ傾向なし」、5~9点を「軽度うつ傾向」、10~27点を「中等度うつ傾向」とすると、それぞれ、64.1%、24.1%、11.8%が該当した。つまり、約4人に1人に軽度うつ傾向、約9人に1人に中等度うつ傾向が認められた。
性別で比較すると、女子のほうがうつ傾向の高い生徒が多かった(p=0.019)。
食べ物の好き嫌いが多い生徒、栄養バランスを考えない生徒はうつ傾向が強い
食べ物の好き嫌いは、「ほとんどない」が28.6%、「少しある」が52.7%、「たくさんある」が18.8%であり、好き嫌いが多いほどうつ傾向が強い生徒が多かった(p<0.001)。また、「栄養バランスを考えて食事を摂っているか」という質問に、「はい」と回答した生徒が82.9%、「いいえ」が17.1%であり、後者においてうつ傾向が強い生徒が多かった(p=0.006)。
朝食摂取頻度、夜食摂取頻度、家族と一緒に食べる頻度に関しては、うつ傾向との関連が有意でなかった。
スポーツをしていない生徒はうつ傾向が強い
体育の授業以外でのスポーツ活動(部活動や郊外のスポーツスクールなど)は、「週4日以上」が61.9%、「週1~3日」が21.0%、「週0日」が17.1%であり、その頻度が低いほどうつ傾向が強い生徒が多かった(p<0.001)。
睡眠習慣もうつ傾向と関連
睡眠時間や就床時刻とうつ傾向との関連については、平日と休日に分けて質問された。
その結果、平日の睡眠時間が短いことと(p=0.002)、休日の就床時刻が遅いこと(p=0.015)が、抑うつ傾向の強さと有意に関連していた。平日の就床時刻と休日の睡眠時間は、うつ傾向と有意な関連がなかった。
そのほかには、睡眠の質の低下(入眠潜時が長く中途覚醒が多い)が、抑うつ傾向の強さと有意な関連が認められた(p<0.001)。
平日より休日のデジタル機器利用が、抑うつ傾向と強く関連
デジタル機器の利用と抑うつ傾向との関連についても、平日と休日に分けて質問された。
その結果、平日については、SNS利用時間の長さのみが抑うつ傾向の強さと有意に関連し(p=0.009)、ゲームプレー、動画(YouTubeやテレビなど)視聴、および、デジタル機器の総利用時間(ゲーム、動画の他にスマホやパソコンなども含む)は、抑うつ傾向と有意な関連がなかった。
一方、休日については、SNS利用時間(p=0.008)、ゲームプレー時間(p=0.024)、動画視聴時間(p=0.015)が抑うつ傾向の強さと有意に関連していた。ただし、デジタル機器の総利用時間は有意な関連がなかった。
活用できる地域の資源を最大限活用する学校保健活動
上記のアンケートの結果や、学校保健スタッフとの交流から、中学生の抱えている健康課題を抽出し、心の健康と関連のある生活習慣、デジタル機器利用に関する教材を作成して、中学2年生を対象とする医学生による授業が行われた。
その結果、中学生からは「規則正しい生活を意識したい」、「心や体の健康のために人に頼ることも大事」、「自分の課題が見つかった」、「目標を立てるきっかけになった」といった声が聞かれ、学校保健スタッフからは「担任の先生からではなく、自分と近い世代で専門知識を持つ外部の人たちによる啓発が生徒にとって新鮮であり、保健活動のマンネリ解消につながる」、「経年的な教育の効果を実感した」、「地域での取り組みの継続が重要である」という意見が聞かれた。また、医学生からは「中学生の目線で考えてほしいという、教員からのアドバイスを得て、情報共有の在り方に気づきを得た」、「アンケートを実施、集計、分析し、その結果を伝わる形にまとめる方法を学んだ」といった意見があった。
著者らは、「健康教育を受講した生徒や学校保健スタッフから得られた意見から、ピア・エデュケーションの教育技法を用いて、デジタル機器の節度ある使用と好ましい生活習慣について啓発することができた。今後は関係者をつないで地域の資源を最大限活用した、思春期世代の心身の健康づくり活動の展開が望まれる」と総括している。
文献情報
原題のタイトルは、「大学と中学校が連携した学校保健活動:デジタル機器の使用と生活習慣についての調査と健康教育」。〔日本公衆衛生雑誌2025 Apr 1(J-STAGE早期公開)〕
原文はこちら(J-STAGE)















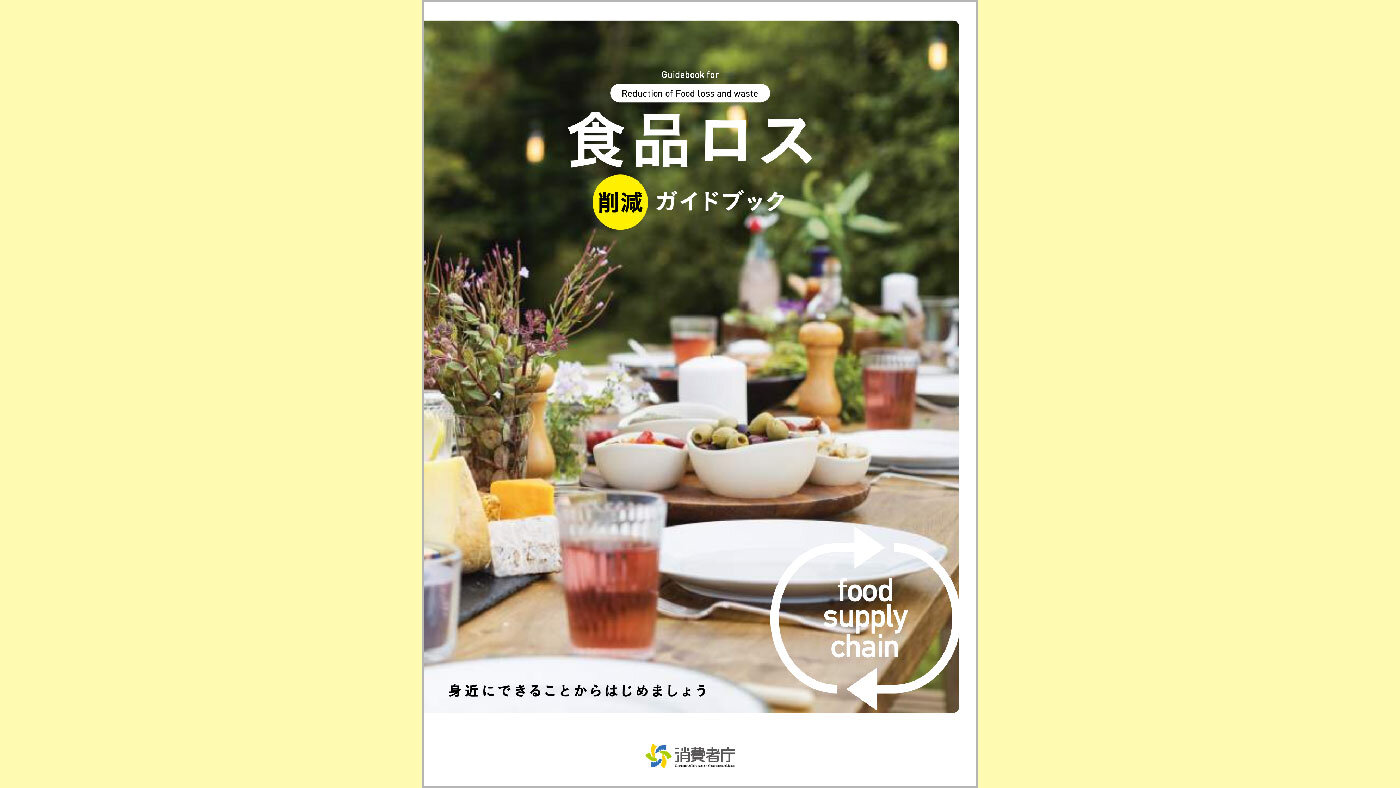







 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










