新開発の日本人向け食嗜好質問表で明らかになった、腹部肥満の有無による嗜好と食品・栄養素摂取量の違い
個人の食事の嗜好を30項目、所要時間5分程度で把握可能な質問表が開発された。また、この質問表を用いたパイロット研究が行われ、腹部肥満者の嗜好は非肥満者と異なり、その差異が実際に摂取している食品群・栄養素の違いに影響している可能性も明らかにされている。大阪大学医学部附属病院糖尿病・内分泌・代謝内科、栄養マネジメント部の長井直子氏、藤島裕也氏、西澤均氏らの研究によるもので、論文が「Nutrients」に掲載された。著者らは、「肥満者への栄養指導に際して、個人の嗜好を客観的に評価することが介入効果の向上につながるのではないか」と述べている。

日本の文化や食習慣に則した食嗜好質問表の開発とその検証
肥満が世界的に蔓延し、重大な健康課題となっている。それに対してさまざまな介入戦略が講じられ、例えば日本ではメタボリックシンドローム予防を主眼とした特定健診・保健指導が2008年度から続けられているが、顕著な効果はまだ報告されていない。
肥満改善の柱となる栄養介入において従来から、理想とされる摂取量や栄養バランスを対象者に指導するという方法が行われてきている。一方、個人の栄養素摂取量には嗜好の影響が小さくないことが注目されるようになり、肥満者の食習慣を変えるには嗜好を考慮した指導が必要と考えられるようになってきた。
食嗜好を把握するツールとして、海外では標準化された質問表(Leeds Food Preference Questionnaire;LFPQ)が用いられている。しかし、人々の食嗜好はその国の文化や伝統・習慣に大きく左右されるため、日本オリジナルの質問表が必要であり、LFPQを基に作成された日本人の食生活を考慮したLFPQ日本語版(LFPQ-J)も既に作成されている。今回、西澤氏らは、肥満者の食事指導での使いやすさにより重点を置いた、新たな日本人向けの食嗜好質問表を開発。その質問表を用いて非肥満者と腹部肥満者を対象とするパイロット研究を行い、食嗜好に違いがあるか、および、違いがあるならそれが、実際に摂取している食品群や栄養素の差に関連しているかなどを検討した。
本稿の前半ではその質問表の内容を紹介し、後半ではパイロット研究の結果を紹介する。
日本食嗜好質問表(JFPQ)の開発
質問表の開発に際して、まず、減量または糖尿病治療のための食事指導で頻繁に取り上げられる、30種類の食品が選択された。
次に、30種類の食品それぞれについて、「日本食品標準成分表(八訂)」および「日本炭水化物成分表(八訂)」を参照し、「糖質食品」(糖質が70%E以上)、「脂質食品」(脂質が40%E以上)、「タンパク質食品」(タンパク質が30%E以上)に分類。さらに、糖質食品と脂質食品については、含まれている糖類の量(可食部100gあたり10g未満/以上)により、「甘い糖質食品」「甘くない糖質食品」、「甘い脂質食品」「甘くない脂質食品」に分類した。
このほか、食物繊維が可食部100gあたり1g以上あり、エネルギー量が100gあたり100kcal未満の食品は「食物繊維食品」とした。なお、果物は食物繊維食品と甘い糖質食品の双方に含めた。
質問表にはこれら30種類の食品の写真を載せ、それぞれの写真の上に0~10点のスケールを表示して、回答者が好みの程度を選択できるようにした(まったく好みでないは0点、非常に好みの場合は10点)。この質問表の回答に要する時間は約5分だった。
このような手順で開発した質問表は、「日本食品嗜好質問表(Japan Food Preference Questionnaire;JFPQ)」と命名された。
JFPQによる嗜好の評価、および食行動、食事摂取量の調査
次に、JFPQを用いた食嗜好の調査が行われた。心血管代謝疾患への影響が強い腹部肥満の人の食嗜好を検出するという研究目的から、非肥満者と腹部肥満者の2群をリクルートした。
研究参加者の特徴
非肥満群は、20~74歳の医療スタッフ(医師または栄養士)から、BMI 25未満、ウエスト周囲長が男性85cm未満、女性90cm未満であり、血圧、脂質、血糖関連の治療薬が処方されていないことを適格条件として38人を登録した。一方、腹部肥満群は、20~74歳の一般企業の健診受診者の中から、BMI 25以上またはウエスト周囲長が前記の基準値を超過している30人を登録した。なお、血圧160/110mmHg以上、食事制限(タンパク制限、アレルゲン除去など)、運動制限などの該当者は除外されている。
両群の主な特徴は、非肥満群/腹部肥満群の順に、年齢は36.4±8.7/45.9±10.7歳、男性の割合50/80%、BMI 21.0±2.0/27.1±2.9、ウエスト周囲長72.8±7.1/96.0±7.1cmで、いずれも腹部肥満群のほうが有意に高値だった。また高血圧の割合は腹部肥満群が有意に高かった。脂質異常症と糖尿病も腹部肥満群のほうが多いものの、群間差は有意水準未満だった。
食行動と食事摂取量の調査
JFPQで把握される食嗜好との関連を検討するため、食行動と食事摂取量が調査された。
食行動については、日本肥満学会「肥満診療ガイドライン」に記載されている、7項目(体質や体重に関する認識、食動機、代理摂食、空腹・満腹感覚、食べ方、食事内容、食生活の規則性)に関する55個の質問で評価した。食事摂取量については、日本人向けの自記式の食物摂取頻度調査票(Food Frequency Questionnaire;FFQ)により把握した。
腹部肥満者は糖質食品・脂質食品の好みが強く、その摂取量が多い
では、ここからはパイロット研究の結果に移る。論文には、JFPQで把握された食嗜好と、食行動、食事・栄養素摂取量の関連について詳細に述べられているが、ここではポイントのみを紹介する。
腹部肥満の有無で、食物繊維食品以外の大半の食品群の嗜好の強さに有意差
JFPQで把握した食嗜好を、年齢と性別を調整後に非肥満群と腹部肥満群で比較した結果、食物繊維食品を除くすべての食品群(糖質食品、脂質食品、タンパク質食品)について両群間に有意差が検出され、いずれも腹部肥満群において嗜好が強い(より好む)という結果だった。
糖質食品を甘味の有無で分けた検討では、甘い糖質食品(和菓子、ソフトドリンク、果物、甘いパンなど)は、やはり腹部肥満群のほうが嗜好が強かった。また、甘くない糖質食品(白米、麺類、甘くないパン、せんべい)についても同様に、腹部肥満群のほうが嗜好が強かった。脂質食品に関しても、甘味があるものもないものも腹部肥満群のほうが嗜好が強かった。つまり、腹部肥満者は甘味を好むというよりも、糖質や脂質の多い食品を好むと考えられた。
食嗜好は栄養素摂取量と相関し、腹部肥満者は脂質・糖質を好むほど多く摂取
続いて、JFPQで把握された食嗜好が、実際に栄養素摂取量に関係しているかが検討された。腹部肥満の有無を考慮しない全体解析では、糖質(r=0.377)、脂質(r=0.414)、タンパク質(r=0.492)、食物繊維(r=0.367)のすべてと有意な正相関が確認された。
次に腹部肥満の有無別に解析すると、まず非肥満群では、糖質、脂質、タンパク質については嗜好の強さと摂取量の相関が認められず、唯一、食物繊維のみ正相関が認められた(r=0.398)。それに対して腹部肥満群では、食物繊維とタンパク質については嗜好の強さとの相関が認められず、脂質(r=0.412)および糖質(r=0.314)の嗜好の強さと摂取量との間に有意な正相関がみられた。
個人の食嗜好を考慮に入れた、栄養指導個別化の可能性
著者らは本研究の限界点として、腹部肥満群では女性の割合が低かったこと、非肥満群は医療従事者であったため結果解釈の一般化が制限される可能性があることなどを挙げている。
一方、以下のように、本研究で明らかになった注目すべき点をいくつか挙げている。
その一つとして、従来、肥満者は甘味に対する欲求が強いと言われることがあったが、本研究では糖質食品、脂質食品のいずれについても甘味の有無(糖類含有量の多寡)にかかわらず、腹部肥満者は非肥満者よりも嗜好が強く、結果として食物繊維食品を除くすべての食品群に対する嗜好が強いことが示されたことを指摘している。
強調すべきもう一つの点として、日本人の主食である白米が含まれる甘くない糖質食品についても、やはり非肥満者より腹部肥満者は嗜好が強く、かつ糖質の嗜好と実際の摂取量が腹部肥満者では正相関することを挙げ、「高脂質食品に加え白米など甘くない糖質食品を好んで多く食べることが、日本人の肥満や肥満関連疾患のリスクにつながっているのではないか」と述べている。
また、肥満者に対する摂取エネルギー制限、あるいはGLP-1受容体作動薬や減量・代謝改善手術により嗜好が変化することが報告されていることから、JFPQによる評価を経時的に行うことで、栄養指導の有効性を予測できる可能性もあるという。
論文の結論は、「腹部肥満を来している日本人は、脂質および糖質を多く含む食品に対する嗜好が強く、これが実際の摂取量の増加と関係している。このことは、肥満に対する栄養指導において、個人の食嗜好を考慮した個別介入の重要性を強調するものであり、新たに開発したJFPQがそのためのツールとして有用と言える」と総括されている。
文献情報
原題のタイトルは、「Food Preference Assessed by the Newly Developed Nutrition-Based Japan Food Preference Questionnaire and Its Association with Dietary Intake in Abdominal-Obese Subjects」。〔Nutrients. 2024 Dec 9;16(23):4252〕
原文はこちら(MDPI)









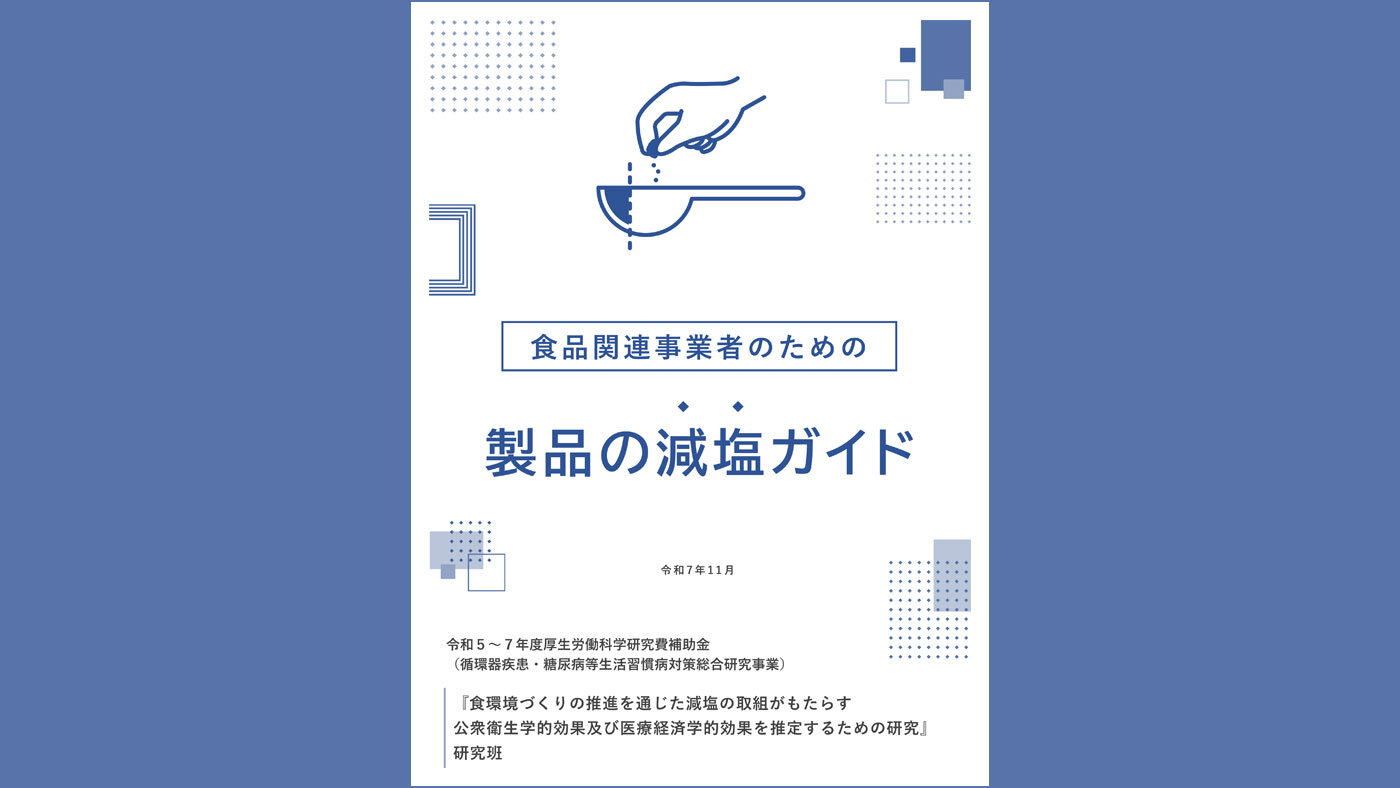













 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










