18歳未満の認知機能が運動介入で向上 実行機能・注意機能・記憶力を有意に改善する可能性
運動による認知機能への影響をシステマティックレビューとメタ解析で検討した研究結果が報告された。実行機能や注意機能、ワーキングメモリなどが運動介入による有意に改善すること、とくに有酸素運動の影響が大きいことなどが明らかにされている。中国の研究者の報告。
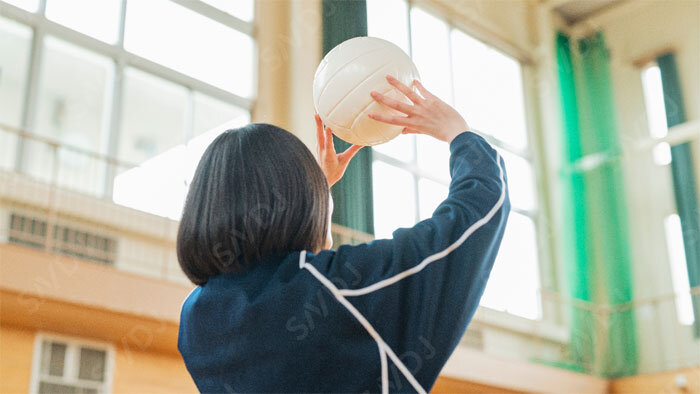
成長期に行う運動は認知機能に有意な影響を及ぼすのか?
論文に述べられている研究背景によると、運動は認知機能にプラスの影響を及ぼすとする報告が多いものの、依然として一貫性が欠如しているという。このことから著者らは、とくに認知機能の成長段階にある未成年に焦点をあて、システマティックレビューとメタ解析により運動の有効性を検討した。
システマティックレビューとメタ解析の推奨報告項目(PRISMA)ガイドラインに準拠し、Web of Science、Embase、PubMed、Cochrane Central Register of Controlled Trials、CBMなどの文献データベースを利用して、それぞれの開始から2024年11月までに収載された論文を対象に、18歳未満の未成年に対する運動加入の認知機能への影響を無作為化比較試験(RCT)で検討した、査読システムのあるジャーナルに掲載された論文を検索。ヒットした論文の参考文献や灰色文献(学術的なジャーナルに正式に発表されていない文献)のハンドサーチも行った。コホート研究、症例対照研究、レビュー論文、学会発表、および、英語または中国語以外の言語の論文などは除外した。
一次検索で2,909報がヒットし、ハンドサーチにより1報を追加。重複削除後の2,560報を3名の研究者が独立してタイトルと要約に基づきスクリーニングを行い51報に絞り込み、全文精査を実施。最終的に、21件のRCTの報告を適格と判断した。
抽出されたRCTの参加者数は合計3,544人(運動介入群1,730人、対照群1,814人)、介入期間は2~39週間だった。
運動介入は未成年の認知機能を向上させ得る
評価されていた認知機能は、実行機能、注意機能、認知的柔軟性(状況の変化に応じて思考や行動を切り替える能力)、抑制制御(不適切な反応や衝動を抑えて行動をコントロールする能力)、ワーキングメモリ(一時的に保持できる情報の量とその処理能力)であり、それら評価項目ごとにメタ解析が行われた。
実行機能については7件のRCTのデータがメタ解析の対象となった。いずれの研究も、標準化平均差(SMD)は0を上回っていたが95%信頼区間が0をまたぎ、それぞれ単独では実行機能に対する運動介入の有意な影響を示していなかった。しかしメタ解析からは、SMD=0.21(95%CI;0.06~0.37)で研究間の異質性はなく(I2=0%)、運動介入により実行機能が向上することが示された。
注意機能については9件のRCTのデータがメタ解析の対象となった。いずれの研究もSMDが0を上回っており、かつ、6件の研究は95%信頼区間の下限が0を超え、単独でも運動介入の有意な影響を示していた。メタ解析の結果はSMD=0.56(0.34~1.22)で、運動介入により注意機能が向上することが示された。ただし研究間の異質性が高かった(I2=71%)。
認知的柔軟性については5件のRCTのデータがメタ解析の対象となった。4件の研究はSMDが0を上回っており、かつ、3件の研究は95%信頼区間の下限が0を超え、単独でも運動介入の有意な影響を示していた。ただし1件の研究はSMDが0を下回っていた(信頼区間の上限は0超)。メタ解析の結果はSMD=0.53(0.04~1.02)で、運動介入により認知的柔軟性が向上することが示された。ただし研究間の異質性が高かった(I2=83%)。
抑制制御については10件のRCTのデータがメタ解析の対象となった。いずれの研究もSMDが0を上回っており、かつ、3件の研究は95%信頼区間の下限が0を超え、単独でも運動介入の有意な影響を示していた。メタ解析の結果はSMD=0.58(0.22~0.86)で、運動介入により抑制制御が向上することが示された。ただし研究間の異質性が高かった(I2=78%)。
ワーキングメモリについては3件のRCTのデータがメタ解析の対象となった。いずれの研究も、標準化平均差(SMD)は0を上回っていたが95%信頼区間が0をまたぎ、それぞれ単独では実行機能に対する運動介入の有意な影響を示していなかった。しかしメタ解析からは、SMD=0.54(0.16~0.91)で研究間の異質性はなく(I2=0%)、運動介入によりワーキングメモリが向上することが示された。
有酸素運動で効果量が大きい傾向があるものの、運動のタイプによらず有意
介入に用いた運動のタイプ別のサブグループ解析も実施された。その結果、有酸素運動でより高いSMDが示される傾向にあったが、サブグループ間での有意差はなく(p=0.562)、全体解析の結果はSMD=0.47(0.35~0.60)、I2=66.5%であり、運動介入はそのタイプによらず未成年の認知機能を向上させ得ると考えられた。サブグループごとの解析結果は以下のとおり。
有酸素運動による介入を行ったRCTは20件だった。19件の研究はSMDが0を上回っており、かつ、7件の研究は95%信頼区間の下限が0を超え、単独でも有意な影響を示していた。1件の研究はSMDが0を下回っていたが、信頼区間の上限は0を超えていた。メタ解析の結果はSMD=0.53(0.32~0.73)、I2=74.2%だった。
高強度インターバルトレーニングによる介入を行ったRCTは4件だった。いずれの研究もSMDは0を上回っていたが95%信頼区間が0をまたぎ、それぞれ単独では有意な影響を示していなかった。しかしメタ解析の結果は、SMD=0.30(0.05~0.56)と有意であり、研究間の異質性を認めなかった(I2=0%)。
抵抗力トレーニングによる介入を行ったRCTは2件だった。いずれの研究もSMDは0を上回っていたが95%信頼区間が0をまたぎ、それぞれ単独では有意な影響を示していなかった。しかしメタ解析の結果は、SMD=0.46(0.10~0.83)と有意であり、研究間の異質性を認めなかった(I2=0%)。
複合運動よる介入を行ったRCTは8件だった。いずれの研究もSMDが0を上回っており、かつ、5件の研究は95%信頼区間の下限が0を超え、単独でも運動介入の有意な影響を示していた。メタ解析の結果はSMD=0.51(0.29~0.73)、I2=67.4%だった。
文献情報
原題のタイトルは、「The effects of physical exercise on cognitive function in adolescents: a systematic review and meta-analysis」。〔Front Psychol. 2025 Jul 28:16:1556721〕
原文はこちら(Frontiers Media)























 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!











