薬局を拠点とした地域の栄養改善に向け薬剤師・管理栄養士に求められること インタビュー調査
地域住民の健康増進の拠点として位置付けられている「地域の薬局」が、住民の栄養改善を積極的に担っていくために必要な事柄が報告された。昭和医科大学薬学部社会健康薬学講座の熊木良太氏らが、薬剤師や管理栄養士、計15名にインタビュー調査を行った結果であり、「Journal of Health, Population and Nutrition」に論文が掲載された。低栄養や生活習慣病リスクのある住民に対する介入のポイントとして5項目、薬局での栄養介入という仕組みそのものを改善するためのポイントとして4項目が特定されたという。

地域の薬局を拠点とした地域住民の栄養改善に必要な方策を探る研究
地域の薬局には地域住民の健康全般をサポートする機能が求められていて、栄養改善も重要な役割の一つ。そのため、管理栄養士を配置している薬局も徐々に増加してきている。しかし現状では、配置された管理栄養士が十分に活用されていない実態も報告されており、薬局が住民の栄養改善に役立つ存在となるために改善の余地がある。これを背景として熊木氏らは、薬局における栄養介入機能の強化方法を探ることを目的に、薬剤師、管理栄養士へのインタビュー調査を行った。
インタビューの対象と方法
インタビューの対象は、健康サポート薬局に関する研修を受けた調剤薬局の薬剤師5人(女性3人)、調剤薬局で管理栄養士と連携して勤務している薬剤師5人(女性3人)、調剤薬局に勤務している管理栄養士5人(すべて女性)の計15人。なお、健康サポート薬局とは、かかりつけ薬局の機能を有し、かつ、介護や食事・栄養摂取に関する相談もできる薬局として、厚生労働大臣が定める基準を満たしている薬局のこと。
インタビューとその分析には、国内で開発された質的研究手法であるPAC分析(Personal Attitude Construct analysis)が用いられた。PAC分析は、インタビューを通じて対象者自身が認識していない内面的な態度や価値観などを抽出できる手法とされている。
本研究ではまず、薬局訪問者の中で低栄養や生活習慣病のリスクのある人に接した場合を想定し、連想するキーワードをカードに記入してもらった。連想を励起するために、研究者によって作成された文(低栄養状態への栄養介入に際して対象者にどんなことを理解してもらいたいか?/生活習慣病患者への栄養介入に際して薬剤師や管理栄養士が身につけておくべき知識は?など)を提示した。
次に、それらのキーワードの互いの関連性を7段階のリッカートスケールで評価してもらい、その結果を基に研究者がデンドログラム(樹形図)を作成。それを対象者に提示して、解釈を求めた。これら一連のインタビューの所要時間は約1時間だった。
最後に、それらのインタビューをすべて文字起こししたうえでラベル化と分類を行い、栄養介入におけるポイントを特定した。
なお、インタビュアーは薬剤師であり、結果の分析も薬剤師が行った。
低栄養や生活習慣病リスクのある住民に対する介入のポイント
低栄養リスクのある住民に対する介入
低栄養リスクのある住民に対する介入が必要なポイントは、合計37種類のラベルに分類された。細かくみると、介入を必要とする患者像に関するラベルが8種類、アセスメントに必要な情報関連で10種類、患者意識の是正関連で5種類、実行可能な方法の提案が8種類、介入時に考慮すべきことが6種類だった。
薬剤師、管理栄養士と連携している薬剤師、管理栄養士の三者で共通するラベルとして、患者像関連では「高齢者」と「食事に関する誤解や知識不足している者」、アセスメント関連では「食事の摂取量・質・栄養バランス」と「体重、BMI」、患者意識の是正関連では「食事に関する誤解の修正」、実行可能な方法の提案では「栄養バランスのとれた食事指導」、「タンパク質を意識したアドバイス」、「嚥下機能にあわせた食事の提案」、「体重管理」が挙げられた。
一方、薬剤師および管理栄養士と連携している薬剤師でラベル化され、管理栄養士でラベル化されなかった項目として、アセスメント関連で「摂食・嚥下機能」と「環境(例えば家族)のサポート状況」が特定された。この点について著者らは、「薬剤師は患者の服薬状況を日常的にモニタリングしており、患者だけでなく家族や介護者にも服薬指導を行っているためではないか」と考察している。
それに対して管理栄養士のみでラベル化された項目として、患者像関連で「若い女性」や「食生活改善を諦めている」などが特定された。この点については「管理栄養士は個々の患者の状況にあわせたきめ細やかな対応が可能であることが示唆される」と考察されている。
生活習慣病リスクのある住民に対する介入
生活習慣病リスクのある住民に対する介入が必要なポイントは、合計29種類のラベルに分類された。細かくみると、介入を必要とする患者像に関するラベルが5種類、アセスメントに必要な情報関連で11種類、患者意識の是正関連で3種類、実行可能な方法の提案が4種類、介入時に考慮すべきことが6種類だった。
薬剤師、管理栄養士と連携している薬剤師、管理栄養士の三者で共通するラベルとして、患者像関連では「生活習慣の乱れ(不規則な食事、偏食、運動不足)ている者」と「食事に関する誤解や知識不足な者」、アセスメント関連では「食事の摂取量・質・栄養バランス」、実行可能な方法の提案では「目標とする具体的な数値(摂取カロリー、体重、検査値など)」、「レシピなど具体的な方法の提案」が挙げられた。また、「薬物療法、食事療法、運動療法の併用」、「成功体験を増やす」、「多職種(医師、看護師、薬剤師、管理栄養士)との連携」も、三者に共通するラベルだった。
一方、薬剤師および管理栄養士と連携している薬剤師でラベル化され、管理栄養士でラベル化されなかった項目として、アセスメント関連で「家族などの周囲のサポート状況」、実行可能な方法の提案として「患者の嗜好や状態に合わせた栄養補助食品の提案」、介入時の留意点として「家族など周囲の支援者への働きかけ」などが挙げられた。著者らは、「薬剤師は生活習慣の改善を服薬アドヒアランス向上と同様に捉えている」と述べている。
それに対して管理栄養士のみでラベル化された項目として、患者像関連で「食生活改善を諦めている」、アセスメント関連で「患者の食事に対する意識」、「体重、BMI」、「食品の入手しやすさ」、「経済状態(暮らし向き)」などが挙げられた。
薬局での栄養介入という仕組みそのものを改善するためのポイント
薬局での栄養介入という仕組みそのものを改善するための課題は、13種類のラベルに分類された。細かくみると、栄養介入フローの確立が6種類、医療者の教育が4種類、患者への制度の周知が1種類、制度改革の必要性が2種類だった。
薬剤師、管理栄養士と連携している薬剤師、管理栄養士の三者で共通するラベルとして、「管理栄養士による栄養指導の提供フローの確立」、「早期発見および早期介入」、「患者情報(疾患名や検査値など)を医療機関(医師)と共有する」、「薬剤師の栄養知識の教育と向上」、「低栄養に関する指導は管理栄養士に依頼する」が挙げられた。
一方、管理栄養士と連携している薬剤師のみでラベル化された項目として、医療提供者の教育関連で「栄養介入が投薬量の削減につながることの認識」が挙げられた。そのほかにも「患者への制度の告知」の必要性、および、「制度改革の必要性」(栄養介入の時間確保、有償化の検討)は、いずれも管理栄養士と連携している薬剤師のみでラベル化された。
栄養指導提供プロセスの確立と、薬剤師のスキルアップが課題
本研究の限界点として著者らは、インタビューの対象者数が十分とは言えないこと、調剤薬局の勤務者のみを対象としたため、処方箋を持たない、より広範な一般住民が訪れるドラックストアー等での傾向を把握できていないことなどを挙げている。そのうえで、「薬局での栄養介入の質を高めるために必要なこととして、薬剤師と管理栄養士の双方が、スクリーニング、評価、そして教育という一連の流れが重要であると認識していることが指摘された。と同時に、この流れを実践するには、管理栄養士による栄養指導提供プロセスの確立と、薬剤師の栄養指導に関する知識不足が課題であることが明らかになった」と総括。また、「とくに薬剤師はリスクの高い患者のスクリーニングと評価に重点を置き、管理栄養士との連携に向けた知識の向上を図る必要がある」と付け加えている。
文献情報
原題のタイトルは、「Toward enhanced nutritional interventions in community pharmacies: personal attitude construct analysis」。〔J Health Popul Nutr. 2025 Aug 11;44(1):287〕
原文はこちら(Springer Nature)









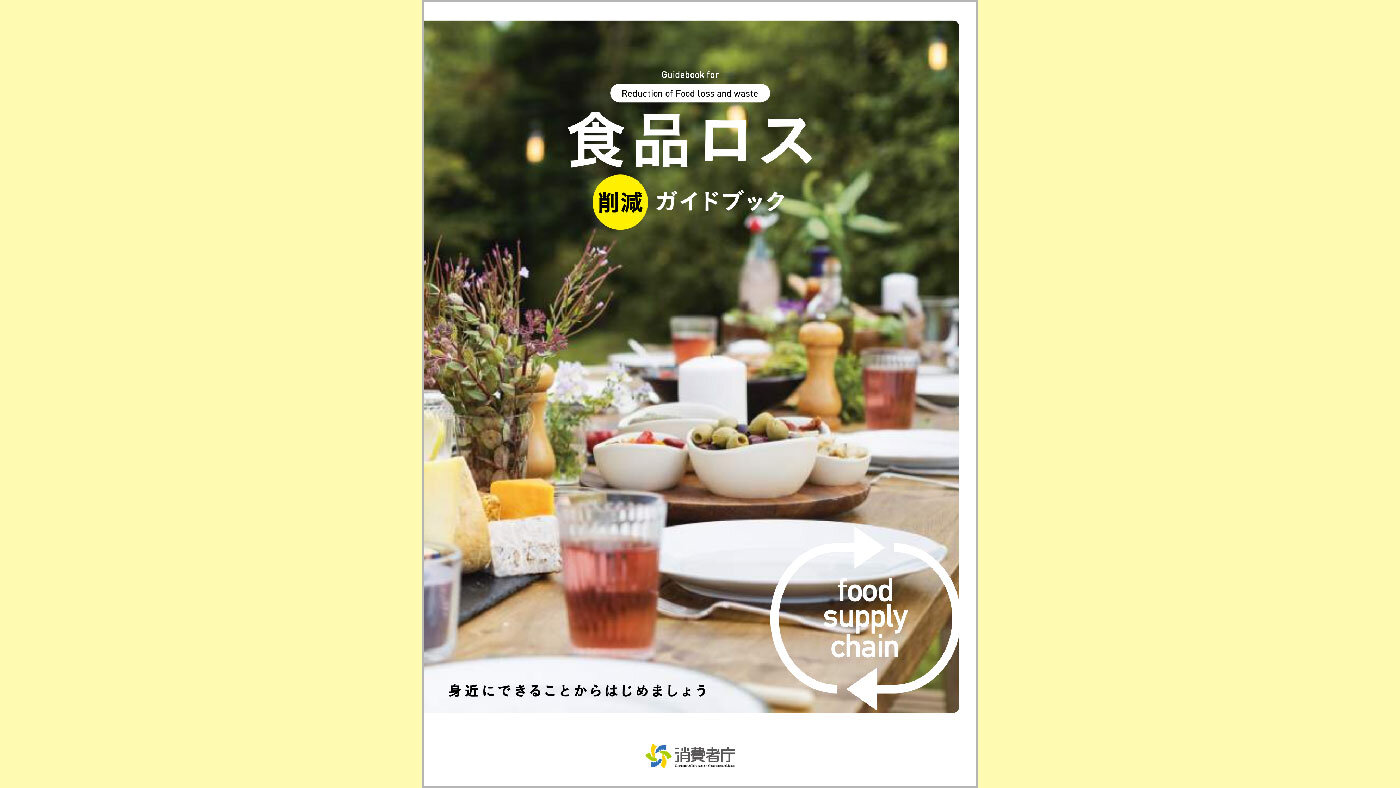













 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!








