毎日朝食を食べる人は生殖補助医療(ART)の治療成績が良好 朝食摂取の重要性に関する新エビデンス
朝食を欠かさないことの重要性を示す新たなエビデンスが報告された。毎日朝食を摂取する人はそうでない人と比較して、生殖補助医療(assisted reproductive technology;ART)治療後の生産率が高く、流産率が低いという。東京医科大学、金沢大学、京都ノートルダム女子大学の共同研究の成果であり、「Nutrition」に論文が掲載されるとともに、大学のサイトにプレスリリースが発表された。著者らは、「毎日の朝食摂取という患者自身による介入が、ARTの成績向上に寄与することが期待される」と述べている。

生殖補助医療(assisted reproductive technology;ART)とは
生殖補助医療(ART)(日本産婦人科医会)研究の背景:時間生物学の知見を生殖医療の治療成績向上につなげる
生殖医療の治療成績は、薬剤・胚培養・凍結技術の改善とともに進歩してきた。さらなる治療成績の向上のためには、新たな視点での介入法が求められるようになり、研究グループでは今回、時間生物学に着目した。
生物の生体リズムは、時計遺伝子群の周期的な発現により形成され、さまざまな標的遺伝子の発現を制御している。この生体リズムは、視床下部の視交叉上核に存在する中枢時計と、全身の細胞にある末梢時計によって制御されており、時計機能の異常は、糖尿病、脂質異常症、高血圧、うつ病の発症リスクを高めることが報告されている。
最近では、夜勤が多いシフトワークが、排卵障害、不妊症および不育症のリスクを増加させることも明らかになった。本研究では、不妊症患者における朝食摂取頻度とART成績との関連を検討した。
本研究で得られた結果・知見:朝食を欠かさないことが転帰に独立して関連
年齢、喫煙状況、飲酒状況、肥満度、抗ミュラー管ホルモン値、妊娠分娩歴を含む潜在的交絡因子を調整後、ART成績の多変量解析を行った。
患者を1週間の朝食の摂取頻度に基づいてグループ分けし解析したところ、毎日(6~7回/週)朝食を摂取する群は、他の群と比較してART治療後の生産率が高く、流産率が低いことが示された(表1)。
独立した関連のある因子は、この朝食摂取頻度と年齢(若年)であり、BMIや喫煙・飲酒状況、分娩歴、卵巣予備能の指標とされる抗ミュラー管ホルモン値は、治療転帰との独立した関連は示されなかった。
| オッズ比 | 95%信頼区間 | P値 | |
|---|---|---|---|
| 朝食摂取頻度 | 3.03 | 1.048–8.771 | 0.04 |
| 登録時年齢 | 0.804 | 0.665–0.939 | 0.01 |
| BMI:肥満指数 | 1.177 | 0.344–4.031 | 0.8 |
| 喫煙状況 | 0.214 | 0.003–14.286 | 0.47 |
| 飲酒量 | 0.978 | 0.312–3.064 | 0.98 |
| 分娩歴 | 1.158 | 0.424–3.164 | 0.78 |
| AMH:抗ミュラー管ホルモン | 0.719 | 0.309–1.674 | 0.44 |
今後の研究展開および波及効果
毎日朝食を摂取することは、良好なART成績と関連していた。本研究の結果は、ARTにおいて毎日朝食を摂取することの重要性を示唆している。
毎日の朝食摂取という患者自身による介入が、ARTの成績向上に寄与することが期待される。
プレスリリース
毎日の朝食摂取は良好な生殖補助医療の治療成績に貢献する(東京医科大学)
文献情報
原題のタイトルは、「Impact of daily breakfast intake on the outcomes of assisted reproductive technology procedures」。〔Nutrition. 2024 Aug 14:127:112555〕
原文はこちら(Elsevier)









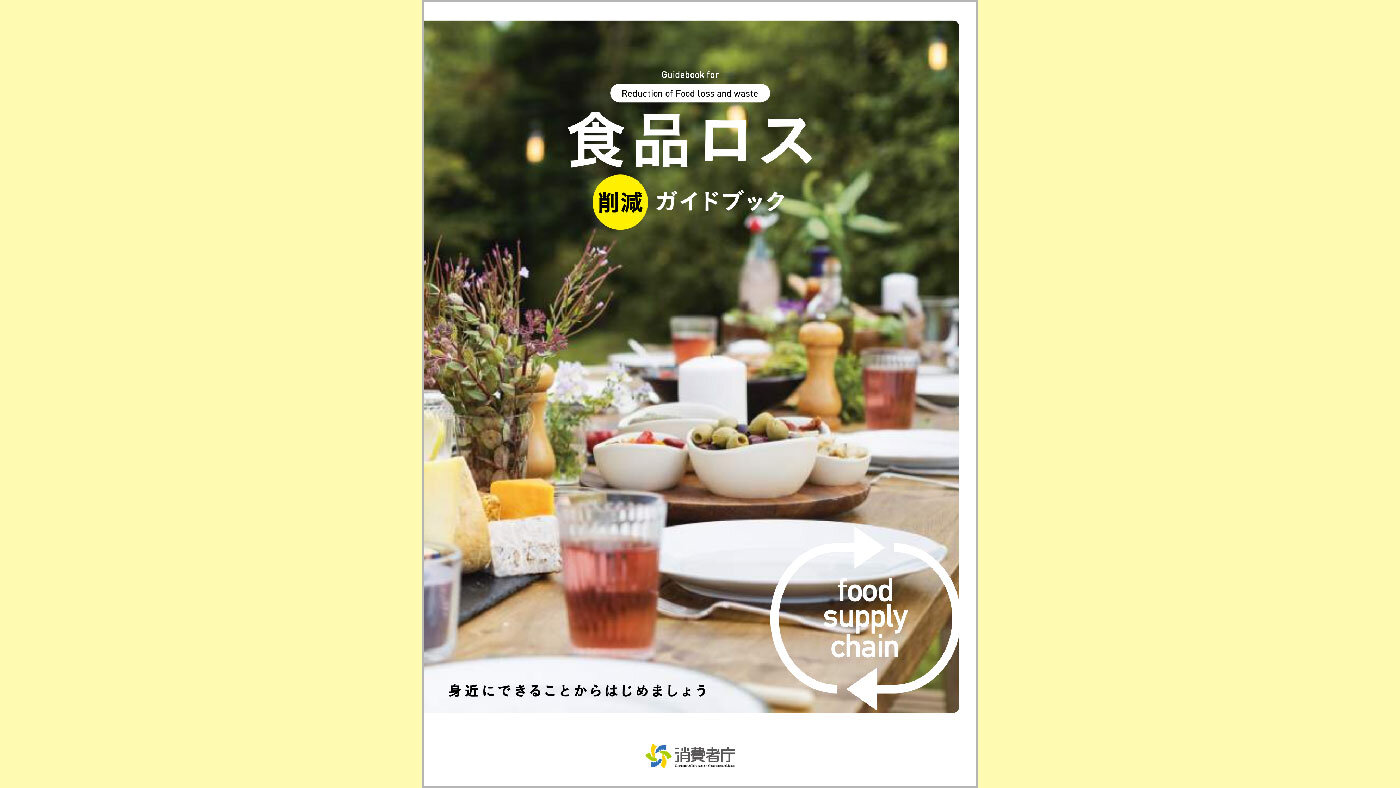













 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!








