女子学生アスリートの半数以上に補食習慣があるも炭水化物はなお不足 補食指導の必要性高まる
国内の女子大学生アスリートの補食摂取状況の実態と、摂取栄養素量との関連が報告された。補食摂取の習慣のあるアスリートは半数強であること、補食摂取群は炭水化物の摂取量が有意に多いものの、推奨値を満たしていないアスリートが少なくないことなどが明らかにされている。新潟医療福祉大学医療福祉学研究科健康栄養学の稲葉洋美氏らの研究によるもので、「Healthcare」に論文が掲載された。

国内女性アスリートの補食の摂り方の実態を調査
アスリートのスポーツパフォーマンスおよび健康の維持のために、トレーニング負荷に見合ったエネルギーを摂取することが欠かせない。とくにエネルギー基質である炭水化物が不足しないことが重要とされている。摂取エネルギーが十分でない女性アスリートでは、短期的には体重減少、長期的には月経異常、骨粗鬆症、摂食障害などのリスクが高まる。
また、トレーニングの直後に炭水化物を摂取することで筋グリコーゲン再合成が促進されること、その摂取タイミングがわずかに遅れただけで、グリコーゲン再合成が遅延することも知られており、1日3食の主要な食事以外に、トレーニング前後やトレーニングの合間にも、補食として炭水化物を摂取することが一般的に行われている。ただ、女性アスリートの補食摂取に焦点を当てた研究は、これまでのところ数少ない。
これを背景として稲葉氏らは、女子学生アスリートの補食摂取習慣の実態と、栄養素摂取量との関連の把握のため以下の研究を行った。
習慣的に補食を摂取している割合は55.7%で、おにぎりが最多
この研究は、同大学の強化指定運動クラブに所属し、全国大会レベルで活躍している女子学生アスリート70人を対象に、強化トレーニング期間中に簡易型自記式食事歴法質問票(brief diet history questionnaire;BDHQ)を用いた横断調査として行われた。また、サプリメントの摂取状況などについても調査されている。
研究参加者の主な特徴は、年齢が20±1歳、BMI21.8±1.8、体脂肪率22.8±4.5%で、所属クラブはバスケットボールが28.6%、バレーボールが22.9%、水泳18.6%、サッカー17.1%、陸上12.9%。摂取エネルギー量は29.3±10.3kcal/kgであり、主要栄養素摂取量は炭水化物が4.45±1.76g/kg、タンパク質1.01g±0.40g/kg、脂質0.76±0.29g/kgだった。
全体の55.7%が週1回以上、補食を摂取していた。補食として摂取する食品は、おにぎりが36.7%と最も多く、次いでパンが20.4%であり、エナジージェルとプロテインサプリが各10.2%と続いた。摂取するタイミングはトレーニング前が55.5%と最多であり、次いでトレーニング後が26.7%を占めていた。
補食摂取習慣の有無でエネルギー量・炭水化物などの摂取量に有意差
補食摂取群と非摂取群の比較で、年齢、BMI、体脂肪率等に有意差はなかった。
それに対して栄養素摂取量は、エネルギー量(31.5±10.00 vs 26.6±9.92kcal/kg、p=0.047)、炭水化物(4.84±1.71 vs 3.96±1.65kcal/kg、p=0.035)が、補食摂取群のほうで有意に高値だった。またビタミンC摂取量も補食摂取群で多かった。
一方、タンパク質、脂質、食物繊維、ビタミンC以外の微量栄養素については有意差が認められなかった。
補食摂取習慣のあるアスリートもDRIの推奨を満たしていないことが少なくない
次に、「日本人の食事摂取基準(Dietary Reference Intakes;DRIs)2020年版」の推奨値を満たしているアスリートの割合を検討。すると、すべての栄養素について、その割合に有意差は認められず、補食摂取習慣の有無にかかわらず推奨値を満たしている割合が低かった。
例えば、炭水化物の推奨比率(50~65%エネルギー)を満たしていた割合は、補食摂取群が56.4%、非摂取群が61.3%であった。
一方、脂質に関する推奨(20~30%エネルギー)については、補食摂取群の64.1%、非摂取群の74.2%が満たしており、比較的高値だった。しかし推奨値の範囲を超過して摂取しているアスリートが、同順に3.2%、12.9%であり、補食摂取習慣のないアスリートで脂質への偏りが強い傾向がみられた。また、たんぱく質(13~20%エネルギー)についても、同順に48.7%、41.9%が推奨を満たしていなかった。これらの結果について著者らは、「主要栄養素の摂取バランスを推奨される比率に近づける必要がある」と、論文の考察において述べている。
なお、補食非摂取群では、カルシウム(推定平均必要量〈EAR〉550mg)および鉄(月経ありでのEAR 8.5mg)を満たす割合が、いずれも9.7%とわずかだった。このほか、サプリメント利用者は全体で31.4%であり、補食摂取習慣の有無では有意差がなかった。また日常の食習慣については、補食摂取群で大豆製品や果物の摂取頻度が高い傾向があったが、群間差は有意水準に至らなかった。
女子大学生アスリートに対し、適切な補食の摂り方を指導する必要がある
著者らは本研究が単一の大学のアスリートを対象に行われたものであること、女性アスリートの栄養関連の主要な問題である三主徴(female athlete triad;FAT)のリスクを評価していないこと、食事調査には過少申告が伴うことなどの限界点を挙げたうえで、「女子大学生アスリートの補食摂取頻度は低く、さらに補食を習慣的に摂取しているアスリートであっても、摂取している食品は嗜好品が少なくなかった。スポーツパフォーマンスの向上のために、補食の適切な摂り方に関する栄養指導が必要であると考えられる」と結論をまとめている。
また、「本研究の結果は、アスリートやアスリートの栄養サポートを行う栄養スタッフにとって有益な情報となり得る」としている。
文献情報
原題のタイトルは、「Snack and Nutrient Intake Status of Top-Level Female University Athletes: A Cross-Sectional Study」。〔Healthcare (Basel). 2024 Feb 13;12(4):468〕
原文はこちら(MDPI)










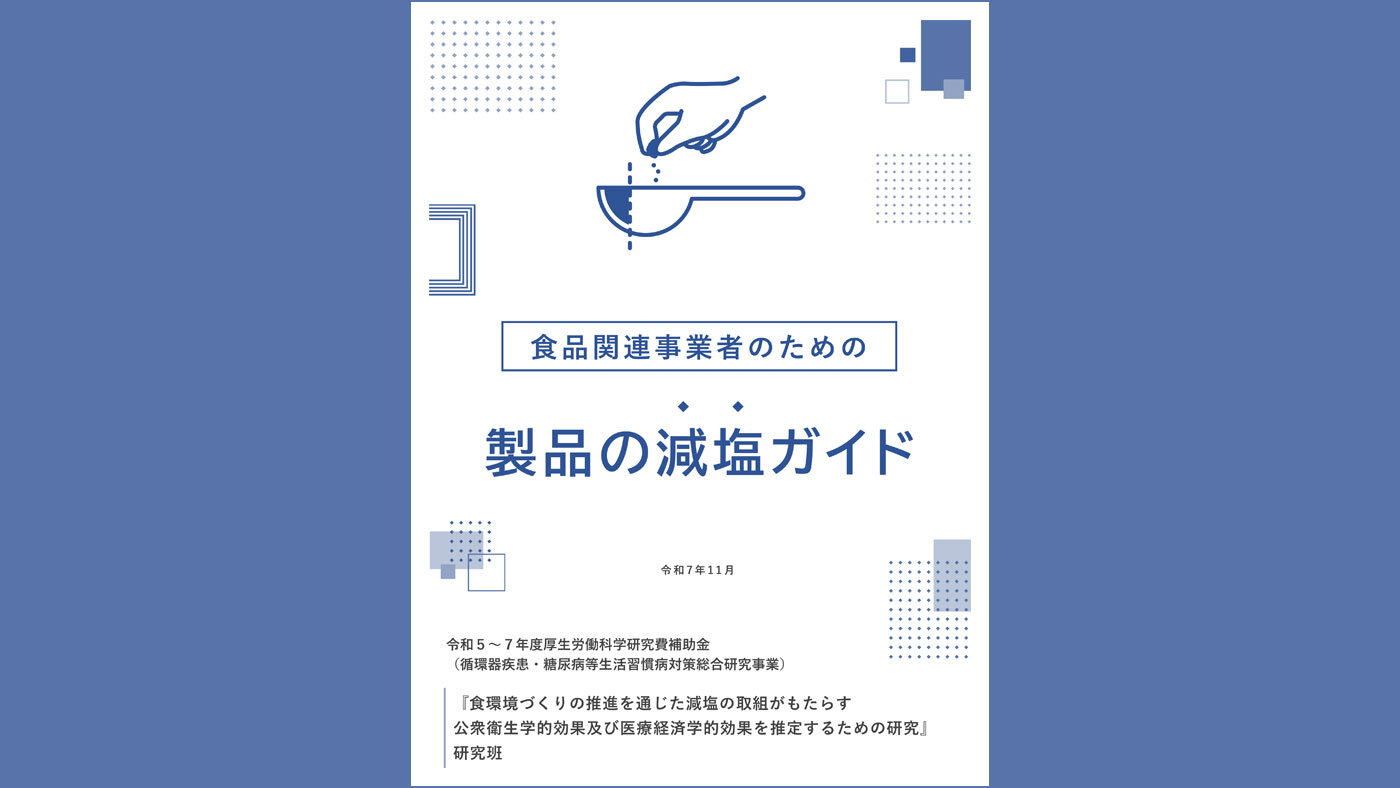












 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










