パフォーマンス向上のためのビタミンD摂取は1日100〜125μgが適量か? ナラティブレビューから考察
ビタミンDの有用性についてスポーツパフォーマンスという切り口で考察を加えた、ナラティブレビュー論文を紹介する。1日4,000~5,000 IU(100〜125μg)が、パフォーマンス向上のための安全な用量ではないかと述べられている。スイスの研究者らによる報告。

スポーツパフォーマンスという視点でビタミンDの影響をレビュー
ビタミンD欠乏がさまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があることは、よく知られている。歴史的には主に、骨と骨格筋の恒常性と代謝との関連で研究されてきたが、過去10年ほどの間に、ランナーやバスケットボール選手、騎手、体操選手、ダンサーを含むさまざまなスポーツアスリートでのビタミンDレベルに関する研究が報告されている。総じて、スポーツアスリートのビタミンDレベルは非アスリート集団と大きく異ならないと考えられるが、日光曝露の減る季節には、アスリートの間でも欠乏症が蔓延している可能性があり、かつ、そのことはあまり認識されていない。
ビタミンDレベルが低いと、疲労骨折や筋骨格損傷が増加したり、またパフォーマンスが制限される可能性がある。ただし、スポーツパフォーマンスという視点から、これまでの研究を総括したレビューは多くない。
このナラティブレビューのため、ScopusおよびPubMedを用いた文献検索が行われた。2022年6月末までに収載された論文を対象に、ビタミンD、アスリート、パフォーマンスなどの用語で検索。原著論文だけでなく、症例報告や総説も適格として、抽出されたそれらの報告を基に、VO2max、筋力、スプリントパフォーマス、回復、および有害事象などの観点で考察がなされている。それらの中から一部のポイントを抜粋する。
ビタミンD欠乏症の定義
ビタミンDの不足や欠乏の定義については、50~75nmol/Lを不足、50nmol/L未満を欠乏、25nmol/Lを重度の欠乏とすることが多いようだが、学会や規制機関によって異なる。
もう一つの問題として、用いられる単位が統一されていないという点も指摘される。「nmol/L」を使用している場合と「ng/mL」を使用しているものなどが混在し、古いものでは10ng/mL未満を欠乏としている。ただし、世界保健機関(WHO)は、25ヒドロキシビタミンD[25(OH)D]の血清濃度が20ng/mL(50nmol/L)未満を、ビタミンD欠乏と定義している。
このほかに、アスリートのビタミンDレベルに関する包括的レビューでは、血清濃度のカットオフ値を30ng/mL(75nmol/L)とする推奨もみられる。
ビタミンDと運動パフォーマンス
近年、ビタミンDにはスポーツパフォーマンスを向上させる可能性のあるエルゴジェニック特性があることが示唆されている。ただし、この関係は性別や年齢に依存したものである可能性があり、若年の男性の場合にとくに有利となるという報告もある。
ビタミンD3受容体はヒトの骨格筋組織にも発現しており、ビタミンDが骨格筋の活動に直接影響を与えると考えられる。トレーニングを行っていない成人を対象とした研究では、血清25(OH)Dレベルの上昇が筋力と筋肉量にプラスの影響を与えることが示された。ところが、アスリートを対象とした研究ではこの関連はまだ認められておらず、アスリートにおける25(OH)D血清レベルの最適値についての結論は出ていない。
VO2maxとビタミンD
アスリートにおけるビタミンDの効果は、最大酸素摂取量(VO2max)、持久力にプラスの影響があるようにみえる。その詳細なメカニズムは不明だが、ビタミンD3の活性化にかかわるシトクロムP450(CYP)によって説明できる可能性がある。
VO2maxによって評価されるアスリートの有酸素能力とビタミンDとの間の関連性には矛盾もみられる。ポジティブな報告としては、男子プロサッカー選手の25(OH)D値とVO2maxが直線的な有意な関連があるとする報告や、未成年サッカー選手に8週間の高強度インターバルトレーニングを行い、その間にビタミンDを5,000 IU/日(125μg/日)またはプラセボを投与した結果、サプリ群でビタミンDレベルが119%、VO2maxが20%上昇したのに対して、プラセボ群ではビタミンDレベルが8.4%低下しVO2maxの上昇は13%だったといった報告がある。
一方、アイスホッケー選手の25(OH)DとVO2maxとの間に相関はないという報告、ゲールサッカー選手の72%がビタミンD不足であり、それに対して3,000 IU/日(75μg/日)、12週間のサプリを摂取することでビタミンD不足は是正されるものの、VO2maxに有意な変化はなかったという報告などがある。このトピックについてはさらなる研究が必要とされる。
同様に、筋力およびスプリントパフォーマンスとの関連についても、より多くの研究を必要とする段階だ。
回復とビタミンD
回復の促進はアスリートにとって大きなメリットであり、迅速な回復が達成されることで高強度のトレーニングをより高頻度に行うことが可能になる。回復に対するビタミンDの潜在的な有用性は、抗炎症作用によって発揮されると考えられる。また、トレーニング後に生じる骨格筋組織の再構築の最中に、活性型ビタミンDがその過程を促進することが実験動物において観察されている。
ラットのヒラメ筋に筋肉重量1kgあたり33万2,000 IU(8,300μg)のビタミンDを投与した場合と、3万3,200 IU(830μg)を投与した場合とでは、前者においてアポトーシスが有意に抑制されることが示された。骨格筋の修復に不可欠な細胞外マトリックスタンパク質の増加も認められ、細胞代謝回転の上昇によって回復が促進されると考えられる。ヒトにおいてもビタミンDサプリ摂取によってトレーニング後のパフォーマンスの低下が6%にとどまり、プラセボ摂取時の32%低下よりも抑制され、条件間の差は48時間後にも持続していたという報告がある。
その一方でサッカー選手を対象とする研究では、1週間に5万 IU(1,250μg)のビタミンDを8週間摂取しても、筋損傷パラメーターはプラセボ摂取群と有意差がないといった報告もみられ、回復に関してもやはり今後の研究が必要とされる。
最適なビタミンD摂取量
要約すると、動物実験では生理学的量を超えるビタミンD3が潜在的なエルゴジェニック効果をもたらし得ることが示されている。人間のスポーツパフォーマンスに対する介入効果は、恐らく、ビタミンDレベルが低い場合に顕著に認められるであろう。ベースライン値が低く「欠乏」に該当するような状態では、摂取による有意なパフォーマンス向上を期待できるかもしれないが、欠乏ではない場合はわずかな改善にとどまるかもしれない。
反対に、高レベルのビタミンD(100nmol/L超)は有害事象を増加させる可能性がある。よって、最適な血清レベルを75~100nmol/Lに維持することが目安となるのではないか。医師やサポートスタッフは、アスリートに対してサプリ摂取の必要性を判断するため、血清25(OH)Dを測定することを推奨する必要があるだろう。複数の研究から、4,000~5,000 IU(100〜125μg)という用量が、骨の健康、怪我のリスクの軽減、血清25(OH)Dの維持と正の相関があることが示されている。ただし、骨代謝な影響を及ぼすビタミンKとの関連もあり、今後の研究ではビタミンDとビタミンKの相互作用という観点も含めて、最適な用量を推測する必要があるだろう。
文献情報
原題のタイトルは、「Performance improvement in sport through vitamin D – a narrative review」。〔Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Nov;26(21):7756-7770〕
原文はこちら(European Review for Medical and Pharmacological Sciences)










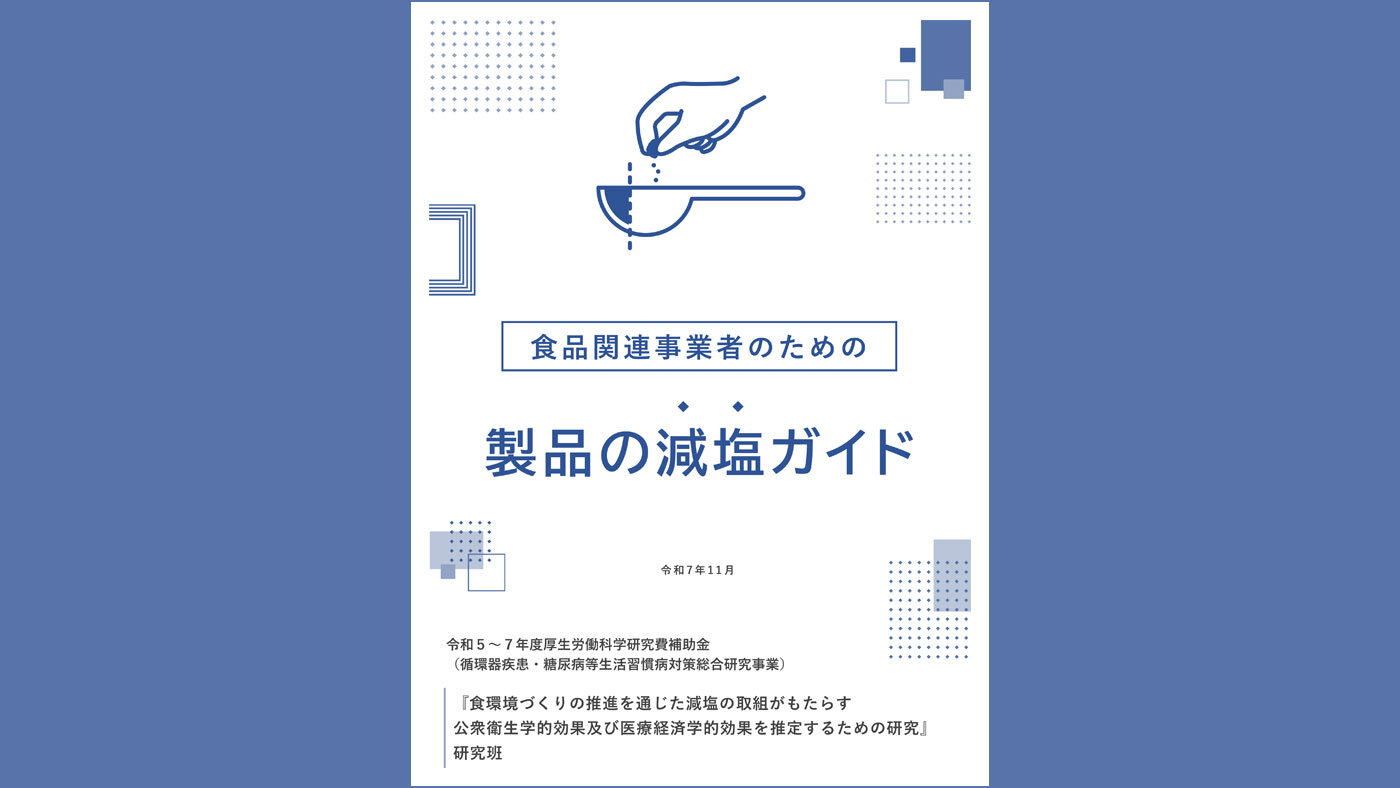












 熱中症予防情報
熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!
SNDJユニフォーム注文受付中!










